ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
脳&心理&人工知能
まじめに動物の言語を考えてみた(カーシェンバウム)
『まじめに動物の言語を考えてみた』2025/5/13
アリク カーシェンバウム (著), 的場 知之 (翻訳)
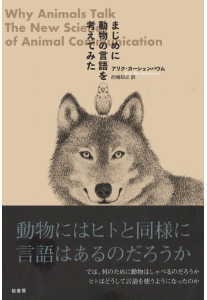
(感想)
なぜ動物が話すのか(話す必要があるのか)を理解することで、初めて動物のコミュニケーションが理解できるようになります。この本でカーシェンバウムさんは、自分自身のフィールドワークでの観察をもとに、動物の行動を科学的に明らかにしていきます。
オオカミ、イルカ、インコ、ハイラックス、テナガザル、チンパンジー、そしてヒト……動物のコミュニケーションの複雑さと、それが動物の社会的行動全体とどのように関わっているのかの観察を通して、すべての動物、さらには人間のコミュニケーションに共通するものを探っている本です。
オオカミが遠吠えをするのは、相手を追い払うためだけでなく、自分がどこにいるのかという情報を家族に提供したり、助けが必要なときに仲間を呼んだりするためのようです。
ヨウム(インコ)はまるで人間のような言語能力を持っているように見えますが、彼らの会話能力のルーツは、何百羽ものヨウムが一緒に暮らすコロニーで、食べ物や捕食者、そして主にお互いについての情報を共有するという不思議な共同生活にもありそう。
そしてチンパンジーは、常に変化する友情とライバルの網の目の中で生きていて、コミュニケーションをとることで、すべてのチンパンジーが自分の立ち位置を知ることができる……要するに「自分たちの社会の歯車をスムーズに回すために、コミュニケーションが必要」なのです。
なお本書では、コミュニケーションのうち「音声」だけに的を絞っていますが、その理由は次の2つだそうです。
1)コミュニケーション媒体のなかで、重要な4つの特徴を備えているのは音声だけ(長距離を伝わる・瞬時に遠くまで伝わる・多くの情報を内包しうる・障害物を超えて伝わる)
2)知られている限り唯一の本物の言語(=ヒトの言語)は音声が主体
*
「第2章 イルカ」によると、イルカたちは絶え間なく音を発している(クリック、ホイッスル、バズがひっきりなしに変化する)のですが、彼らが「音声」を利用する理由は、次のような環境にもありそうです。
「音は水中をよく伝わる。だからイルカは音声を主要なコミュニケーション手段としている。よほど澄みきった海でないかぎり、僕たちに見えるのはせいぜい一〇メートル先までなので、視覚的コミュニケーションを使える範囲は限られる。」
……イルカの社会が「離合集散型」であることも、彼らが音声コミュニケーションを発達させた理由かもしれません。
「(前略)世界にはたくさんの種のイルカがいるが、もっとも研究が進んでいるハンドウイルカとタイセイヨウマダライルカは、いずれも「離合集散型」と呼ばれる社会のなかで生きている。これは、ある個体と顔見知りの個体すべてからなる関係の輪の大きさはある程度固定的だが、関係の輪そのものは流動的である、という意味だ。」
……こういう社会では、以前に会ったことのある個体のことを覚えておく方が、都合がいいのです。また彼らはとても社会的な賢い生物で……
・「イルカはとても協力的な動物で、例えば魚を獲るときも力を合わせて効率を上げる。敵味方を正しく認識できれば、協力はスムーズになるだろう。」
・「(前略)大集団をつくって生活し、そのなかで複雑な相互作用をする動物には、他個体に呼びかけ、物体を区別し、情報のやりとりをする能力が必要だ。」
……イルカについては、大量の録音データをAIでビッグデータ分析する研究もされているようです。いつか彼らの言葉が分かる日がくるのでしょうか? ワクワクしますね☆
また本書でとても興味深かったのが、「第5章 テナガザル」と、「第6章 チンパンジー」。チンパンジーが人類と近いのに対して、テナガザルは「僕たちともっとも縁遠い」類人猿なのですが、実はコミュニケーションに関しては、チンパンジーよりテナガザルの方が、私たちに近いのかもしれません。
「(前略)現生のすべての類人猿のなかで、ヒトとテナガザルだけが複雑な音声を利用してコミュニケーションをとる。」
……テナガザルの歌には、自らの存在や縄張りを主張する機能の他、つがいのオスとメスの絆を強める機能があるようです。しかもテナガザルには、歌の学習システムがあるようで……
「(前略)テナガザルの母親は、積極的に歌を変化させて娘の学習を手助けする。娘が正確に復唱できるように、ピッチとテンポを調整するのだ。」
……これに対してチンパンジーは、発話より手話(ジェスチャー)やコンピュータインターフェースを通じたコミュニケーションの方が得意のようです。声はコミュニケーションというよりも情動を表すのに使われているようで……
「(前略)高度な認知能力や豊富な語彙に反して、チンパンジーの発声は往々にして本能的なものだ。」
……チンパンジーは賢いのですが、コミュニケーションは他の動物とあまり変わらないようでした。
でもチンパンジーは他の動物にない(人間と同じような)特質があり、それは「自分が知っていることを他者も知っているとは限らないと認識している」こと。次のように書いてありました。
「(前略)他個体が自分とは別の存在だと認識できれば、他者は独自の思考や欲求や意図をもっていることも理解できるはすだ。現生のチンパンジーの複雑な同盟形成行動は、かれらが少なくとも他者操作のある程度の心得をもっていて、他者の思考を読み、それを自己利益につなげようとしていることを裏づける。そして、このような複雑な意識が形成されたあと――おそらくは形成されて初めて――その動物の脳は一種の言語を実現できる程度に複雑になったのだろう。(中略)もちろん、複雑な意識さえあれば言語の誕生が保証されるわけではなく、チンパンジーはおそらく、この大きな跳躍を果たさなかった。それでも、このような脳が必要であることは、ほかの動物に僕たちのような言語が見られない理由のひとつだろう。」
……なるほど。ヒトと違ってチンパンジーは言語能力を発展させませんでしたが、おそらく彼らはその必要性を感じなかったのでしょう。次のようにも書いてありました。
「(前略)チンパンジーはヒトの下位互換ではない。かれらはかれらの生活様式に見事に適応しているのだから、大きなお世話だし、それに率直に言って、現代人のほとんどは、チンパンジーの社会に放り込まれたら一週間と生き延びられないだろう。」
……確かに、そうですね(苦笑)。
『まじめに動物の言語を考えてみた』……動物のコミュニケーションの仕方の観察を通じて、コミュニケーションや言語の本質や進化について深く考察している本で、とても参考になりました(動物の言語については、もちろん、まだ翻訳できるまでには至っていませんが……)。興味のある方は、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『まじめに動物の言語を考えてみた』