ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
脳&心理&人工知能
高校生に知ってほしい心理学-第3版(宮本聡介)
『高校生に知ってほしい心理学-第3版: どう役立つ?どう活かせる?』2024/8/28
宮本 聡介 (編集), 伊藤 拓 (編集)
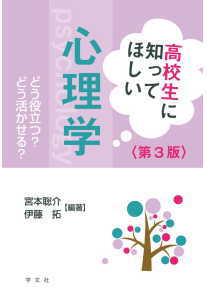
(感想)
「心理学」のおもしろさ、学問的な意義、そして今現在の本当の姿をできるだけ分かりやすく伝えるとともに、心理学とは何か、大学でどういったことを学べるのか、学ぶことでどう活かせるのか?などについて紹介してくれる本で、主な内容は次の通りです。
はじめに
第1章 心理学とは何か
第1節 心理学を知ろう
第2節 心理学の全体像と隣接領域
第2章 大学で学ぶ心理学
第1節 講義
第2節 実習
第3節 ゼミナール(ゼミ)
第4節 卒業論文
第5節 心理学をどう生かすか
第3章 基礎系心理学
第1節 認知心理学にAttention please!
第2節 社会の影響を科学する
第3節 ヒトのこころの発達を理解する
第4節 社会や集団における心理学を理解する
第5節 犯罪と向き合う心理学
第6節 こころを測る
第4章 臨床系心理学
第1節 こころの問題を見立てる
第2節 生徒の問題解決をサポートする
第3節 からだの病気に心理学は何ができるか
第4節 発達臨床心理学:発達の多様性の理解と支援
第5節 家族とこころの健康
第6節 「環境」と「個人」の関わりから悩みを理解する
第7節 集団による癒しと成長
第8節 心理学と精神医学の接点
第5章 心理学と進路
第1節 卒業後の進路
第2節 資格
おわりに
*
「第1章 心理学とは何か」によると、次の二つの答えがあるそうです。
1)こころの仕組みや働きを明らかにしようとする学問
2)こころや行動の科学
……科学は、実証性、客観性、再現性の3つを満たすことが求められるので、超常現象などは対象外になっているそうです。
「第3章 基礎系心理学」では、認知心理学や社会心理学などの概要が書いてありました。
例えば認知心理学では……
「認知心理学では、(中略)認知の働きを調査や実験を通じて科学的に明らかにすることを目的としています。認知心理学の主な研究分野には知覚、記憶、注意、言語、思考などがありますが、研究領域は年々拡大し、基礎研究とともに応用的な研究も増えています。」
……ここでは、注意の大事な特性として「利用量の限界」があることなどが紹介されていました。
また発達心理学では、発達心理学者のピアジェが「3つ山課題の実験」を行って、7歳以前の子どもが見た目にとらわれた自己中心的思考を行ってしまうのに対して、7歳から11歳の子どもは、ある程度まで論理的思考を行えると指摘したことが紹介されていました……これは子どもたちを見ていると、実際にそうなんだろうなーと思えることで……それをこんなふうに心理学実験で科学的に明らかにしてくれているんですね……。
また次のようなことも……
「(前略)心理学で発見される法則とは、「大多数の人びとにおおよそ当てはまる」ような集団の傾向であることがほとんどです。」
……心理学は統計を使って人びとの全体の傾向を把握するようです(心理統計学)。
ここでは、「新しい学問評価」の作り方についても紹介されていました。
「評価が公平であるためには、すくなくともテストの得点が、1.テストの難易度に依存しない、2.一緒に受検した集団の能力に依存しない、という2つの性質をもっていなければなりません。(中略)
この2つの問題に、理論的にも実践的にも見事に対応したのが、項目反応理論(Item Response Theory:以降ではIRTと略記)です。(中略)
IRTによるテスト運営の要は項目プールです。項目プールとは(問題)項目の巨大なデーベースのことです。作成された項目は、受検者に提示される前に、モニター(受検者集団)に仮提出され、回答データが収集されます。この回答データを利用し、すべての項目について難易度や能力の高低を識別する性能について統計的な数値を算出しておきます。この数値がついた項目群をプールに収めていくわけです。項目プールが一定以上の規模になったら、(中略)複数のテストの行い、一般受検者に提供します。(中略)
わかりやすくいえば、IRTのスコアは基準集団内での偏差値です。たとえば、項目プールから作成された3つのテストのうち、あなたがどれを受検したとしても、常にひとつの基準集団内での偏差値が返されることになります。したがって、あなたの能力が同じであれば、一緒に受検した集団によらず、3つのテストのスコアは同じになるのです。」
……公平な評価をするためにも統計学が役だっているんですね。
その他、臨床心理学やカウンセリングについても概要解説がありました。
そして「第5章 心理学と進路」では、卒業後の進路として、国家公務員では、「家庭裁判所調査官」、「法務技官(心理)」、「法務教官」などの他、厚生労働省、警察庁、自衛隊にも心理系の職があること。地方公務員では、「児童心理司」の他、公立病院、公立の教育相談室、障害のある子どもや大人の支援施設で働いている人がいることが紹介されていました。
また心理専門職としての資格には、次のようなものがあるようです(一部の抜粋紹介です)。
1)公認心理師(「公認心理師法」(2017年施行)に基づいて誕生した心理専門職の国家資格)
2)臨床心理士(財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する資格)
3)認定心理士(公益財団法人日本心理学会が出している資格)
この他、教員免許がとれる大学もあるようでした(ただし心理学の単位の他に免許取得に必要な単位をとる必要あり)。
『高校生に知ってほしい心理学-第3版: どう役立つ?どう活かせる?』……心理学とは何か、大学でどういったことを学べるのかについて、総合的に概説してくれる本でした。心理学に興味がある方は、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『高校生に知ってほしい心理学-第3版』