ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
描画参考資料
博物館DXと次世代考古学(野口淳)
『博物館DXと次世代考古学』2024/9/12
野口 淳 (編集), 村野正景 (編集)
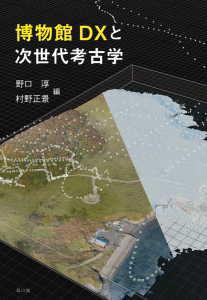
(感想)
考古学・博物館資料のデジタル化は、記録、保存、公開共有の新しいあり方や利用者の特別な体験をもたらす……博物館DXの背景や考え方、世界的な動向や日本での取り組みの現状がわかる初めての本です。
最初の「次世代考古学とは何か」によると、次世代考古学には、次の3つの特徴があるようです。
1)3D考古学(三次元計測法)
2)文・理・医の融合考古学(古代人骨のDNA解析や、宇宙線物理学(ミューオン透視)などの活用)
3)進化したパブリックアーケオロジー(研究成果を社会に還元)
……なるほど。三次元計測や、文・理・医の融合は、今後の考古学研究に大いに貢献してくれそうですね!
そして考古学だけでなく、博物館のDXでも、次のことが期待できるようです。
1)デジタル・アーカイブ化が資料の体系的な整理を可能にする
2)デジタル資料のオンライン公開が進めば、どこでも鑑賞できる(海外からも)
3)障害者・高齢者など博物館に足を運べない人でもアクセス可能になる
4)市民が主体的に参加できるようになる
*
特に「三次元計測法」は、立体形状が記録できると同時に、自由視点での観察を可能にするので、「1つしかない資料を同時に多数の人が立体的に鑑賞できる」という利点があり、これは学校の授業でとても役に立つようです。なぜなら対象物を「自分のタブレット端末で自由に見られる」から。……確かにそうですね! 学校行事で博物館見学に行っても、大勢の人たちの隙間から対象物を眺めながら進んでいくだけだと、「なんとなく眺めたなー」という感想しか持てないので、むしろ「自分のタブレット端末で自由に鑑賞」できるほうが、よりよく学習できそうな気がします(残念ながらオリジナルではありませんが……)。
本書では、博物館のDXの事例も多数見ることが出来ました。
例えば、「歴史都市京都のデジタル・ミュージアム(バーチャル京都)」の事例では、次のように書いてありました。
「立命館大学アート・リサーチセンターでは、2002―2006年度文部科学省21世紀COEプログラム「京都アート・エンターテインメント創成研究」において、歴史都市京都のあらゆる地理空間情報を網羅的に収集し、GIS上でそれらを自由に重ね合わせる仕組みとして、バーチャル京都を構築してきた。それは、最先端の3次元GISやVR技術を駆使した、時間時限を取り入れた4次元都市モデルと2次元WebGISをベースとしている。」
……なんと昭和期、明治・大正期、江戸期、平安期の京都を見られる(重ね合わせることもできる)ようです。この他にも「祇園祭デジタル・ミュージアム」なども行っているのだとか。
立命館大学だけでなく、京都府京都文化博物館も、別館の建物の3D化と環境モニタリング関連事業や、学校資料のデジタル化支援などを行っているようです。さすが歴史都市・京都ですね!
ところで、このような博物館のDXを実際に実現するためには、さまざまなシステムが必要で、「DX時代の資料・情報管理専門職とは、どのような存在なのか」というテーマには、次のことが書いてありました。
「デジタル環境における情報管理では、古典的には唯一無二の究極的な保存の対象であったオリジナルをモノとして同定するより、資料・情報の真正性、信頼性、完全性、アクセス可能からなる「要件」のメタデータによる管理、つまり業務コンテクストとプロセス、手続きと責任権限の管理が重要となる。また、資料の生成の場から文書館へのモノの移管が意味を失うことから、作成段階から利活用、廃棄、永久保存までの全過程を統合した管理プログラム、制度の設計が、つまり現場で生み出された資料を事後的に取り扱うのではなく、業務管理と文書記録管理が統合された上で、ルールの事前決定とその厳正な運用管理が求められる。最後に標準化の要請で、作成や利用の関係者・機関間、および関連管理機関間という縦と横の双方にわたって、可能な限り標準化された形式、フォーマット、手続きにそうことが求められる。」
……まさしく、その通りですね! 「資料のデジタル化」では、鑑賞などを行うために、さまざまなハードウェアやソフトウェアを必要とすることを忘れてはならないと思います。たとえば埴輪などのオリジナル資料は、それだけで「見る」「触る」ことが可能ですが、デジタル化された立体画像・埴輪は、「見るためのハード(画面)」+「それを動かすソフト」がなければ、何もできないわけで、例えば保存している機器が損傷したら見られなくなるだけでなく、jpegなどの画像規格や、資料を保存しているDBなどの規格が変更されたら、全博物館のデジタル資料が全滅するという事態すら起こりかねません。だから「デジタル化」だけでなく、「オリジナルの保存」も、やはりとても大事だと思います。
また「資料のデジタル化」では、デジカメでの撮影などの作業が膨大に必要になります。これに関しては、飛騨みやがわ考古民族資料館の事例がとても参考になりました。
「(前略)岐阜県飛騨市では、2021年から毎年「3D合宿」として、飛騨みやがわ考古民族資料館で、館蔵・展示資料の3Dデータ化を、一般参加者を募集して実施している。」
……飛騨みやがわ考古民族資料館には、資料館の存続を目指す取り組みの「石棒クラブ」があるそうです。
この石棒クラブでは、「一日一石棒」という取り組み(塩屋金清仁社遺跡で出土した石棒類1,074点を撮影し、ほぼ毎日1点ずつInstagramで画像を公開している)を行っているそうです。さらに2023年11月には、インターネット回線を利用して無線LANを整備。スマートキーやネットワークカメラを利用して、学芸員や管理人が不在でも開館できる体制を整えたのだとか……素晴らしいですね! このように一般の人や学生が参加できる仕組みがあると、小さな博物館でも堅実にDXを進めやすいのではないでしょうか。
また西日本自然史系博物館ネットワークでは、拠点となる博物館に撮影スタジオを設置して、小規模館の標本等を持ち込み撮影できる体制を整備中だそうです。
『博物館DXと次世代考古学』……博物館DXの背景や考え方、世界的な動向や日本での取り組みの現状だけでなく、最新のDX技術についても解説してくれる本で、とても参考になりました。博物館が好きな方は、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『博物館DXと次世代考古学』