ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
描画参考資料
文化観光立国時代のやさしい博物館概論(幸泉満夫)
『文化観光立国時代のやさしい博物館概論』2025/1/6
幸泉 満夫 (著)
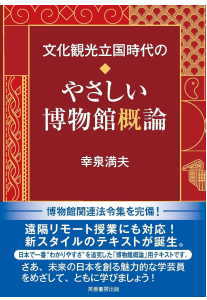
(感想)
最新の「博物館法令集」を完備し、リモート授業にも対応しやすい「博物館概論」テキストで、主な内容は次の通りです。
まえがき
第I部 博物館概論
第I章 まずは博物館を知ろう
第II章 学芸員をめぐる主な業務
第III章 博物館をめぐる法的枠組みの概要
第IV章 博物館の歴史
第V章 博物館の組織体制
第VI章 近未来に向けた明るい展望
第II部 博物館関連法令集
A 日本国憲法(抄)
B 教育基本法(抄)
C 社会教育法(抄)
D 文化芸術基本法(抄)
E 文化観光推進法(抄)
F 博物館法
G 博物館法施行規則
H 地方自治法(抄)
I 文化財保護法(抄)
J 公開承認施設に関する規定等(抄)
参考文献
あとがき
著者略歴
*
2022年開催のICOM(国際博物館会議)第26回総会で採択された定義によると、博物館とは「有形及び無形の遺産を研究、収集、保存、解釈、展示する、社会のための非営利の常設機関である。博物館は一般に公開され、誰もが利用でき、包摂(ほうせつ)的であって、多様性と持続可能性を育む。倫理的かつ専門性をもってコミュニケーションを図り、コミュニティの参加とともに博物館は活動し、教育、愉しみ、省察(せいさつ)と知識共有のための様々な経験を提供する。」と定められているそうです。
そして博物館を支える学芸員の五大業務は、収集、保管、展示、調査研究、教育普及なのだとか。
「第III章 博物館をめぐる法的枠組みの概要」では、日本国憲法の精神とその概略、教育基本法の概略、社会教育法の概略、文化芸術基本法の概要、文化観光推進法の概要、博物館法の解釈と施行規則への解釈、関連する地方自治法の概略、文化財保護法の概要、公開承認施設についてなど、博物館関連の法律について学ぶことができます。
なお日本では博物館法で学芸員資格の取得方法が定められているのですが、なんと「こうした国民への資格制度は海外ではめずらしく、ほとんど見当たらない」そうです! そうだったんだ……。
続く「第IV章 博物館の歴史」では、次のような博物館の黎明期の話から、近現代の博物館に至るまでの歴史を知ることができます。
「今日、世界中で通用する”Museum(ミュージアム)”という英語表記の語源は、紀元前280年ごろ(今から2300年ほど前)、古代ギリシア(ギリシャ)で信仰されていた女神たち「Mousa:ム(ー)サ」(複数形Mousai:ムーサイ、英語表現のMuse:ミューズ)を祀る神殿「Mouseion:ム(ー)セイオン」にまで、さかのぼります。」
そして日本における博物館の源流としては、奈良県東大寺の正倉院宝庫が紹介されていました。
さらに「第V章 博物館の組織体制」では、「独立行政法人 国立文化財機構の組織体制図」、や「東京国立博物館の組織体制図」などを見ることが出来ます。
そして本書で最も興味津々だったのが、「第VI章 近未来に向けた明るい展望」。ここでは、地域と博物館をつなぐ3つの先進的事例として、「沖縄ガンガラーの谷」、「愛知県瀬戸市のエコミュージアム構想と「窯垣の小径」」、「長州藩ゆかりの地、萩の城下町とまちじゅう博物館」が紹介されていました。どれもとても魅力的なのですが、なかでも次の「沖縄ガンガラーの谷」が素晴らしく感じました。
・「沖縄ガンガラーの谷(ツアーガイドを介した旧石器洞窟と地域観光)」
「このツアーでは、「サキタリ洞窟跡」のある「ケイブカフェ(CAVE CAFE)」をスタート地点とし、天然の洞窟や熱帯林の生い茂る「アカギの大原生林」、ガジュマルの巨木、展望台からの景観観察、そして再び先史時代の「武芸洞遺跡」までをめぐるなかで、オリジナルで偉大な歴史と自然、風土を、楽しみながらもしっかりと学べるという、まさに理想的なコースが実現されているのです。
ツアーでは、知識豊かな専門ガイド員とともに、整備された舗道上を徒歩でゆっくり、めぐっていきます。全長約1km、所要時間も約90分ほどです。」
「(前略)定期的に実施される発掘期間中では、そうしたカフェテラスで気軽に軽食を楽しみながら、目の前で、県立博物館等による発掘調査の様子も見学できます。」
……旧石器原人・港川人が発見された港川フィッシャー遺跡(石灰岩断層崖)を一望できる、美しい樹上ツリーテラスにも行けるようで……とても魅力的ですね!
また瀬戸市、萩市も「まちじゅう博物館」になっているようです☆
これら3つの事例に共通している要素は……
「(前略)いずれも世界じゅうどこにもマネのできない固有の、すばらしい「地域資源(史跡や文化的景観、自然環境、伝統産業など)」が背景にあり、それらを、地域の人びとの力で上手く活用しようとする姿ではなかったでしょうか。」
……博物館は、「「博物館資料」をもとに利用者すべての学習機会を保証し、あらゆる手段のもとでサポートしていくことこそが、博物館に課せられた真の使命」で、「博物館は活動成果をすべて、利用者へと普及還元させることを使命としている」ということですが、これら3事例は、 それを「観光資源」としても活かしている、とても素晴らしい試みだと感心させられました。
そして本書には、各章の最後に「リモート課題」という問題集がついています。これは自習をするときにも利用できると思います。
また第II部の最新の「関連法令集」は、博物館関連の部分だけが「抄」として掲載されているので、これもとても便利に使えると思います。
まさにタイトル通りの『文化観光立国時代のやさしい博物館概論』……博物館学を学びたい方はもちろんのこと、「まちづくり」に興味のある方も、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『文化観光立国時代のやさしい博物館概論』