ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
ビジネス・問題解決&トラブル対応
間違い学(松尾太加志)
『間違い学:「ゼロリスク」と「レジリエンス」 (新潮新書 1048)』2024/6/17
松尾 太加志 (著)
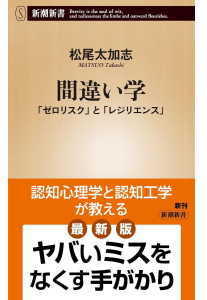
(感想)
なぜ、どのように間違いは起こるのか? そのミスを大惨事につなげないためにはどうしたらいいのか? について考察している本で、主な内容は次の通りです。
はじめに
第1章 ヒューマンエラーがもたらす事故
手術で患者を取り違えた事故【事例1-1】/複数のエラーが生じて事故に至る/どうすべきだったか/リストバンドの装着ミス【事例1-2】/ITやDXは新たなヒューマンエラーを生み出す
第2章 ヒューマンエラーとは
キャッシュレス決済での失敗【事例2】/本来できたはずなのに/エラーとそうでない場合の違い/ヒューマンエラーの定義/モノや機器と関わるからエラーが生じる/AIも万能ではない
第3章 エラーをした人は悪いのか?
遮断機を上げざるをえなかった開かずの踏切の事故【事例3】/不完全なシステムを人が調整している/システムの問題がヒューマンエラーを生む/人を責めない対策/意味のない「気をつける」対策/注意すると改善されるという誤謬/後知恵バイアスによる指摘―後だしじゃんけん―
第4章 外的手がかりでヒューマンエラーに気づかせる
欠席者を合格にしてしまった入試ミス【事例4】/外的手がかりで防止策を検討/外的手がかりを考えてみることが大事
第5章 外的手がかりの枠組みでエラー防止を整理
インターホンの配線間違い【事例5】/文書で気づかされる/表示で気づかされる/対象で気づかされる/電子アシスタントで気づかされる/人(他者)から気づかされる/外的手がかりの効果と実現可能性/5つの枠組みで防止策を現場で考える
第6章 そのときの状況がエラーを招く
薬の処方ミスによる死亡事故【事例6】/さまざまな背景要因がエラーを誘発/医師のおかれた多忙な背景/モノやシステムの改善によるエラー防止策
第7章 外的手がかりは使いものになるのか
照合せずに輸血をしてしまった【事例7】/外的手がかりは使ってもらえるか?―動機づけ理論―/人の行動は誘因と動因で決まる/外的手がかりは何を防いでいるのか/行為をどうとらえるか――行為の制止、防護、修正/外的手がかりだけでヒューマンエラーは防ぐことができるのか
第8章 IT、DX、AIはヒューマンエラーを防止するのか
人は進化していない/人を介さないことでエラーがなくなる/電子アシスタントによるエラーに気づかせるしくみ/エラーに気づきやすいインタフェースが可能か/ネットワーク上の外的手がかり/人間をどう活かすか
第9章 ゼロリスクを求める危険性
新型コロナウイルスへの対処の異常さ/複雑なシステムには必ずリスクが/Safety-I, Safety-IIの考え方/感染者ゼロを目指すSafety-I、ウィズコロナのSafety-II/人間というシステムに合うのはSafety-II/レジリエンスという考え方/リスクとベネフィットを考える/人工知能がうまくいくのは/エラーに気づいてうまく対処できればよい
おわりに
参考文献
*
「はじめに」には次のように書いてありました。
・「(前略)ヒューマンエラーをなくすには、気づいていない間違いに気づくようにすることが第一である。ただし、間違いに気づくように自分自身の行動を注意深く自己観察しなさいといったところで何も解決しない。精神論ではダメなのだ。間違いに気づくようにうまく工夫することが、エラーをなくすことにつながる。」
・「(前略)ヒューマンエラーというものは完全になくすことはできない。重要なのは、エラーが生じても大きな被害をもたらさないようにすることである。」
*
そして事例として「第1章 ヒューマンエラーがもたらす事故」では、心臓手術で患者を取り違えたという重大事故が、どのように起きたかが詳細に語られていました。まさに「複数のエラーが生じて事故に至る」状況だったようで、うーん、こんな不幸なヒューマンエラーの連続が起こるものなんだなーと恐ろしくなりました。最近は病院で、「フルネームで名乗ってください」と言われることがありますが、このような重大事故を起こさないために「患者自身に名乗らせる」ように変わったそうです。
また患者を間違えないために付けられるようになったリストバンドが取り違えられたという事例も紹介されていて……ITやDXだけでは、ヒューマンエラーは防げないことを再確認させられました(涙)。
「第3章 エラーをした人は悪いのか?」では、ヒューマンエラーを罰則で防ごうとすると、さらに大きな問題になることが、次のように指摘されていました。
「罰則を前提とすると何が生じるかというと、エラーの低減ではなく、隠ぺいにつながっていく。隠ぺいされてしまうと、潜在的に存在している問題が解決されないままで、小さなエラーで済んだものが大きなものとなって顕在化してしまう。」
……全くその通りだと思います。
そして「第4章 外的手がかりでヒューマンエラーに気づかせる」と、「第5章 外的手がかりの枠組みでエラー防止を整理」では、入試での受験生の取り違え、インターホンの配線間違いの事例で、どのようにすれば間違いを防止できるのかが具体的に示されていました(文書、表示、対象、電子アシスタント、人(他者)など)。
最終章の「第9章 ゼロリスクを求める危険性」では、安全心理学者ホルナゲルのSafety-I, Safety-IIという考え方が紹介されています。
「Safety-I」は、エラーをなくすことが目標ですが、
「Safety-II」は……
「要は安全になればいい。エラーをなくすことを考えるよりも、行いたい仕事や作業が満足のいくレベルに達することを目指せばよい。エラーは起こってもいい。ただし、エラーが起こっても外的手がかりで気づかされ、それにうまく対処することを考える。そう考えると安全のとらえ方が違う。安全というのはエラーがないことではなく、事がうまくいくようにすることである。それがSafety-IIの考え方だ。」
……ヒューマンエラーを完全になくすことが不可能である以上、Safety-IIの方が、現実的に役に立つのではないかと思います。
この章は次の文章で締めくくられていました。
「人間に求められるのは、ヒューマンエラーを絶対にしないことではない。ITやDXが進展した時代では、機械のほうが正確に効率よくいろいろなことをこなしてくれる。機械的な細かい業務や作業は機械に任せ、人間はもっと大局的な見地から、想定されないことが生じたときにどう対処できるかが求められていると考える。」
『間違い学:「ゼロリスク」と「レジリエンス」』……手術患者の取り違え、投薬ミスによる死亡事故、手動遮断機の操作ミスで起きた踏切事故などの事例を通して、どのように間違いは起こるのか? そのミスを大惨事につなげないためにはどうしたらいいのか? を具体的に検討している本で、とても参考になりました。みなさんも、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『間違い学:「ゼロリスク」と「レジリエンス」』