ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
数学・統計・物理
学び直し高校物理(田口善弘)
『学び直し高校物理 挫折者のための超入門 (講談社現代新書)』2024/2/22
田口 善弘 (著)
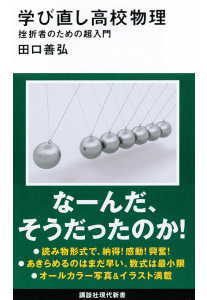
(感想)
高校物理の内容について、楽しんで読めるように、たとえ話や歴史的なエピソードを交えて、分かりやすく解説してくれる本です。『学び直し高校物理』というタイトルに思わず怯んでしまう人も多いと思いますが(私もです)、この本は「挫折者のための超入門」という副タイトルがついている通り、数式がほとんどなく、Newtonなどの科学雑誌の記事のように楽しく読めました。
「はじめに」には次のように書いてあります。
「本書では、高校物理の教科書に登場するお馴染みのテーマを題材に、物理法則が導き出された「理由」を読者とともに考えていく。」
……本当にありがたいことです。
さて最初の章には「物理は質量がすべて」という項目がついていました。……え? 質量?
「高校物理の説明を始めるにあたってもっとも重要なことは何か。それは「質量」だと思う。」
「質量とは、端的に言えば、物質の動きにくさの度合いである。物質の質量は、地球上でも、宇宙ステーションでも、月面でも同じである。」
……えー、そうだったんだ。どんな場所でも変わらない「重さ」かと思っていました(重力の影響を差し引いた「重さ」みたいな感じ?)。……なるほど「動きにくさの度合い」だったのか……。
また次の章の「曲がっていても実はまっすぐ(等速直線運動)」では、蜃気楼について……
「光は密度が大きいほど遅くなる傾向がある。海面の温度が低いと海面すれすれの空気は冷やされて密度が大きくなるので光速が遅くなる。すると、光の経路が曲がる。しかし、我々にはそんなことはわからず光はまっすぐ来たと思うので、地上にある家が空中に浮かんで見える。」
……光は「いつも同じ光速で進む」わけではないんですね。実は「光は速度が遅いところは避けて最短距離を進む」ので、その結果、光は「屈折」することがあるようです。例えば重力レンズも……
「重力による光の屈折が起きるのも同じような理由だが、そこで最短時間で移動するのではなく、時空間内での移動距離が最短になるように移動する。」
……蜃気楼と逃げ水が同じ原理で起こっているのは知っていましたが、重力レンズも同じような理由だったんですね……。
そして驚いたのが、「恐竜はなぜ絶滅したのか?」に関する説明。
「(前略)地表に落ちて来る隕石には、空気抵抗を考えない場合、必ずこれ以上の速度でなくてはいけない、という最低の値があり、その値はなんと秒速(時速ではない!)11.2kmというとんでもない速さだ(中略)
隕石が地球に衝突するときには、膨大な位置エネルギーが放出される。(中略)
地面に衝突したらこの膨大なエネルギーはどうなるのか? エネルギー保存則があるので、隕石の持っているエネルギーがなくなることはない。ほとんどの場合、それは熱になる。前述したように一辺12mの隕石が落ちてきたら原爆1個分の熱が発生する。
ユカタン半島に落下した巨大隕石は直径10kmから15kmだったから、これはもう大爆発になるしかないではないか!」
……そうだったんだ! 隕石の落下速度に「最低値」があったことすら知りませんでした!
またモーターと発電機は、構造的には同じようなものだそうで…・・・
「(前略)モーターと発電機に構造上の大きな違いはない。磁場の中で電流を流してコイルを回転させるのがモーターなら、コイルのほうは動かさずに磁場のほうを回転させて電流を発生させるのが発電機、というわけだ。」
……そして直流と交流にまつわる、エジソンさん(直流陣営)とテスラさん(交流陣営)の争いについては、「直流発電機」が、磁石を固定してコイルを回転させるもので、構造上の問題から送電ロスが大きい一方、構造的にその逆をいく「交流発電機」は、送電ロスが少ない上に、電圧の変換が容易だった(何もしなくても電流の高さや向きが変動するので、変動磁場を簡単に作り出せる)というメリットがあり、最終的に送電に「交流」が採用されたのは当然だったということが、とても分かりやすく解説されていました。
また雲の発生にはシャルルの法則(圧力が一定の場合、体積は温度に比例する)が関係しているそうで……
「(前略)地表面付近の大気圧は1気圧で一定のため、大地から伝わった熱で大気塊(空気の塊のこと)の温度が上昇しても、圧力は変わらない。
一方で、シャルルの法則で、温度上昇により大気は膨張する。膨張した大気塊の密度は下がって軽くなるので、大気塊はぐんぐんと上昇を始める。」
……そして雲が出来て降雨するまでは、次のようなことが起こるそうです。
1)大地が太陽熱で暖められる
2)大地の熱が、接する大気塊へ移動
3)大気塊の温度が上昇すると、その体積が膨張。浮力が生じて、上昇する
4)上空の大気圧は低いため、大気塊の体積がさらに膨張し、圧力が低下し、熱も失われる
5)大気塊の温度が下がり、水滴や氷の粒が生まれて雲ができる
6)水滴や氷の粒が大きくなって、支えられなくなり、降雨が始まる
*
……「シャルルの法則」のような物理法則は、会議室(や教科書)で起こっているのではなく「現場で起こっている」んですね(笑)。
『学び直し高校物理 挫折者のための超入門』……小学校の頃、理科は大好きだったのに、なぜかその後、数学や物理が苦手だった私にとって、とても勉強になる、まさに『学び直し高校物理』でした。高校物理で挫折した(または履修すらしなかった)けど、あらためて学び直したい方は、ぜひ読んでみてください☆ 現在、高校で物理を学んでいる方にも、お勧めです☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。
『学び直し高校物理』