ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
歴史
史料と旅する中世ヨーロッパ(図師宣忠)
『史料と旅する中世ヨーロッパ』2025/4/5
図師宣忠 (編集), 中村敦子 (編集), 西岡健司 (編集)
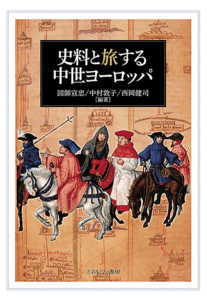
(感想)
教科書などの歴史叙述の背後にどのような史料が「隠れて」いるかに気づき、それらの史料を読み解くコツを学ぶとともに、史料に基づいた歴史像とは何かを考えるために編まれたテキストで、主な内容は次の通りです。
序 章 史料を紐解き,過去の世界に旅しよう(図師宣忠・中村敦子・西岡健司)
第Ⅰ部 権威と統治
第1章 王は「強かった」のか?──ノルマン征服とウィリアム征服王(中村敦子)
第2章 イコノクラスムのはじまりとレオン3世──8世紀のビザンツ帝国をとりまく世界(小林 功)
第3章 聖性・儀礼・象徴──中世後期チェコの国王戴冠式式次第より(藤井真生)
史料への扉1 アイスランド・サガ──過去の真実を物語る(?松本 涼)
史料への扉2 史料としてのビザンツ文学(上柿智生)
第Ⅱ部 教会と社会
第4章 辺境にみる西欧カトリック世界──13世紀スコットランドの一証書を通して(西岡健司)
第5章 正統と異端のはざまで──南フランスの異端審問記録にみる信仰のかたち(図師宣忠)
第6章 魔女裁判って中世ですよね?──例話集にみる魔術と悪魔(轟木広太郎)
第7章 「十字軍」とは何か?──12世紀の公会議・教会会議決議録より(櫻井康人)
史料への扉3 社会を通して大学を,大学を通して社会を読む(中田恵理子)
第Ⅲ部 都市と農村
第8章 都市と領主の付き合い方──中世のフランドル地方をめぐって(青谷秀紀)
第9章 つながり合う都市──ロンバルディア同盟にみる「都市同盟」の意味(佐藤公美)
第10章 都市と農村のあいだ──北イタリア・バッサーノの条例集にみる自治(髙田京比子)
第11章 抑圧された農民?──中世ドイツの農村社会(田中俊之)
史料への扉4 公証人記録──名もなき人々の生きた痕跡を探る(高田良太)
付録 中世ヨーロッパに関する史料の和訳図書リスト
索 引
*
「序章」には次のように書いてありました。
「本書は中世ヨーロッパという過去の世界への旅路を示すガイドブックとして編まれたものであり、史料を紐解きながら歴史的に中世を読み解くためのアプローチを紹介している。もちろんタイムマシンでもない限り、実際に中世の世界に「旅する」ことができるわけではない。だが、史料の読み解きを通じて適切な手続きに則った歴史的想像力を働かせることで、私たちは「過去の世界に触れる」ことができる。」
*
この本は、執筆者たちが「とっておきの」素材をもとに史料を紐解いて、その面白さを提示することで、読者に、ある歴史像の背景には必ず史料が存在することを意識させながら、歴史的な事象を、多角的に考えさせてくれます。
各章は、当該テーマの概説・史料と読み解き・ワークという展開で構成されていて、大学の史学科の授業に参加しているような気持ちにさせてくれます。
教科書で習った「中世ヨーロッパの歴史」についても、史料に基づいて検討することの大切さを教えてくれます。
例えば「第7章 「十字軍」とは何か?」では、「教科書における「十字軍」の記述」として、次のことが紹介されていました。
「(前略)イェルサレムを支配下に置いたセルジューク朝がアナトリアに進出すると、ビザンツ皇帝は脅威を感じ、教皇ウルバヌス2世に救援を求めた。これを受けた教皇は、1095年、クレルモン教会会議で聖地回復のための十字軍の派遣を提唱し、熱狂的な支持を集めた。
翌1096年、第1回十字軍が出発し、ここに、長期にわたる断続的な十字軍遠征が開始された。宗教的情熱をともなう大義は聖地イェルサレムの奪回にあったが、当初から関係者の思惑はさまざまであった。教皇は東西教会統一の主導権を握ろうとし、諸侯や騎士は武勲と領地・戦利品をねらい、民衆は贖宥や債務帳消しを求め、商人たちは経済的な利益を追求した。」
……確かに、このように習った記憶があります。
ここでは、この「十字軍」について、12世紀の公会議・教会会議にみる「十字軍」史料をもとに読み解いています。それによると「十字軍」の本質とは……
「(前略)「十字軍」とはキリスト教会の敵と戦うことによって認められる贖罪である、とまずは定義されなければならない。(中略)
さて、「贖罪」について注意しなければならないのは、カトリック世界においてはそれを認める権能をもつのはあくまでも教皇である、ということである。「贖罪」の中でもキリスト教会の敵と戦うことに認められたものは、一般に「十字軍特権」と呼ばれるものである。」
……犯罪者や違反者たちの贖罪の場としても「十字軍」が提供されていたようです。
また、十字軍は常に聖地イェルサレムに向かっていたのかと思っていましたが、実際には……
「(前略)一般には12世紀の間の「十字軍」は常に聖地を対象としたととらえられがちであるが、1130年代よりすでに聖地以外を対象とした「十字軍」が呼びかけられていた。」
……そうだったんですね。
「十字軍」関係の史料は割と多いようですが、その理由は……
「(前略)多くの「十字軍」士は遠征に出る前に、在地の教会との関係を修復するために寄進を行った。また、やはり「十字軍」士たちの多くは、遠征費をつくるために教会から借金をした。このために「十字軍」に関連する多くの証書が比較的多く現存することになるが、その内容の検討はもとより、副署人リストの分析から「十字軍」における人的ネットワークの実態が明らかにされつつある。」
……なるほど。このように「本物の史料」を分析することで、歴史をより正しく知ることが出来るんですね。もっとも歴史的資料は、著作者や権力者の思惑などで歪められていることも多いので、間違っている可能性についても十分に留意すべきようですが……。
『史料と旅する中世ヨーロッパ』……史料を読み解くことで過去の世界を旅することができることを、事例とともに解説してくれる本でした。とても勉強になるので、歴史に興味がある方は、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『史料と旅する中世ヨーロッパ』