ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
社会
海底の覇権争奪(土屋大洋)
『海底の覇権争奪 知られざる海底ケーブルの地政学』2025/4/27
土屋大洋 (著)
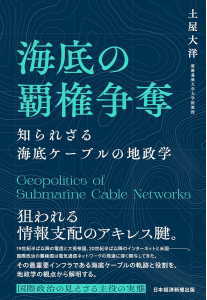
(感想)
地政学の観点から海底ケーブルの現代における意義を解明し、その知られざる実態に迫っている本で、主な内容は次の通りです。
Ⅰ 電信の大英帝国からインターネットの米国へ
Ⅱ 大日本帝国と海底ケーブル
Ⅲ 太平洋横断海底ケーブルのドラマ
Ⅳ 接続の力学 太平洋島嶼国におけるデジタル・デバイド
Ⅴ 攻防 海底ケーブルの地政学
Ⅵ サイバーグレートゲーム 海底ケーブルの地経学
終章 高まり続ける重要度
*
「Ⅰ 電信の大英帝国からインターネットの米国へ」によると……
「電気通信ネットワークの発達を見ると、19世紀半ば以降の電信と大英帝国、20世紀半ば以降のインターネットと米国という、それぞれの時代の国際政治の覇権国が深く関与していることが知られている。」
……海底ケーブルの実用化は1850年、英仏間のドーバー海峡から始まったそうです。英国はいち早く電信・通信の活用を始め、世界各地の植民地を海底ケーブルでつなぎ、ロンドンの指令を短時間で帝国中に伝えるとともに、貿易を活性化させ世界の覇権国となりました。
そして1914年に第一次世界大戦が始まるやいなや、英国はドイツの海底ケーブルを切断しました。この時すでに海底ケーブルは、戦略的にも重要なものとなっていたのです。さらに……
「(前略)第二次世界大戦後の通信需要の高まりは、新しい技術を求めることになった。それに応えたのが、人工衛星による通信および海底中継器を用いた新型の同軸ケーブルシステムである。」
……切断されやすく容量も不足していた海底ケーブルは、同軸ケーブルへと進化していきました。そして同軸ケーブルと人工衛星を主導したのは米国。米国が英国の覇権を崩していきます。
1989年には光ファイバーを使った光海底ケーブルが敷設されるようになり、これは大容量で衛星通信を凌駕するようになりました。
・「この通信衛星および光海底ケーブルという二つの技術革新の中心にいるのは米国であった。」
・「本来、大西洋と太平洋という二つの大きな大洋に隔てられた米国は、地理的にはハブになる要素は弱い。しかし、国際政治経済における覇権的な地位をテコとし、技術によって大西洋ケーブルと太平洋ケーブルを敷設し、インターネットという新しい技術で需要を喚起することで、米国は通信のハブとなっている。」
*
……このように海底ケーブルの覇権は英国から米国へ移ってきたんですね。ちなみに日本は意外に早い時期から健闘していて、1978年時点で、海底ケーブル本数の多い最終陸揚げ国は、米国、英国、カナダ、日本、フランスだったようです。
また「Ⅱ 大日本帝国と海底ケーブル」でも、日本がかなり早い時期から「通信」技術を取り入れていたことに驚きました。
「日本国内での電信線敷設は、明治維新の翌年の1869(明治2)年に東京-横浜間で行われた。」
……明治維新の翌年にはすでに電信線を敷設していたんですね!
そして日本初の国際海底ケーブル陸揚げの地は、長崎(1871に最初の国際ケーブルが長崎に陸揚げ、同年ウラジオストクとも接続。ただし敷設したのはデンマークの大北電信)。すでに1942年には、日本の主な島々だけでなく、朝鮮半島や中国、台湾など諸外国にも海底ケーブルがつながっていたようです。
「海底ケーブルは、100年前に既に政治、経済、そして軍事にとって重要な役割を果たすインフラストラクチャになっていた。しかし、第二次世界大戦の時代には、無線電信が重要な役割を果たすようになった。その間、海底ケーブルは各所で切断・破壊され、インフラストラクチャとして大きな損害を受けた。日本や台湾のような海洋国家が今後もし戦争に巻き込まれることがあれば、海底ケーブルは初期段階で破壊される可能性が高い。」
*
そして「Ⅲ 太平洋横断海底ケーブルのドラマ」、「Ⅳ 接続の力学 太平洋島嶼国におけるデジタル・デバイド」では、米国から戦略的に重要とされたハワイには早い時期に海底ケーブルが引かれた一方で、核持ち込みをめぐって米国と対立したパラオは米国との接続が遅れたことが紹介されていました。
・「(前略)21世紀のネットワークの時代においては、ネットワークにつながっていること、それも強大なハブに直結していることが重要になる。逆に、ネットワークにつながらない国家やアクターは取り残され、情報が入らず、政治、経済、文化など各方面で後れを取ることになる。」
・「(前略)一つの国家を一つのネットワークとして考えてみれば、小国は地域内で相互接続するよりも、できれば米国と直接つながってしまうほうが、効率が良い。したがって、多くの国が米国と直結する海底ケーブルを模索するようになる。」
*
「Ⅴ 攻防 海底ケーブルの地政学」では、海底ケーブルをめぐる諜報活動について……
「(前略)ソ連はミサイル基地との通信のために、オホーツク海に海底ケーブルを沈め、通信を行っていた。その存在を察知した米国は、同軸線から漏れ出る微弱電波を記録するために装置を開発し、海底でソ連のケーブルにつけることに成功した。定期的に装置を回収すると、暗号化されていないソ連の海底ケーブル通信を復元することができ、米国のインテリジェンス活動に大きく役立った。
このアイヴィーベル作戦は、実施していた米国国家安全保障局(NSA)から情報がソ連側に漏れ、ソ連が装置を奪ってしまったため、中止された。」
……でも米国の諜報活動が、これで終わったわけではありません。米国だけでなく各国とも密かに行っているようです。
「信号が同軸の銅線を流れる電気信号から光ファイバーを流れる光信号に変わったことで、各国政府の通信傍受は難しくなった。アイヴィーベル作戦のように海底で装置を付けても、光信号は微弱電波を発しないためである。海底での傍受が技術的に困難になったため、各国政府は陸揚局あるいはその先の通信事業者設備内での傍受にシフトした。
陸上に傍受拠点が移ったことで注目されるようになったのが、海底ケーブルの陸揚局のセキュリティである。」
*
さて「Ⅵ サイバーグレートゲーム 海底ケーブルの地経学」によると、浅い海底で使う海底ケーブルは、底引き網や錨、岩や海底ケーブル同士の接触による損傷を防ぐため、防護が厚くなっているそうです。その一方で、深い場所に設置される海底ケーブルは、接触損傷の可能性が低いこともあり、対象域への運搬や沈める作業の負荷を軽減させるため細くて軽くなっているのだとか。
そして「終章 高まり続ける重要度」では……
「(前略)海底ケーブルを引き上げて切断することは、現在では難しい。水深1500メートルより浅い水域では、ケーブルを海底に埋設し、露出しないようにしている。深海では潜水艦や無人潜水艇を使ってケーブルを探さなくてはならない。ところが、地上では陸揚局を比較的簡単に探すことができる。それらは多くの場合、純粋な民間設備のために、民主主義体制の国では軍が常時防護するというわけにはいかない。
さらに近年では、海底ケーブルのシステムにおけるサプライチェーン・リスクへの懸念が高まっている。こうしたサイバーシステムの製造は国境を越えるサプライチェーンによって行われており、一つの国のなかですべての部品の製造と組み立てを簡潔させることは難しい。仮にそれができたとしても、部品に不正が仕込まれる可能性を完全に排除することは難しいだろう。」
……さらに災害大国・日本にとっては、自然災害での切断というリスクもあります。
「海底ケーブルは様々な自然現象の影響を考慮して、ぴんと張った状態ではなく、冗長性を持たせてゆったりと引かれている。したがって、ある程度は地震の衝撃を吸収できるが、しかし、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震の衝撃はすさまじく、福島、茨城、千葉沖にあった海底ケーブルは多くの箇所で切断されてしまった。深い海底で高い水圧にさらされているケーブルは、海底で急激に地盤がずれることで、耐え切れずにちぎれてしまった。」
……海洋国日本にとって海底ケーブルは超重要なインフラなので、その安全性を守ることの他に、いざとなったときのバックアップとしての衛星通信も準備しておくことが大切だと痛感させられました。とりわけ気になるのが、陸揚局についてで……
「(前略)海底ケーブルがどこにあるかは、現代においては隠すことが難しい。陸揚局がどこにあるかは、筆者のような部外者にも探すことができる。海底のケーブルのだいたいの場所は、船の航行に使う海図に記されている。ケーブルが複数敷設されているところであれば、そうしたケーブルに直角になるような角度で海底に機械を這わせればケーブルを破壊することができるだろう。」
「海底ケーブルが複数失われたときにどうするかという危機管理計画は必要である。」
……陸揚局も含めた危機管理体制を確立して欲しいと願っています。
『海底の覇権争奪 知られざる海底ケーブルの地政学』…‥海底ケーブルの歴史や、地政学的観点から見た海底ケーブルの重要性を解説してくれる本で、とても参考になりました。みなさんも、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『海底の覇権争奪』