ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
医学&薬学
病の錬金術(ワイズナー)
『病の錬金術 化学物質はなぜ毒になりうるのか (ニュートン新書)』2024/8/23
ジョン ワイズナー (著), 小椋 康光 (監修), 日向 やよい (翻訳)
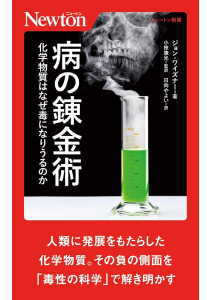
(感想)
中世から現代まで,化学物質が人間に悪影響を及ぼしてきた歴史を「毒性学」の視点で語り、化学物質と病気の因果関係を突き止める手法や、毒性学の社会での活用例などを紹介してくれる本で、主な内容は次の通りです。
まえがき
パート1 毒性学はなぜ必要なのか?
第1章 癌のクラスター:真相がはっきりしない場合もある
第2章 ヒ素や動物が産生する毒素による死:真相がはっきりしている場合もある
第3章 パラケルスス:錬金術と医術
第4章 採鉱と初期の産業医学
第5章 化学物質の時代
第6章 バイオアッセイ・ブーム
パート2 毒性学ではどのような研究をするのか,毒性学研究からわかったことは何か?
第7章 鉛:脳の発達を阻害する重金属
第8章 レイチェル・カーソン:沈黙の春はいまや喧騒の夏に
第9章 癌の研究
第10章 発癌性物質はどのようにしてできるか?
第11章 一部の発癌性物質は遺伝子に直接影響を及ぼす
第12章 刺激によって起こる癌
第13章 喫煙:タールまみれの黒い肺
第14章 何が癌を引き起こすのか?
パート3 毒性学はどのように利用されているか?
第15章 化学物質による病気から労働者を守る
第16章 名称が注目度を高めた化学物質
第17章 化学物質は的確に規制されているか?
第18章 用量が毒をつくる
第19章 除染をめぐる混乱
第20章 法廷闘争
第21章 戦争の毒性学
パート4 毒性学における未完の研究とは何か?
第22章 アヘン製剤と政治
第23章 気候変動の毒性学
第24章 ヒトの病気を予測するための動物モデル
第25章 実験動物を用いた発癌実験は信頼できるか?
第26章 ホルモン模倣物質と内分泌撹乱物質
第27章 毒性試験のためのよりよいツールの開発
第28章 予防は治療に勝る
*
「第1章 癌のクラスター」では、ケンタッキー州で見つかった癌のクラスターではポリ塩化ビニルが原因であるとされた一方で、小児白血病のクラスターでは飲料水中のTCEに疑いがもたれたものの明確にならず、ある化学物質がガンを引き起こすかどうかを解明するのは簡単な仕事ではないことが示されています。
「第3章 パラケルスス:錬金術と医術」では、治療薬と毒物がまったく別物とみなされていた時代に、パラケルススが、環境中の要因によって病気が起こり得ること、化学物質の有害な作用の主な原因がその用量にあると気づいたとして、次のように書いてありました。
「(前略)パラケルススの仕事は薬物療法の始まりを意味する。体内の平衡の調整を通じてではなく、体に対する化学物質の直接の効果を通じて病気を治癒する方法だ。」
「パラケルススが遺したものには、化学物質に対する毒性学および薬理学上の生体反応の研究に関する実験こそが不可欠だという考え方がある。」
*
そして鉱山労働者がヒ素や鉛、シリカなどを原因とする病気にかかってきたこと、石炭や石油を原料とする化学物質製造工場(たとえばアニリン染料など)の労働者が芳香族アミンやベンゼンによって癌や白血病になったことなどで、産業医学や毒性学が必要とされてきたという経緯が詳しく解説されていきます。
必ずしも安全ではなかった薬や食品の問題も明らかになってきて……
「(前略)1962年の医薬品改正法によって、所定の病気に対して効果があるだけでなく安全でもあることを証明済みでなければ、医薬品は市場に出せないことになった。」
また1958年には、食品添加物改正法(発癌性があるとわかった食品添加物の使用禁止)などが行われたそうです。
さらに鉛が脳の発達を阻害することが分かってきたことや、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』の農薬の散布による動物の大量死などを受けて、危険な化学物質の研究が進み、規制する法律がしだいに整備されていきました。
この本は『病の錬金術』というタイトルだったので、正直言って「インチキ薬」の事例紹介の本ではないかと想像していたのですが、意外にも(?)毒性学の歴史や研究方法について詳しく解説してくれる、とても真摯な内容の本なのでした。
そして「第9章 癌の研究」では、「一部の化学物質に染色体の遺伝子暗号を書き換える力がある」ことが分かってきたとして……
「染色体およびDNAの構造の発見が、細胞複製中に体細胞変異が継承される仕組みを細胞レベルで理解するための土台となった。またがん細胞における変異とその継承の本質の理解にもつながった。」
また「第10章 発癌性物質はどのようにしてできるか?」では……
「(前略)癌化を開始させるイニシエーター化学物質は、DNAと反応して変異を発生させることによって、細胞に遺伝子変化を起こさせることが発見された。この遺伝子変化は娘細胞に渡される。さらに、発癌を促進するプロモーター化学物質が遺伝子の調節に変異を引き起こし、それによって、遺伝子の発現、すなわちタンパク質をつくる能力を変異させることが同様に発見された。」
さらに「第12章 刺激によって起こる癌」では……
「(前略)細胞の増殖だけでは癌が起こらないことが現在では明らかになっているものの、炎症細胞や成長因子、活性化基質、DNA損傷促進作用物質などに富む環境での持続的な細胞増殖は、癌発生のリスクを高める。時には、刺激やそれによる炎症反応に対処する体の能力が損傷に圧倒されてしまうことがあるのだ。シリカやアスベストに起因するヒトの病気は主に、これらの作用物質がもたらす刺激によって起こる。」
……など、癌と発癌物質の関係が詳しく説明されていました。
そして「第18章 用量が毒をつくる」では、発癌物質などの有害物質が、必ずしもすぐに癌化を起こすわけではないことも説明されています。
「(前略)体から化学物質を排泄する仕組みのおかげで、ヒトは低レベルの曝露に耐えることができる。何らかの効果をもたらすほどの濃度で体内に存在した場合さえ、その他のホメオスタシスによって相殺することが可能だ。(中略)明らかな効果を起こさせるために超えなければならない閾値用量があるのは、ホメオスタシスのためだ。ホメオスタシスが、化学物質が生体に及ぼす効果に必要な閾値をつくり出している。」
……ホメオスタシスがあることで、私たちの体は守られているんですね。
石油やさまざまな化学物質は、私たちの生活になくてはならないものとなっているので、有害だからといって、すべてなくしてしまうことは現実的ではなく、「どの程度なら許容できるか」のレベルを設定することが大切なようです。
……そうかこんなふうにして、毒性学や動物実験は、私たちの健康にとって、とても大事な役割を果たしてきてくれたんだなーと感謝でいっぱいになりましたが、「第24章 ヒトの病気を予測するための動物モデル」や、「第25章 実験動物を用いた発癌実験は信頼できるか?」では、その動物実験に潜む問題が、次々と明らかにされています。
なんと「2004年に、冒される器官系や疾病タイプによっては疾病遺伝子がヒトとラットやマウスでかなり異なっていることを示す証拠を、ある研究論文が提示した」そうで、ヒトとラットやマウスは、神経機能では類似していますが、免疫系などでは類似性がとても低いそうです。
しかも動物実験の再現性は意外に低く、それはマウスの腸の微生物集団、腸内細菌叢と呼ばれるものとも関係があるのだとか……。
うわー……薬の効果や毒性を決めるのに使われる動物実験が信頼できないとしたら……いったいどうしたらいいんだろうなー、と途方にくれてしまいました……。
最終章の「第28章 予防は治療に勝る」には、「予防のほうが健康とコストの両面ではるかに効果的(障害が最も少ない)」と書いてありました。……うーん、まさしくその通りなのでしょう。
喫煙、過剰なアルコール摂取、薬物乱用、過食、大気汚染、運動不足が、癌をはじめとする致命的な病気の予防可能な原因として確認されているそうなので、とりあえず、それを避け、食事、運動、睡眠に気をつける健康生活を続けていこうと思います。
『病の錬金術 化学物質はなぜ毒になりうるのか』……ここで紹介した以外にも、毒をめぐる法廷闘争や、化学戦に使われた化学物質など、参考になる情報が満載でした。医学や薬学、化学に興味がある方は、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『病の錬金術』