ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
防犯防災&アウトドア
防災
活断層防災を問う(鈴木康弘)
『活断層防災を問う: 阪神・淡路大震災30年』2025/2/17
鈴木康弘 (著)
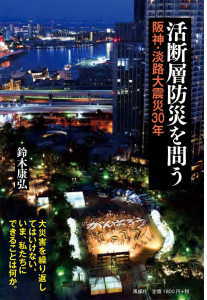
(感想)
阪神・淡路大震災から30年。その後に発生した東日本大震災、熊本、能登の地震を見る限り、社会の脆弱性は一向に減っていない……大災害を繰り返さないために、いま私たちにできることは何かを、活断層防災に詳しい鈴木さんが考察している本です。
「はじめに」には、次のように書いてありました。
「本書は、阪神・淡路大震災以後、ときにリクエストに応じ、あるいは衝動に駆られて、筆者が活断層防災の考えを書き留めた原稿を集めたものである。」
……ということなので、本書には、1995年など、かなり以前に書かれた記事も入っています。
第1章には次のような記述がありました。
「「次にいつ断層が動くか」はわからないが、今後数百年間は比較的安全な活断層か、危険な活断層かを判断することはできる。断層が沖積層(新しい時代の地層)を切っている場所で、深さ3~5m程度の溝を掘って地層の年代と乱れ具合を調べる。最後にいつその活断層が地震を起こしたか、周期はどれくらいかを明らかにする。このトレンチ調査と呼ばれる方法で、地震の切迫具合がわかる。サンアンドレアス断層を抱えるアメリカのカリフォルニア州では、断層通過地点を開発するときには調査することが法律によって義務づけられている。
トレンチ調査はこれまでに、約1500以上ある日本の活断層のうちの約30に対して延べ60回程度行われているのみである。」
……この記事は1995.1.20に中日新聞に掲載されたものなので、調査回数はもっと増えているのかもしれませんが、基本的な内容は変わっていないのでしょう。活断層は、こんな風に調査されているんですね! また大まかな活断層は、空中写真による地形観察でも見つけられるようです。
第3章では過去の地震から学ぶこととして、およそ千年に一度の都市直下活断層地震には、全国一律の耐震性強化によって備えることには限界があるので、ハザードマップ(防災を目的に災害に遭う地域を予測し表示した地図)などで住民が自ら最低限守るべきことを考え、自主的な備えを促す必要があることが書いてありました。また次のことも……
・「防災の基本はイメージトレーニングであり、ハザードマップは、災害が自分の住む町において具体的にどのように起きるかをイメージするための教材である。」
・「1999年台湾地震の際には活断層の真上に位置していた校舎だけが選択的に潰れた。」
・「(前略)学校の校舎が活断層真上に放置されることは児童生徒の安全確保の観点から問題がある。既存校舎を急に移転することは難しいとしても、建て替え等のタイミングで、設置者の自主的判断により問題が解消されることに期待したい。」
*
……学校の校舎は地域住民の避難所に指定されていることも多いので、防災の観点からも活断層真上は避けて欲しいと思います。また病院や福祉施設も、災害時に地域住民の治療や保護の拠点にもなるので、同じような考慮が必要だと思います。
この章では2005年3月に「全国を概観した地震動予測地図(地震調査研究推進本部地震調査委員会)」が公開されていることも紹介されていました。
続く第4章では、活断層や活断層大地震について……
・「活断層とは、最近の地質時代に「ずれ」を繰り返し、今後もそのような活動を起こす可能性が高い断層のことです。これを探すには、まず過去の「ずれ」の痕跡を追うことになります。」
・「活断層の分布は、現時点でも完全にわかっているわけではなく、その情報は改訂され続けています。」
・「一方、陸上の活断層についてはかなり調査が進んでいて、まったく活断層がないと考えられている場所に突如大きな活断層が現れることは、まずないだろうと思います。1970年代から80年代にかけて、多くの地形学者や地質学者が日本列島全域の航空写真を観察して、活断層のずれの痕跡を探し、90年代以降も今日に至るまで詳細な調査が続けられた結果です。例えて言えば、活断層の「名簿」はほぼできあがっています。
しかし、その「身体検査」はまだ十分にできていません。地震の規模を予測するためには、活断層の長さを決めることが重要ですが、断層の終点を明らかにすることは簡単ではなく、また、断片的に見つかる活断層が相互につながり、長い活断層を形成しているかどうかを見極めるのも容易ではありません。」
*
さて、陸上はこのように調査が進んでいますが、「海底活断層」になると、その全体がよく分かっていないようです。例えば能登半島地震の震源となった海底活断層も、地震の震源としては想定されていませんでした。それというのも沿岸海域の調査は技術的に困難で、これまで主流だった調査は音波調査(ケーブルを引きずりながら舟を走らせ、音波を発して海底下の地質の様子を調べる)ですが、こうした調査は、陸地に近い沿岸海域においては漁業権との兼ね合いで容易ではないそうです。
それでも最近は、活断層の調査で、新技術の活用が期待されているようです。
例えば、航空レーザー測量(LiDAR)という「上空から地表に向かってレーザーを照射して地表の形状を測る先端技術」を使うと、自然の森や構造物の形も正確に捉えられるので、これらの保全・保守の他、災害時にもいち早く被災状況を正確に測れるのだとか。
また海域においても陸上と同様に、変動地形(地殻変動がつくった地形)を重視して活断層認定を行う試みが、近年盛んに行われているそうです。
「近年、水深15~20mより浅い沿岸海域については、水中を透過する緑レーザーによって詳細な海底地形を測量することができる技術開発が進み、この手法を導入して全国の沿岸海域の調査をしようという取り組みが民間ベースで行われている(日本財団2020)。その結果に期待がもてるが、現状においてはこうしたデータがすぐに活断層調査に使える見通しは立っていない。」
……今後、新技術の導入で日本周辺の活断層調査が進むことを期待したいと思います。
また、これまでの地震を教訓に、これからどうするべきかに関する次のような提言もありました。
1)沿岸海域の活断層は盲点だった→調査して、陸上と同様に国土地理院の活断層図に示すべき。
2)海岸地形を見直し、海成段丘が標高の高い場所にあるのにその原因が明らかになっていない地域をリストアップし、沿岸に海底活断層がある可能性を見極め、調査の優先順位を検討する必要がある。
3)活断層評価をまとめる地震本部の体制を見直すことも必要。
*
『活断層防災を問う』……活断層がどのようなものかを解説してくれるとともに、活断層と地震の関わり、さらに防災との関わりや提言を語ってくれる本で、とても参考になりました。地震や防災に興味のある方は、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『活断層防災を問う』