ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
地質・地理・気象・地球環境
地球の測り方(青木陽介)
『地球の測り方 宇宙から見る「水の惑星」のすがた』2025/2/28
青木 陽介 (著)
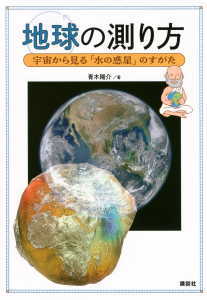
(感想)
地球は本当はどんな形なのか? 宇宙から眺める青い惑星の姿を「測る」ことで、プレートテクトニクスから気候変動まで、その奥深いメカニズムが見えてくる……「測地学」から眺める、新しい地球科学の入門書で、主な内容は次の通りです。
第1章 地球を知るホットな学問 測地学とは何だろうか
第2章 地球は丸いというけれど…… 地球の形
第3章 地球ははたして固体なのか? 地球内部構造の基礎知識
第4章 紀元前から測られてきた地球 伝統的な地上測量技術の原理
第5章 小さな変形も見逃さない 連続観測
第6章 測地学を変えた計測技術 衛星測地の原理と地表変形の観測
第7章 質量の移動を宇宙から測る 重力の計測
第8章 1日の長さは一定なのか 地球回転の計測
第9章 月や太陽も地球を変形させる 潮汐
第10章 地球温暖化は気温のみならず 気候変動による地球の変形
第11章 地殻変動観測が明かした地球の姿 地震による地球の変形
第12章 火山と測地学の奥深い関係 火山活動による地球の変形
第13章 人間も地球の形を変えている 人為的な要因による地球の変形
*
第1章には次のように書いてありました。
「地球の形や大きさや内部構造を計測し、その時間変化を調べるのが測地学です。」
地球を測ることで多くのことが分かってきているようです。例えば……
「北米大陸北部やヨーロッパ大陸北部では現在、最大年10mm以上の速度で隆起しており、このような変形を後氷期変動(post-glacial rebound)といいます。この地域では氷河期の頃に数千mもの厚い氷河で覆われていた地域ですが、氷河期が終了し氷河がなくなったにもかかわらず、氷河による荷重から解放されたことによる隆起が現在でも継続しています。」
……大地はプレートテクトニクスだけでなく、潮汐力(太陽や月の引力)や降雨や降雪、地震や火山噴火、地球温暖化などのさまざまな影響で動いているようです。
「地下構造を知るのに最も幅広く用いられているのは地震波を使った方法です。地震波の周期は1秒からせいぜい数百秒ですから、地震波を用いることによって分かる地下構造は比較的短い時間スケールの現象に対応するものといってよいでしょう。(中略)
地球を構成する物質は(外核を除いて)日常生活の時間スケールでは固体的にふるまうが、数千年を超える時間スケールでは流動的に振る舞うということです。現在観測されているこのような地表変形は地下の粘弾性構造の情報を含んでいますから、地球内部の粘弾性構造、すなわち長い時間スケールでの応答を知ることができるというわけです。」
*
第2章や第3章では、地球が赤道方向に張り出した回転楕円体であることや、地震波速度構造から地球が浅いほうから地殻・上部マントル・下部マントル・外核・内核の層構造をしていることなどが、「地球を測る」ことで明らかになってきたことが説明されていました。
そして第4章では、伝統的な地上測量技術の原理について知ることが出来ます。古くから行われている「水準測量(2点の観測点(水準点)の相対的な高さの差を計測する)」、「三角測量(既知の2点を結ぶ直線と測定したい点のなす角を計測することによって測定したい点の位置を決定する)」の他、最新の「光波測量(反射されて戻って来たレーザーの時間を計測することで2点間の距離を測定)」などの解説がありました。
第6章は衛星測地の原理と地表変形の観測がテーマで、例えばVLBIについては……
「超長基線電波干渉法(VLBI)は、地球から数億光年以上離れた準星や活動銀河などの天体から発せられる強い電波を観測し、その電波源の大きさを求めるために1960年代に開発されました。(中略)1970年代から80年代にかけての信号処理技術や地上局の時計の精度の向上により、VLBI地上局の位置を数mmの精度で決めることができるようになり、測地学への応用が可能になりました。(中略)共通の電波源を見つけることができれば、VLBIは長距離の観測点間の距離を計測することができます。」
……この他、衛星レーザー測距(SLR)についても解説がありました。
人工衛星は地球からの重力を受けて地球の周囲を回っていますから、人工衛星の位置を知ることによって地球内部の質量分布を知ることができるそうです。
なんと宇宙から海底を測ることも出来るようです。ただし海水は電波を通さないので、実際の計測には音波を利用するようですが……。またGNSS衛星から射出される信号は海水面で反射してしまうので、海の計測で利用する場合は、「船」を利用するのだとか。例えば「GNSS-音波測距結合方式」では……
「(前略)船から発せられる音波により船と海底のトランスポンダーの相対的な位置を計測し、船に搭載されたGNSSによる位置計測と合わせて、海底のトランスポンダーの(重心)位置を決めます。海水の音速は海水温によって変化するため、船と海底のトランスポンダーとの距離を正確に計測するには海水温の分布を正確に知らなくてはならず、この温度分布の不確定性がこの計測の主な誤差源になります。この計測の精度は陸上でのGNSS観測には劣りますが、それでも水平位置で数十mm、鉛直位置で100mm程度の精度で観測点の位置を求めることができます。」
……なるほど。このようにすれば海底を測るときに、衛星による位置情報を利用できるんですね……。
また第7章では、重力の計測に使われているGRACEという衛星について……
・「(前略)密度の高い物質の上を衛星が飛ぶと衛星がその物質に引き寄せられるために二つの衛星の距離が短くなり、逆に密度の低い物質の上を衛星が飛ぶと二つの衛星の距離が長くなります。そのため2衛星の距離変化を計測することで地球の重力場を知ることができるのです。」
・「GRACEは(中略)打ち上げ時から気候変動に関連した質量移動を観測することを目的の一つとしてきたのですが、水の移動の年周変化だけでなく異常気象による洪水や干ばつ、農業用水や工業用水の汲み上げにともなう地下水の減少なども検出しており、地球の環境変化を監視する強力な手段として活躍しています。
GRACEは、季節変動による重力変化だけでなく、重力の経年変化も観測しました。」
*
第8章では、地球の歳差運動(周期は約25,700年)が、地球の気候を大きく変えている(氷河期と間氷期)ことが次のように書いてありました。
「歳差運動により、日射量の地球上での空間分布は周期的に変わります。そのほかに、現在は円軌道に近い楕円軌道である公転軌道の離心率の変化や、現在は約23.4度である回転軸の傾きの時間変化(長期的には約21.5度から約24.5度まで変化します)が日射量の空間分布を変えます。これにより、地球の気候は数万年以上の時間スケールで氷河期から間氷期へ、もしくは間氷期から氷河期へと周期的に変化します。」
……歳差運動などの周期や回転軸の傾きなどを知るのにも、測地学が役に立っているのです。
そして第9章では、潮汐力が、「潮位を上下させるだけでなく、地球を変形させ、地球の自転変化、すなわち1日の長さを変える原動力にもなる」ことについて解説されていました。
また驚かされたのが、積雪が日本列島を隆起・沈降させているという話。
「(前略)東北日本では積雪の多い場所で冬に沈降し夏に隆起するという季節変動が見られ、また日本海岸と太平洋岸のGNSS観測点の距離は冬に短縮し夏に伸張するという季節変動が見られます。この観測は冬から初春にかけての積雪とその後の融解によってよく説明できます。」
……うーん、測定技術の精度の向上で、こんなことまで分かってきているんですね……。
さらに第13章では、人為的な要因による地球の変形の中で、地下水についても……
・「地下水のくみ上げは、そのスポンジに吸い込まれている水を抜くようなものです。水を抜かれたスポンジは体積が減少します。同様に地下水が汲み上げられると地表は沈降します。」
・「たとえばメキシコシティでは、過去100年以上にわたって最大で年間500mm以上の速度で地盤沈下が継続しています。」
……それだけでなく、鉱山活動なども……
・「鉱山での活動や地下への注水により人工的に引き起こされる地震については早くから認識されていました。」
・「21世紀に入り、先に述べたようにシェールガスが多くの誘発地震を引き起こしました。特に北米大陸では顕著で、地震活動が通常は低調な南部などで多くの地震が発生しました。実際、2014年から2018年にかけて、オクラホマ州では太平洋プレートと北米プレートの境界が位置するカリフォルニア州よりも多くの地震が発生していました。オクラホマ州などで発生する誘発地震には被害を及ぼしうるマグニチュード5を超えるものも数多く含まれていますから、科学的な注目だけでなく社会的な注目も集めることになりました。その後北米大陸では水圧破砕によるシェールガス採掘が減少し、それと同時に地震活動も低下しました。」
……シェールガスが人工的な地震を引き起こしていたんですね……驚きです。
この他にも、第11章では「地震」が、第12章では「火山噴火」が地球を変形させてきたことに関する説明がありました。
『地球の測り方 宇宙から見る「水の惑星」のすがた』……「測地学」から地球の姿を俯瞰する地球科学の本で、とても勉強になりました。『地球の測り方』というタイトルなので、計測の仕方に重点があるのだと予想していましたが、どちらかというと地球科学に重点があったようで、「計測技術」については概説レベルでした。でも測地学で分かって来た「地球科学」について詳しく知ることができて、とても有意義だったと思います。地球科学に興味のある方は、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『地球の測り方』