ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
地質・地理・気象・地球環境
大地と人の物語(日本地質学会)
『大地と人の物語: 地質学でよみとく日本の伝承』2025/6/11
日本地質学会 (著)
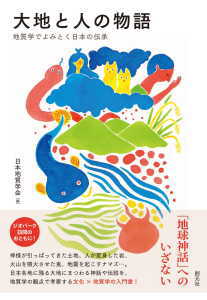
(感想)
神様が引っぱってきた土地、人が変身した岩、火山を噴火させた鬼、地震を起こすナマズ……日本各地に残る大地にまつわる神話や伝説を、地質学の観点で考察する文化×地質学の入門書で、主な内容は次の通りです。
刊行によせて
〈第1部 総論〉
第1章 大地から生まれる物語――地球神話への誘い(野村律夫)
第2章 地球を読み解くストーリー――ジオパークの歴史と活動(山﨑由貴子)
コラム1 ジオパークことはじめ(矢島道子)
〈第2部 各論〉
第1章 アイヌ民族の伝承とジオパーク――神々【カムイ】と人間【アイヌ】の交わる世界(大野徹人)
第2章 磐梯山の岩なだれが造りだした地形・奇岩――「宝の山」に伝わる伝説と昔話(竹谷陽二郞)
第3章 関東地方の大地震と鯰伝説――地震を起こした鯰の正体は?(天野一男)
コラム2 災害教訓を伝える自然災害伝承碑(大塚孝泰)
第4章 大男が射抜いた穴 星穴伝説――奇岩の山・妙義山にまつわる伝説(関谷友彦)
第5章 浅間山と鬼伝説――火山の噴火は鬼のしわざ?(古川広樹)
コラム3“さざれ石”と“たもと石”(先山徹)
第6章 糸魚川ジオパークの景観――奴奈川姫と大国主命の伝説からたどる(竹之内耕)
第7章 熊野の神話と火成岩――古事記・日本書紀からみる(此松昌彦)
第8章 豊岡盆地の成り立ちとアマノヒボコ伝説――日本海形成と玄武洞(松原典孝)
コラム4 身近にもある? 化け物と化石の接点(荻野慎諧)
第9章 わら蛇の祭と伝説――大蛇が語りかける(先山徹)
第10章 「こし」のヤマタノオロチ 火山説の再考――洪水か、火山噴火か(荻野慎諧)
第11章 くにびき神話と島根半島――神が土地を引っ張ってきた!(野村律夫)
第12章 阿蘇カルデラの歴史と神話――地形・地質の特徴からひもとく地震・地球の動き(永田紘樹)
コラム5 自然災害と天然記念物(柴田伊廣)
おわりに
用語集

「刊行によせて」には、次のように書いてありました。
「(前略)地すべりだとか噴火だとかといったイベント的な地質現象もまた、神話のモチーフになったのだろう。自然災害の種類も頻度も多いこの国において、神話や伝承に耳を傾け、防災に思いをめぐらすことは、人々の古来の知恵というものである。」
また、海外でも、神話や伝説と地質との関係が注目されているようで……
・「(前略)アメリカ・ヨーロッパでは、1960年ごろから「Geomythology」という言葉が提案され、神話や伝説と地質のあいだに密接なかかわりがあるのではないかと考える研究者が現れ始めた。」
・「(前略)神話は伝説の中には、実際の自然現象(地震、津波、火山噴火、隕石衝突、地形の変化など)を表現したのではないかと考えられるものが数多く存在する。」
……実際にハワイに伝わる「火山の女神ペレの物語」では……
「姉とのもめ事によって、火山の女神が島々を南東方向にどんどん移動していき、最後に現在も活発に活動しているキラウェア火山に宿ったというこの神話は、実はハワイ諸島の形成メカニズムとおどろくほど似ている。」
……古代の人は、今よりも自然観察眼が優れていたでしょうから、それが伝説に反映されているのかもしれません。
そして〈第2部 各論〉の「第1章 アイヌ民族の伝承とジオパーク」では、アイヌの古老の言い伝えの「観音山山頂で盗賊を埋めた場所は、そこだけ冬も雪が積もらず湯気がでている」に対して、現実にそれらしい場所に「温風穴」があったそうです。……山腹から「冷気」が噴き出す「風穴」は知っていましたが、北海道には「暖気」が噴き出す「温風穴」があるんですね! これは温泉由来のものではなく、「洞窟の内外で温度差や気圧差が生じることにより、風が通り抜ける現象」だそうです。
また「コラム2 災害教訓を伝える自然災害伝承碑」には、長野県の南木曽町の「蛇ぬけの碑」の写真があり、これには、「白い雨が降るとぬける」「長雨後谷の水が急に止まったらぬける」「蛇ぬけの前はきな臭い匂いがする」など、1953年の土石流災害で得られた6つの教訓が刻まれているそうです。……教訓がすごく具体的で、後世の人の無事を心から祈って作ってくれたんですね……。
なおこのような石碑の伝承をより活かそうと、国土地理院が次の活動をしているそうです。
「(前略)国土地理院では、過去の災害教訓を伝える石碑やモニュメントを「自然災害伝承碑」として地図上に表示する取り組みを2019(令和元)年6月から開始し、全国各地に存在する碑の掲載を進め、2023(令和5)年9月には掲載数が2000基を超えた。」
……祖先が作ってくれた石碑の教えを、活かしていきたいですね。
また古い絵図も、災害の詳細を教えてくれることがあるようで……
「1803年以降に書かれたと考えられる作者不詳の絵図(「浅間山夜分大焼之図」には、天明の大噴火で火口から巨大な火柱を上げて噴火する浅間山の様子が描かれている。(中略)
絵図には、高く吹き上がる溶岩の柱、黒煙、降下する溶岩のしぶきが描かれている。その周りには火山雷と思われる稲光も確認できる。火山雷は火山噴火の際、その噴煙にともなって発生する雷で、細粒となった火山噴出物が上昇途中で摩擦によって電気を帯びるために発生する。」
……カラー写真で見ることができるこの絵図には、確かに「火山雷」まで描かれていて、この噴火を実際に「見て」描いたんだなーと実感させられました。
「第6章 糸魚川ジオパークの景観」では、有名な糸魚川のヒスイについて……
「ヒスイは、日本列島がまだ大陸の一部であった頃、プレートが沈み込む地下深部で形成され、さらに深部をつくるマントル由来の蛇紋岩によって包み込まれ、地表近くに上昇してきたと考えられている(茅原1988)。小滝川が、隆起する蛇紋岩からなる大地を削って洗い出したヒスイ岩塊は、重たく硬いため、普段の清流では下流へ運搬されない。そのため、河床に溜り徐々にヒスイが集積していき、ヒスイ狭ができあがった。」
……ところが古墳時代を最後にヒスイの勾玉が生産されなくなり、糸魚川でヒスイが産することも、明治時代ごろまでには、すっかり忘れ去られてしまったそうです。その後、万葉集の和歌をヒントに日本のヒスイ原産地探しが始まって、1939年に、小滝川からヒスイが出たことが科学的に確認されたそうです。再発見されたのは、意外に最近だったんですね……。
この他にも、一般的に「洪水」と関係が深いと考えられている「ヤマタノオロチ」は、火山噴火と関係があるかもしれないとか、出雲地方の「くにびき神話」は、自然科学的に見て島根半島の地質的な特徴をよく捉えているとか、興味深い記事をたくさん読むことができました。
『大地と人の物語: 地質学でよみとく日本の伝承』……一見、荒唐無稽なファンタジーに思えるような神話や伝承が、成立した当時の人々なりの見方・考え方に基づいて、物事の由緒や現象を説明し、現代に伝えてきたものだということを教えてくれる本で、とても面白かったです。興味がある方は、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『大地と人の物語』