ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
地質・地理・気象・地球環境
日本列島の地震・津波・噴火の歴史(山賀進)
『増補改訂版 科学の目で見る 日本列島の地震・津波・噴火の歴史』2025/6/18
山賀 進 (著)

(感想)
4枚ものプレートがひしめき合い、そのうち3枚のプレートが一点で接している場所が2つもあるという日本列島で起こってきた地震・津波・噴火の歴史(5世紀以降)を、科学的な目で見つめなおしている本で、いつどこでどんなことがあったのかを時代を追って俯瞰して紹介してくれます(なお本書は2016年7月に発売した同名書籍の増補改訂版です)。
「第0章は、地震と火山が多い日本の基礎知識」。第1章から始まる日本列島の地震・津波・噴火の歴史紹介の前に、日本の地震や火山全般に関する基礎知識の解説があって、とても勉強になりました。
例えば「日本の火山の特徴」が分かりやすかったので、ちょっと長いですが以下に紹介します。
「日本は海のプレートが潜り込む場所です。冷たい海のプレートの潜り込む場所で、なぜマグマが発生するのか。これはかつては大問題でした。しかし現在では、中央海嶺(海洋底の拡大をもたらす大規模な海底山脈)で生成された海のプレートが、海溝にたどり着くまでの間に(最大で2億年くらいかかる)、プレートをつくっている岩石(鉱物)が海(水)を含むようになり、その水がプレートの潜り込みによって岩石(鉱物)から絞り出されると、岩石が溶け始める温度が劇的に下がるためだということがわかってきました。水は鉱物の分子の結びつきを断ち切り、分子を小さくします(中略)。分子は小さいほど溶けやすいという性質があります。こうして水は、岩石を構成している鉱物の溶け始める温度を劇的に下げる役割を果たすのです。
そのため冷たいプレートが潜り込む海溝でも、マントル成分のうち溶けやすい成分だけが溶けて(部分溶融して)、かんらん岩質のマントルから、かんらん岩質ではない玄武岩質マグマが発生します。その深さは百数十mから200km程度だと考えられています。液体のマグマは固体のマントルの中を浮力で上昇します。(中略)
マグマが上昇してモホロビッチ不連続面(モホ不連続面、地殻とマントルの境界)までに達すると、そこから上の岩石の密度は急に小さくなるために浮力を失い、マグマはいったんここで停滞してマグマだまりをつくります。」
……その後、このマグマだまりの中で、周囲の岩石を融かしたり、鉱物を析出・沈殿させたりして、玄武岩質マグマから安山岩質(~デイサイト質マグマ)へと組成が変わっていって、さらに浮力により上昇。まわりの岩石の密度が小さくなったところで、またマグマだまりをつくるのだとか……地震だけでなく火山活動も、プレート活動で起こっていたんですね……。
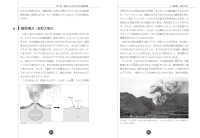
そして第1章から、いよいよ日本列島の地震・津波・噴火の歴史が始まります。
日本の記録の中で一番古いものは、『日本書紀』に記された西暦416年の遠飛鳥宮付近(明日香村)で起きた地震だそうですが、残念ながら被害などの記録はないそうです。
この後は、富士山の噴火(貞観の噴火)や、東海・南海・西海でほぼ同時に2回の大地震(慶長の南海-房総地震)、関東から九州までの広域で大地震(宝永の南海・東海地震)など、遠い過去の記録から、近代の記録、さらに現在の記録まで、日本に起きた大きな地震・津波・噴火が紹介されていき、その間に、南海トラフで起こる大地震の“癖”とか、富士山の宝永大噴火の噴出物の色の変化(白から黒へ)とか、地震や火山噴火についての、さまざまな科学的な説明を知ることが出来ます。
ちょっと驚いたのが、「浅間山の天明の噴火」。浅間山の北側で鬼押し出し溶岩が流出、それが柳井沼に達して水蒸気爆発を起こし、その爆発の衝撃で山崩れが発生(鎌原火砕流)。土砂総量はなんと東京ドーム約80杯分だったそうです。……高温の溶岩が沼や海などの水に出会ってしまうと、「水蒸気爆発」を起こして被害を大きくしてしまうんですね……。
この後も、日本列島の各地で巨大な地震(及び津波)や火山噴火がどんどん起こっていて、まさに日本は地震・火山大国なんだなーとあらためて痛感(戦慄)させられました。世界地図で見ると、小さい国に見えますが、実は「日本は世界で起こっている地震の1割以上が起こっていて」、「世界の活火山の約1割がこの狭い日本にある」そうです(涙)。
また、あの2011年の東北地方太平洋沖地震(M9.0 Mw9.1)は、地震計での地震観測が始まって以来、1960年のチリ地震(Mw9.5)と1964年のアラスカ地震(M9.2)に次ぐ、世界第3位の巨大地震だったそうです。ちなみに第1位の1960年のチリ地震では、発生した津波が、太平洋を横断して、日本の太平洋海岸のほぼ全域を襲い、全国で142人の犠牲者を出したほどで、なんとその津波は、チリからジェット機並みの時速で襲ってきたそうです(涙)。凄いですね……。
『増補改訂版 科学の目で見る 日本列島の地震・津波・噴火の歴史』……日本がいかに「災害大国」なのかを痛感させてくれる本で、とても勉強になりました(ただし本書には、台風などの気象災害は含まれていないので、実際にはさらに多くの災害に見舞われているのですが……)。
みなさんも、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『日本列島の地震・津波・噴火の歴史』