ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
地質・地理・気象・地球環境
河川ダイナミクスの生態学(森誠一)
『河川ダイナミクスの生態学: 動く川が育む生物多様性の保全』2025/6/19
森 誠一 (編集)
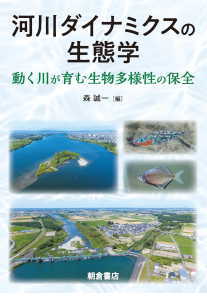
(感想)
今後の河川環境目標の根拠と指針を、木曾三川流域における生物群集を対象とした河川生態系の管理手法に関する研究成果を通して呈示している本で、主な内容は次の通りです。
第1章 河川の人為下における自然史
第2章 氾濫原環境と生物:変動の水環境
第3章 湧水環境と生物:動的安定の水環境
第4章 ざわめく自然の再生
*
冒頭の「動く川に宿る“ざわめく自然”」には、次のように書いてありました。
・「河川は、源流水源から河口海域までの縦断方向、氾濫原を含む流水域から支流・耕作水路までの横断方向、さらに地下水域の垂直方向への連続的な水および砂の物理的な移動現象の総体である。いいかえれば、河川は降水や地下水・伏流水をしばしば貯めつつ高所から低所に修水し流れる流水系であると同時に、浸食と堆積をくり返して土砂を搬送する流砂系の地形でもある。(中略)つまり、流砂系があることが河川の主要な物理特性ともいえ、当然ながら河川は、それゆえに多用な生物の生息場として成立する。」
・「(前略)河川形態として恒常的に瀬と淵は存在するが、それを構成する河床礫の粒度組成は常に変動し、さらに今そこにある瀬・淵は位置を移動してもよく、存在さえして多様な環境を生成すれば、動的平衡として「動く川」となる。
しかしながら「動く川」という河川本来の自動性が低下している現状、河川環境の管理は「動かせる川」として、たとえば循環的氾濫原再生が求められ、その範囲、掘削深、周期などの精度向上が求められる。」
*
……川というと「水」に注目することが多かったのですが、川は「水」だけでなく「土」も運ぶこと、そして洪水や氾濫は災害をもたらすだけでなく、豊かな自然も育むものであることに気づかされました。
「第1章 河川の人為化における自然史」でも、河川に生息する生物に対して土砂動態が果たす機能として次の3つがあげられています。
1)生物間相互作用の調整
2)生物や物質の移動
3)地形を改変することによる生息域の多様性の形成維持
*
そして流域治水の方向性としては……
「2023年度から開始された内閣府のSIP戦略的イノベーション創造プログラム第3期スマート防災ネットワークの構築(2023~2027)「サブ課題D:流域内の貯留機能を最大限活用した被害軽減の実現」において、流域治水の実践的な取り組みの一環として、国土交通省をはじめとした関係省庁および流域関係者が連携し、既存インフラを活用して流域全体としての治水効果を最大化することを目的とする研究開発が開始されている。」
……だそうです。
続く「第2章 氾濫原環境と生物:変動の水環境」では、木曽川の氾濫原環境やそこに生息している生物(二枚貝とイタセンパラなど)の状況について、「第3章 湧水環境と生物」では、扇状地帯の湧水生態の特徴などについての解説がありました。
そして最後の「第4章 ざわめく自然の再生」では、今後の治水と環境保全の参考として、次のような「循環的氾濫原再生」が紹介されていました。
「二極化、樹林化が進行し、生息場の更新やシフティング・モザイクが期待できない河道内氾濫原において、イタセンパラや二枚貝を含む生物多様性を保全するための戦略として「循環的氾濫原再生(cyclic floodplain rejuvenation)」が有効だと考えられる。これはもともと、オランダのワール川で提案された、治水と環境保全を両立させた考え方である。ワール川では、多様な湿地性植物の保全を目的とし、氾濫原が二極化・樹林化してきたら一定面積を伐木・掘削して湿地に戻す行為を繰り返すことが提案された。これは、氾濫原がふたたび二極化・樹林化することは避けられないため、それを前提として循環的に管理しようという考え方である。それと同時に、二極化・樹林化にともなって低下する治水安全度を伐木・掘削によって回復させ、川の氾濫防止にもつなげることを目的とした。」
……かつて1~2年毎に全域が冠水していた日本の原生的氾濫原は、戦国時代以降の河川改修と農地開発、さらに明治以降の土木技術の進歩で、全国的に失われていきました。それは人間の生活や経済活動にとっては良いことのような気がしますが、その一方で、自然環境だけでなく生態系の破壊などももたらしてしまいました。本書でも指摘しているとおり、今後は、「治水」のみならず、「利水」や「環境」(流域利水や流域生態系マネジメント)の視点が重要になるのだと思います。
この章では、コラム「湧水域復活とトゲウオ保全の話」で、梅津市の湧水自然環境再生事業のなかで、トゲウオ科ハリヨの営巣地として好適な環境条件になるよう造成池の砂泥や水深や流速を整備し、良い結果が得られたという事例の紹介もありました。
『河川ダイナミクスの生態学: 動く川が育む生物多様性の保全』……「山の国」であると同時に「川の国」でもある日本の今後の河川事業のあり方を考える上で、とても参考になる本でした。みなさんも、ぜひ読んでみてください。(ただ……単行本サイズなのに、文字の大きさが文庫本並みなので、読むのがちょっと大変かもしれません。価格もちょっと高めなので、購入予定の方は、ぜひ書店などで実物を確認してみてください)。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『河川ダイナミクスの生態学』