ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
科学
自然史標本のつくり方(国立科学博物館)
『自然史標本のつくり方』2025/6/4
国立科学博物館 (監修)
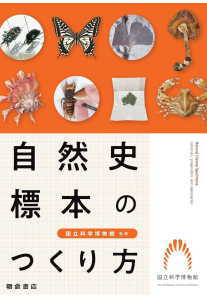
(感想)
国立科学博物館等の研究員さんたちの経験に基づいた動物・植物・岩石などの自然史標本の作製方法の実践的なマニュアルで、主な内容は次の通りです。
イントロダクション:自然史標本をつくろう・集めよう・使おう
第1章 植物学分野の標本
1.1 維管束植物 1.2 コケ植物
1.3 大型藻類 1.4 微細藻類
1.5 地衣類 1.6 菌類
1.7 変形菌類
第2章 動物学分野の標本
2.1 チョウ・ガ類 2.2 甲虫類
2.3 トンボ類 2.4 クモ類・多足類
2.5 ハチ類 2.6 甲殻類
2.7 貝類 2.8 棘皮動物
2.9 寄生蠕虫類 2.10 両生類・爬虫類
2.11 魚類 2.12 鳥類
コラム 哺乳類標本
第3章 地学分野の標本
3.1 植物化石 3.2 無脊椎動物化石
3.3 微化石 コラム 脊椎動物化石
3.4 岩石 3.5 鉱物
コラム 隕石!?
第4章 その他の様式の標本
4.1 樹脂封入標本 4.2 透明標本
*
「まえがき」には次のように書いてありました。
「本書では、自然史標本(動植物や化石、岩石、鉱物など)の作製方法について、ビジュアルに解説します。一般家庭や学校でも実際に作製可能な標本のつくり方に焦点をおき、対象ごとに、採集の準備に必要な事項や理解するべき法令、採集のコツ、標本作成のプロセス、ラベルの書き方、保管・管理方法などをオールカラーの写真・図表とともにわかりやすく概説します。」
……まさにこの通りの内容で、自然史標本の作り方の総合的な教科書です☆
「イントロダクション:自然史標本をつくろう・集めよう・使おう」では、標本作りの目的として……
「(前略)標本の多くは生物の形態のサンプルである。そして、標本が存在することによって、データに疑問が生じたときに再検証が可能になる。」
……などの他、よく使う試薬(ホルムアルデヒドやエタノール)や、データベースを作ることなど、自然史標本をつくるための基礎知識が解説されていました。
そして「第1章 植物学分野の標本」からは、いよいよ種類別の詳しい標本作製方法の解説が始まります。
「1.1 維管束植物」の場合は、「植物を新聞紙に挟んで、形を整えプレスする」などの押し花作りのような方法を教えてもらえる一方で、「1.2 コケ植物」の場合は、「乾燥させたコケをそのままパケットに挿入して折りたたむ」というような、実践的な方法が解説されていました。
そして採集方法についても、採集道具や場所、時期などについて解説があり、例えば「1.3 大型藻類 」では、適切な時期として……
「干潮時の時間帯は直射日光を受けやすく、夏季に多くの海藻が高熱に耐えられずに消失するため、春季の大潮が採集に適している(冬季は、再干潮が深夜に起こるため推奨できない)。」
……というような親切な解説もありました。
「第2章 動物学分野の標本」では、昆虫の標本の作り方などの解説があります(虫や魚、鳥類などのちょっとグロい写真もあるので、虫や生物が嫌いな方には、ちょっと気持ち悪いかもしれませんが……)。
まず「2.1 チョウ・ガ類」の標本では、「展翅」について、次のような驚くほど細かい解説がありました。
「軟化処理した場合、そのままでは固くて翅を整形できないため、翅の基部の翅脈に接着剤(木工用ボンド等)をつけた針を何度も軽く刺し、翅脈を翅が自由に動かせる程度になるまで壊す。もしくは、針で壊した後に、接着剤をその上から塗る。」
……とても実践的な解説ですね! また次のようなことも……
「ラベルの高さをそろえるために、平均台と呼ばれる器具を使う。」
……これも多数の標本をつくってきた方ならではの「道具」だと感心させられました。
さらに「2.3 トンボ類」では、腹部がバラバラになってしまうと標本としての取扱いが難しくなるので、次のような処理をすると良いそうです。
「胸部の頭側から尻側に向かって一気に、トンボ亜目や大型のイトトンボ亜目ならシャープペンシルの芯を思い切って刺す。腹部の先端まで届いたら、飛び出ているあまりの芯は折ってしまえばいい。」
ちなみに標本対象の生物を殺す場合、「冷凍」するのが良い場合も多いようでした。なるほど……冷凍なら薬品を使うこともなく、安全に処理できますね……。
また標本化の前に「写真撮影」をしておいた方が良い場合もあるようです。例えば、甲殻類の多くは、固定液に漬けると生時の色彩が失われるそうです。
「第3章 地学分野の標本」では、「標本への番号記入」のやり方も書いてあり、例えば、化石の標本への番号記入では……
「標本には、化石の価値をそこなわない部分に標本番号等を書いておく。たとえば、白い修正液を塗って、その上に黒インキで番号を書き、さらにその上にマニキュアを塗っておくとよい。」
……なるほど。
そして最終章の「第4章 その他の様式の標本」では、「展示のための標本」の2つの方法が紹介されていました。
「4.1 樹脂封入標本」では……
「生物標本は研究のために作製されるもので、解剖・顕微鏡観察や化学分析などに供されることを予定して保管されるが、それらを目的とせず、初めから長期的な展示を目的として作製される場合には、透明な樹脂による封入処理が施されることがある。」
……これは常設展示や、ミュージアムグッズなどに多用されているようです。
また「4.2 透明標本」では……
「透明骨格標本とはその名称が示すように、筋肉部分を透明な状態にして骨格を染色することで、形態をほぼ保ったまま骨格を中心とした体の内部も観察可能となる標本である。魚類や両生類など一般的には液浸標本として保管する水棲の脊椎動物で作製されることが多い。
また透明骨格標本は硬骨部分が紫色、軟骨部分が青色に染まり見た目が大変美しい状態になるため、イベントなどで使用すると好評となる。そのため装飾物や展示を目的として作製されるイメージが強い。」
……これはミネラルマルシェなどで見たことがありますが、本当に美しい標本でした。
『自然史標本のつくり方』……自然史標本の作製方法に関する、本当に実践的なマニュアルで、とても勉強になりました。大学の生物部などはもちろん、中・高校の生物クラブなどでもとても便利に使えると思います(3700円+税と、ちょっと高価な本ですが……)。生物好き、博物館好きの方は、ぜひ一度読んで(眺めて)みてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『自然史標本のつくり方』