ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
科学
宇宙がわかる 新・周期表ガイド(シャロナー)
『宇宙がわかる 新・周期表ガイド』2025/6/24
ジャック・シャロナー (著), 桜井 弘 (監修)
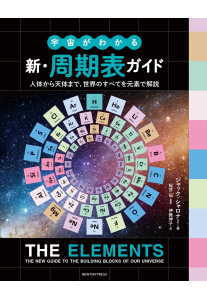
(感想)
ビッグバンと超新星爆発でつくられた元素とその化合物は、太陽系、地球、空気、水、そして生命となるタンパク質をつくり上げた……この宇宙を構成する118の元素について、発見された経緯から名前の由来、用途まで解説してくれる「新しい周期表のガイド」で、主な内容は次の通りです。
はじめに
元素の歴史
水素
アルカリ金属(1族)
アルカリ土類金属(2族)
中間に位置する元素:d ブロックと遷移金属
遷移金属(3族)
遷移金属(4族)
遷移金属(5族)
遷移金属(6族)
遷移金属(7族)
遷移金属(8族)
遷移金属(9族)
遷移金属(10族)
遷移金属(11族)
遷移金属(12族)
中間に位置する元素:f ブロックーランタノイドとアクチノイド
ランタノイド
アクチノイド
ホウ素族(13族)
炭素族(14族)
窒素族(15族)
酸素族(16族)
ハロゲン(17族)
貴ガス(18族)
超ウラン元素
「はじめに」によると、世界の複雑な美しさや世界のあらゆる事象は、陽子、中性子、電子というわずか3種類の粒子の相互作用で説明されるそうです。
そして周期表の先頭は「水素」で……
・「あらゆる元素の中で最も存在度が高いのは水素です。宇宙に存在する通常の物質(宇宙の質量の大部分は「暗黒物質」であり、その性質は今もって謎です)の75%以上は水素で、宇宙に存在する原子の約90%も水素です。地球上に存在する水素は大半が水分子に含まれていますが、生命の営みに関わる重要な成分でもあります。水素は化石燃料に変わる重要なエネルギー源として期待されています。」
・「水素は水分子のほかに、生物の主要な成分であるタンパク質、炭水化物、脂質などの有機分子にも含まれています。(中略)水素結合と呼ばれる特別な結合によって、分子の構造が維持され安定するからです。DNA(デオキシリボ核酸)の二重らせんも水素結合によって保たれています。水素結合は、二重らせんの二本鎖を一つにまとめあげるくらい強く、その一方で成長や生殖の際の細胞分裂では、DNAを複製するために二本鎖がほどけるくらいには弱いです。」
……ここで紹介したのは、「水素」の項目のほんの一部。主要な元素については、それぞれかなり詳しい解説があって、とても勉強になります。
ちょっと驚いたのが、遷移金属(11族)の「銅」。古代から利用されてきた銅は、「血液中で酸素分子を運ぶ色素物質であるヘモグロビンをつくるのには鉄のほかに銅も必須」なようで、私たちの体内でも使われているそうです。そしてタコなどの血が青いのは……
「タコをはじめ軟体動物が酸素分子を運ぶために利用するのは、鉄を含む赤色のタンパク質ではなく、銅を含む青色のタンパク質ヘモシアニンです。そのため血液の色は青です」。
……そうだったんだ! 私たちの血が赤いのは、主に鉄が利用されているからで、タコは銅を使っているから青いんですね……知りませんでした……。
そして炭素族(14族)で「炭素」の凄さも知りました。
・「(前略)混成軌道は電子を原子核のまわりに均等に共有し、ほかの原子との結合について興味深い可能性を与えます。炭素は混成軌道をつくることができるおかげで、きわめて多才な元素となっています。炭素を含まない化合物をすべて合わせても、炭素を含む化合物のほうが多く、炭素は地球上に暮らすあらゆる生物の基盤を支えているといえます。」
・「(前略)炭素が多才といわれるのは、単結合、二重結合、三重結合、環状結合をつくることができ、さらに水素、酸素、窒素に代表されるほかの元素とも結合しやすいからです。」
・「炭素化合物は光合成や呼吸にはじまり、栄養、細胞や組織の修復、さらに成長や生殖まで、生命現象のあらゆる過程に深く関わっています。」
・「炭素は、地球をつくりあげている生物圏(全生物)から大気圏、岩石圏(地殻)、水圏(川、湖、海)まで、ありとあらゆる圏に存在しています。各圏同士で炭素を絶えず交換しながら循環させることを炭素循環(炭素サイクル)といいます。炭素循環に関わる主な化合物は、光合成によって大気から吸収され、呼吸によって大気に戻される二酸化炭素です。」
*
また窒素族(15族)の窒素についても……
「窒素の単体は、常温では無色無臭の気体です。窒素分子は2個の窒素原子からなります。各原子には半分満たされたp軌道が三つあり、これが重なって、きわめて安定した三重結合をつくります。そのため窒素ガスの反応性は非常に低く、不活性を失します。(中略)窒素は地球の大気中には群を抜いて大量に存在します。ところが、地殻中の存在度は上から31番目です。この違いは、窒素が不活性であることに起因します。反応性が高ければ、地殻中でほかの元素と結びついて鉱物をつくっていたはずです。」
……なるほど!
この他にも、単体のときと、化合物になったときに大きく性質を変える元素があることにも驚かされました。
例えばジルコニアは、「ジルコニア(酸化ジルコニウム)のなかでも原子が立方晶の結晶構造をつくるものは、外観も硬さもダイヤモンドにそっくり」なので、単体でも硬いのだと思っていたのに、「ジルコニウムの単体はかなり柔らかく、展性と延性の大きさが特徴です。」なのだとか!
また危険な火山ガスの素だと思っていた、あの臭い硫黄は……
「硫黄の単体は無臭で、毒性はきわめて低いのですが、硫黄を含む化合物には悪臭を放つことでよく知られたものが多く、なかには毒性を示すものもあります。」
……そうだったんだ……。
また途方もなく長い半減期を持つ元素として、「トリウム」は……
「アクチノイドのなかでトリウムとウランだけは、数十億年前に超新星爆発でつくられた原子が今も、かなりの数が残っています。最も安定した同位体トリウム232の半減期は約140億年です。つまり、およそ46億年前に地球が誕生したときに存在していたトリウム原子の約20%ほどしか崩壊していないということです。」
……という長さに驚いていたら、「ビスマス209」の半減期はなんと2000京年! 「ビスマスには安定した同位体は存在しない」そうです。
『宇宙がわかる 新・周期表ガイド』……周期表を構成する元素について、とても詳しく解説してくれる周期表のガイドで勉強になりました。これらすべての元素が、陽子、中性子、電子の、たった3種類で出来ているなんて……とても不思議なことですね……みなさんも、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『宇宙がわかる 新・周期表ガイド』