ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
生物・進化
生物界は騒がしい(ハスケル)
『生物界は騒がしい: 音と共に進化した、生き物とヒトの秘められた営み』2025/3/22
D.G.ハスケル (著), 屋代通子 (翻訳)
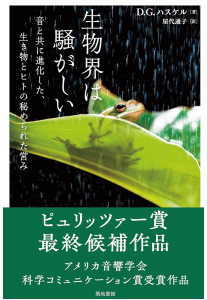
(感想)
歴史、生態学、生理学、哲学、生物学をシームレスに融合させながら、鳥や昆虫、風や海、人の声や楽器が作り出す美しい音を紹介してくれるとともに、人間の「自然破壊による生態系の沈黙」についても警告している本です。
驚きだったのは、「序」に次のように書いてあったこと。
「地球の歴史のうち一〇分の九までは、何かを伝え合おうとする音は存在しない世界だった。海に最初の生き物が群れをなした時、初めてサンゴ礁がせりあがってきた時、歌う生き物はいなかった。原初の森には、声を発する昆虫も脊椎動物もいなかった。(中略)何億年にもわたる動物の進化は、伝達のための音のない中で繰り広げられたのだ。
声は一度進化を始めると、動物たちをネットワークでつなぎ、時には膨大な距離を隔てていても、あたかもテレパシーのように、ほぼ共時的な対話を可能にした。」
……「生物の音」は「あって当たり前」のものかと思っていましたが、実は意外に最近のものだったんですね!
「第一部」によると……
・「原初、地球の音は岩と水、雷鳴と風だけだった。」
・「命が発した最初の音は、バクテリアが自分を取り巻く水に向けたごく微小なつぶやきであり、囁きであり、鳴動だ。」
……二億七〇〇〇万年ほど前のペルム紀の化石に、翅の付け根のところに集まった翅脈が分厚く盛り上がったものが見つかっていて、この昆虫はヤスリをこすったような単純な音を出していたのかもしれないようです。
「コオロギの祖先は、肢によく発達した感覚器官があった。繊毛のある細胞が並び、地面のごくかすかな振動や空気のわずかな圧迫を感じ取った。(中略)鼓膜ができたのはおよそ二億年前のことで、まず間違いなく、音を立てる翅の進化に促されたものだろう。」
……「生き物の音」は、このころから始まったのでしょうか。
この本は生物の音に関する科学的ドキュメンタリーですが、生物の音の調査などが、とてもリアルに描かれています。ところどころに聴覚の進化などの解説もあり、勉強になりました。例えば次のようなことが書かれています。
・「(前略)脊椎動物はそれぞれ非常に異なる方法で音を生み出すが、音を生み出すプロセス時代には発生学上の共通項がある。菱脳と脊柱の交わる部分の神経組織の一部が発達し、成体の音の生成をつかさどる神経回路になっていく。この回路が、動物の発声のパターンを生み出す役割を担うのだ――それは、浮袋を使う魚をとってもそうだし、喉を使う陸生動物の場合も同じ、あるいは胸の中にある独特の管を震わせて生み出される鳥の音をはじめ、ゲロゲロ鳴く音やブンブンいう音を出す鳴嚢や、水をかき分ける胸鰭、平らな表面を打ち鳴らす前腕によって作られる何千もの音のヴァリエーションのすべてがそこに起因する。
発声を統率する脊柱の部位は、胸の周辺、胸鰭や前腕を動かす筋肉の調整も行っている。このふたつが関連していることは、発声と身体の動きの調整を細かくコントロールする必要があることを示している。」
・「わたしたちは、聞くのにも繊毛が必要だ。内耳の、音を感じる一万五〇〇〇個の細胞のそれぞれに、細かい毛の並んだ繊毛がのっている。音の波が耳を伝わると、その動きで毛の束が偏る。それを感知して、細胞が神経系統に信号を送るのだ。このようにして、繊毛によって物理的な動きが感覚に変えられる。」
・「わたしの耳の中の繊毛は、有毛細胞の上にのって、渦を巻いた管の間に挟まれた膜に沿って並んでいる。(中略)高い周波数の音は狭いほうの端を振動させる。低い周波数の音は広いほうを刺激する。人間の可聴域に収まる波長はいずれも、蝸牛の膜の端から端までのどこかに感応する部分があるということだ。」
・「適度な周波数の音が外有毛細胞にあたると、タンパク質が作動し、細胞を上下させる。」
*
そして私たちの耳のつくりについては……
・「わたしたちの頭の両側についているラッパ状の耳介は、外耳道とともに音を一五から二〇デシベル増幅させる。」
・「鼓膜と耳小骨からなる中耳は、空気中の音の振動を蝸牛の中のリンパ液の振動に変換する役割がある。」
・「蝸牛の神経は、内有毛細胞が刺激されると発動する。ひとつひとつの有毛細胞は、蝸牛膜での位置に応じた周波数の音に反応する。」
・「わたしたちの脳は耳からの情報を受け取るだけではなく、耳に信号を出してもいる。蝸牛をその時々の状況によって調整するためだ。騒々しい環境では、脳は外側の感覚毛の感度を押さえる。」
・「わたしたちの感覚感度はヒトコブラクダのようなもので、真ん中あたりの感度は高いが低いほうと高いほうにいくほど鈍くなる。耳は、人間の生存に最も深く関わりのある環境音に合わせてチューニングされているのだ。」
*
……わたしたちは「音」をこんな風に「聴いて」いるんですね。
世界に溢れる生物たちの多様な音は、危機に瀕しているようです。
「世界の多様な音が、今危機に瀕している。われわれ人間という種は、音の最高の作り手であると同時に、世界に満ちる豊かな自然の音を大々的に損なっている破壊者でもある。生態系の破壊と人間の発想る雑音が、世界中で音の多様性を消失させている。(中略)自然の音が消え去り、人間の雑音がその他の声を圧してしまえば、地球は活気を失い、単調な場所になる。」
……私たちの立てる騒音は、その場に生きる生物のコミュニケーションを阻害するだけでなく、ストレスを与えたり、さらに激しい振動で命を奪ったりすることがあるようでした(涙)。
「命ある存在がつながる時、新しい可能性が芽生える。動物の声は新しいものを生む触媒だ。」
……動物の声を守り、環境を守っていくことが、私たちの地球の豊かさを維持することにつながるのでしょう。
そのためにも「環境録音」が役に立ちそうに感じました。「第5部」には次のように書いてありました。
・「これから数年後の音の風景には、今まであった地球の声のいくつかが失われていることだろう。したがって、現在わたしたちが録音しているものの一部は、絶滅の備えになる。」
・「将来的に、環境録音は政府や地域コミュニティ、企業、組織、木材などの産品の状態を監視し、その安定性に「お墨付き」を与えたい者たちのモニタリングを強化する道具になることも考えられる。」
また「日本の音風景一〇〇選」についても紹介されていました。でも2018年の調査では、最初の一〇〇選のうち五つが失われたか、その場にいけなくなっていたそうです。消えずに残っている音は、地方自治体なり市民グループが、保存のために何らかの活動を行っていたとのことで……ちょっと寂しく感じましたが、それでもこの取り組みには意義があるようです。
「日本の音風景一〇〇選は、選定地以外の場所でも、音への意識を高めるきっかけになった。」
*
『生物界は騒がしい: 音と共に進化した、生き物とヒトの秘められた営み』……音を通じて生物の進化や環境問題を考察している本で、とても勉強になりました。人間のたてる騒音が生態系を破壊してることについて、あまり考えたことがなかったことを反省させられました。みなさんも、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『生物界は騒がしい』