ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
生物・進化
植物たちに心はあるのか(田中修)
『植物たちに心はあるのか (SB新書 688)』2025/4/6
田中 修 (著)
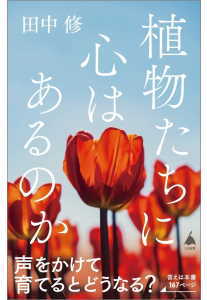
(感想)
「植物たちは生き方の極意を知っており、たくましく命を守って生きているということを、多くの人に知ってほしい」という願いをもって、植物に心や心意気、気持ちを感じるような事例があることを紹介してくれる本で、主な内容は次の通りです。
第一章 植物たちの生き方に心を感じる
(一)植物たちは、「動きまわりたい」と思っているのか?
(二)植物たちは、「光を欲しい」と思っているのか?
(三)植物たちは、「水を欲しい」と思っているのか?
(四)植物たちは、「二酸化炭素を欲しい」と思っているのか?
第二章 子孫の繁栄を願う親心
(一)植物たちが、花に込める思いとは?
(二)「一人ででも、子どもを残したい」という思いを遂げる!
第三章 からだを守り、命をつなぐための心意気
(一)「暑さや寒さに打ち勝つ!」という心意気
(二)「紫外線に負けない!」という心意気
(三)食べられる宿命に備える心意気
第四章 まるで心があるかのような反応
(一)刺激に反応する心があるかのようなしくみ
(二)人間の刺激に心で反応するようなしくみ
第五章 植物の心、日本の心
(一)サクラの心情を探る!
(二)「日本人の心の花」は?
*
「第一章 植物たちの生き方に心を感じる」では、植物たちは、「動きまわりたい」とは思っていないだろうと書いてありました。その理由は……
・「(前略)植物が食べ物を求めて動きまわらないのは、植物たちは、葉っぱで自分の食べものをつくることができるからなのです。」
・「植物たちは、根から吸った“水”と、葉っぱが吸収する“二酸化炭素”を材料にして、太陽の“光”を使って、自分の力で、食べものをつくります。この反応は、「光合成」といわれます。」
……確かにそうですね。
その一方で、植物は「光」や「水」を求めているようです。
例えば、暗がりでひょろひょろ伸びていくモヤシ。モヤシに日を当ててやると、もっと伸びそうに見えますが、そんなことはまったくなく、光が当たるとモヤシの成長は止まるそうです。なぜならモヤシは光を探し求めて伸びているので、日が当たれば、もうそれ以上伸びる必要がなくなるから……なるほど。
そして芝生。芝生には「水が足りなければ水を求めて根を伸ばす」という性質があるので、水がないと水を求めて、たくさんの強い根を精いっぱいに伸ばすそうです……植物たちは、ちょっと過酷な環境の方が、大きく強く成長するんですね……(人間も、かもしれませんが……)。
そして「水」が根から吸われる仕組みは「蒸散」によるもので、水が葉っぱの気孔から蒸散して空気中に出ていくと、出ていく水に引っ張られて、下の水は上の方へ引き上げられるそうです。
また「二酸化炭素」については、植物たちは二酸化炭素を積極的に吸い込むのではなく、二酸化炭素は葉っぱの中にひとりでに入ってくるのだとか。葉っぱが光合成をして二酸化炭素を使うと、葉っぱの中の二酸化炭素濃度が低くなるので、空気中の二酸化炭素が葉っぱの中に移動してくるわけで……植物は、割と単純な仕組みで生きているんですね……。
「第三章 からだを守り、命をつなぐための心意気」では、動かない植物が、自らの体を守るための方法を、いろいろ持っていることを知りました。
例えばタネ。タネの役割の一つは、不都合な環境に耐えて生きのびることなのだとか。
「草花たちは、夜の長さをはかることによって、寒さ、暑さの訪れを前もって知り、花を咲かせてタネをつくり、暑さ、寒さを耐え忍んで生きているのです。」
また最近は夏がどんどん暑くなっていって、人間でも生きるのが大変ですが、植物も頑張って耐えているようです。
「葉っぱでは、光合成を進めるために、多くの酵素という物質がはたらいています。酵素はタンパク質であり、温度が高くなるとはたらかなくなる性質があります。すると、光合成ができませんから、温度が高くなりそうになると、葉っぱは必死に抵抗します。
その方法は、汗をかくことです。葉っぱの表面から水をさかんに蒸散させるのです。」
……蒸散には、そんな効果もあったんですね。「緑のカーテン」は夏の暑さ対策としてもとても優秀なようです。
さらに冬の寒さに耐えるために、常緑樹の葉っぱは、冬に向かって、葉っぱの中に凍らないための物質(糖分など)を増やすそうです。これは冬の寒さに耐える多くの植物に共通のもののようで、「寒じめホウレンソウ」や「雪下ニンジン」などは、植物のこの力を利用して甘くしているのだとか。
さらに紫外線対策としては……
・「紫外線は、植物であろうと人間であろうと、からだに当たると「活性酸素」という物質を発生させるのです。活性酸素は、「老化を急速に進める」、「生活習慣病、老化、がんの引き金になる」などといわれます。」
・「そのために、植物たちは、活性酸素を消し去る働きをする「抗酸化物質」とよばれるものをからだの中につくります。抗酸化物質の代表は、ビタミンCとビタミンEです。」
・「花々が、花びらを美しくきれいに装うのは、紫外線が当たって生み出される有害な活性酸素を消去するためであり、植物たちの生き残り戦略の一つなのです。このため、植物に当たる太陽の光が強ければ強いほど、活性酸素の害を消すために多くの色素がつくられ、花の色はますます濃い色になります。」
……人間の美容にも良いとされるビタミンCやビタミンE、さらに植物の美しい色までが、植物たちの紫外線対策(アンチエイジング)だったんですね……。
さらに「第四章 まるで心があるかのような反応」では、植物たちを優しく撫でてあげると、大きく立派に育つということは事実だと書いてありました。実は、これには「エチレン」が関係していて、植物は触られるとエチレンという気体を発生させるのですが、エチレンには「茎の伸びを押さえて、茎を太くする作用」があるそうです。
また切り花を長持ちさせるためには、少し寒くしてあげる方が良いようで……、
「温度が高いほど呼吸は激しくなり、花の老化が促されます。呼吸が激しくなると、切り花に蓄えられている、栄養が急速に使われてしまいます。ですから、温度を低くすると、呼吸が抑制され、花の老化の速度が遅れ、花の寿命は長くなります。」
*
『植物たちに心はあるのか』……植物たちは、いろんな方法で自らの体を守り、光・水・二酸化炭素を得ようとしていることを学ぶことが出来る本でした。植物好きの方は、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『植物たちに心はあるのか』