ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
生物・進化
ぼっちのアリは死ぬ(古藤日子)
『ぼっちのアリは死ぬ ――昆虫研究の最前線 (ちくま新書 1851)』2025/4/10
古藤 日子 (著)
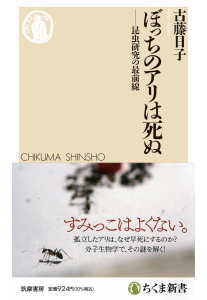
(感想)
孤立したアリは、なぜ早死にするのか? 分子生物学で、その謎を解きあかしていくとともに、アリの不思議な世界を詳しく紹介してくれる本で、主な内容は次の通りです。
はじめに
第1章 なぜアリを研究するのか?
1 モデル生物
2 アリとヒトを比べる
第2章 アリの生活史
1 クロオオアリのコロニー
2 アリの社会のはじまり
3 ゲノム編集
第3章 孤立アリは早死にする
1 1944年の論文
2 ウロウロする孤立アリ
3 トランスクリプトーム解析
第4章 鍵はすみっこ行動
1 原因は酸化ストレス
2 舞台は脂肪体
3 昆虫進化のひみつ
4 鍵はすみっこ行動
5 寿命はなぜ縮むのか
第5章 アリから学ぶ社会と健康
1 アリの生きる意味
2 アリからのヒント
おわりに
注
図版出典
索引
*
「第1章 なぜアリを研究するのか?」では、「社会的な孤立が健康にマイナスの影響を及ぼす」ことを調べるために、社会的な昆虫のアリをモデル生物とした研究を始めたこととともに、「モデル生物」についての解説がありました。
例えば癌の発症を人工的に誘導できるようなモデル生物を作ることができれば、たくさんのサンプルを使って発症プロセスを調べたり、遺伝子情報を調べたりできるのです。次のように書いてありました。
・「(前略)モデル生物は飼育や繁殖が容易であり、世代交代が短期間であることが期待されます。」
・「モデル生物のすごいところは、特定の遺伝子を操作する実験が可能であるだけではなく、注目した生命現象に関わる遺伝子を網羅的に調べることができるところにあります。」
*
「第2章 アリの生活史」では、アリの社会は、各個体が自律的に行動していることが紹介されていました。
「アリの社会は、女王アリや特定の個体がリーダーとなって全体に対して仕事の指示をしているわけではありません。それぞれの個体が、自分の周囲の局所情報を手掛かりにして自律的に行動することが、社会全体の群れとしての振る舞いを作り出していると考えられています。」
*
そしていよいよ「第3章 孤立アリは早死にする」。ここでは、二次元バーコードをアリの胸部に貼り付けることで、それぞれのアリを識別して長期間にわたり行動を観察した研究の成果が詳しく紹介されていました。
「(前略)グループで飼育する労働アリは約67日で実験した個体の半分が死に至るのに対して、孤立アリは約7日で半数の個体が死んでしまうことがわかりました。孤立アリの寿命は、グループアリの約10分の1程度にまで短くなっていました。」
……驚くほど早死にしてしまうんですね(涙)。
孤立アリは他のアリとは違って、外でより長い距離を、より速い速度でウロウロし続けることが多いようです。
「グループアリとは異なり、孤立アリは巣のなかで過ごす時間が顕著に少なくなります。」
……しかも孤立アリは、お腹の調子が悪くなるようで……
「(前略)グループアリと孤立アリで、ごはんを食べた量には大きな差がないことがわかりました。
次に、腹部を解剖し、素嚢と消化管を切り離して、消化管に入っている食べ物の量を測ってみると、孤立アリでは半分程度にまで減少していることがわかりました。
つまり、孤立アリはごはんを食べているにもかかわらず、その食べた分を素嚢に蓄えたままにして、自分で消化しエネルギーに変えることができない状態となっていたのです。」
……実は、アリは口移しで餌や水をお互いに与え合う栄養交換を行う習慣があり、餌を仲間と分かち合うことが出来ないと、自分で消化できない可能性もあるようでした……なんだか、せつないですね……。
「第4章 鍵はすみっこ行動」では、孤立アリの状態について、体の内部状態や遺伝子まで調べた結果が紹介されていました。
グループアリと比較して、孤立アリで大きく発現量が変化している遺伝子を同定すると、894もの遺伝子が候補にあがったそうです。たった1日、社会的な環境が変わっただけで、こんなにも多くの遺伝子に変化があるなんて……アリは本当に「社会的な交流」に依存している生物なんですね……。次のようにも書いてありました。
・「(前略)より長く壁際の近くで過ごす個体ほど、酸化ストレスに関わる遺伝子群が顕著に変化することがわかったのです。この中には、(中略)活性酸素を作るための遺伝子、そして活性酸素を除去するための遺伝子のどちらも含まれていました。(中略)
つまり、孤立環境に対する行動の反応性が高く、顕著な行動変化を起こす個体ほど、酸化ストレスを増悪させる方向に、遺伝子の発現も大きく変化していことがわかったのです。」
・「頭部と消化管、そして脂肪体の3つの組織、それぞれで産生された活性酸素の量を調べてみると、驚いたことに、活性酸素量が増加しているのは脂肪体のみであり、脳や消化管では、グループアリと孤立アリで活性酸素の量は変化していないことがわかりました。」
*
……孤立アリでは、脂肪体全体のなかで、脂肪滴を溜め込むトロフォサイトに比べて、特に丸く小さなエノサイトで活性酸素が高く蓄積している様子が観察されたそうです。
・「(前略)加齢や、アリの孤立ストレス応答などによってエノサイトは活性酸素が蓄積しやすい、ダメージを受けやすい細胞であることがみえてきました。」
・「加齢によってエノサイト自身がダメージを負いやすいだけではなく、全身性の加齢性疾患の発症に関わる可能性がある、非常に重要な細胞と考えられるようになりました。」
……ここでは、「すみっこにいるほど酸化ストレスが強い(壁際滞在時間と脂肪酸の酸化ストレス度合いには統計的に相関がある)」ことが明らかにされています。このすみっこ(壁際に滞在する)行動は、酸化ストレスが起こった結果として引き起こされたようです。
そして「第5章 アリから学ぶ社会と健康」には……
「すみっこにいることで、敵に見つかりにくく自分の身を守られていたつもりが、実はそれ自体は自分の体になんらかのマイナスの影響を与えている可能性も考えられるのかもしれません。」
……社会的昆虫のアリの世界では、孤立のストレスは早死にまでつながってしまうんですね……。
『ぼっちのアリは死ぬ ――昆虫研究の最前線』……アリをモデル生物とした「社会的孤立」研究の結果を知って、ちょっぴりせつなくなりましたが、分子生物学的な研究手法について具体的に学ぶことができて、とても勉強になりました。生物学が好きな方は、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『ぼっちのアリは死ぬ』