ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
科学
生命にとって金属とはなにか(桜井弘)
『生命にとって金属とはなにか 誕生と進化のカギをにぎる「微量元素」の正体 (ブルーバックス B 2284)』2025/2/20
桜井 弘 (著)
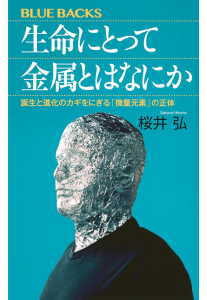
(感想)
「微量」の名とは裏腹に、多種多様で、きわめて重要な役割を果たしている生体金属。その存在は、生命の誕生と進化にどう関わったのか? 「金属=無生物」の視点からみた壮大な生命史で、主な内容は次の通りです。
金属はすごい!
プロローグ カンブリア大爆発はなぜ起こったか?
第1章 生命の誕生と金属
第2章 生命のエネルギー源「酸素」を使いこなす金属
第3章 「新しい生物の出現」を可能にした金属のはたらき
第4章 微量元素を使え!
第5章 金属とはなにか
第6章 金属を薬にする!
*
「プロローグ カンブリア大爆発はなぜ起こったか?」には、「生体必須微量元素」について、次のような説明がありました。
「ヘモグロビンの生合成に必要な鉄、銅、亜鉛のほかに、マンガン、セレン、モリブデン、クロム、コバルトなども生体必須微量元素として知られている。さらに、必須かもしれないと考えられている微量元素として、鉛、スズ、ニッケル、バナジウムなどがある。」
そしてこれらの微量元素と生命体との関わりについては……
「生命はその誕生初期、エネルギーを効率よく使用するために、電子をたくさんもっている元素、すなわち金属イオンを真っ先に利用したと考えられている。そして、その一番手が、酸素分子が存在しなかった時代の海水中で、最も豊富に存在していた鉄(鉄イオン)だった。」
……その後、シアノバクテリアの繁殖で地球上に酸素が増加して……
「シアノバクテリアはますます繁殖し、やがて海洋中の酸素濃度が飽和しはじめる。海水に多く溶け込んでいた鉄イオンは酸素分子と反応し、水に溶けない酸化鉄となって、海底へと沈んでいった。
その結果、海洋中の鉄の量が減少し、相対的に濃度が高くなった鉄以外のいくつかの金属イオンが生体に取り込まれ、新たに利用されるようになっていく。新しい金属イオンの登場によって、金属が関与する生体機能に変化が生じ、その変化によって生物の進化に新しい道筋が生まれたと想像される。」
*
そして興味津々だったのが、カンブリア爆発についてで……
「――カンブリア爆発はなぜ、どのようにして起こったのか?
生物の進化における最大級の謎はまだ解き明かされていないが、いくつかの仮説が発表されている。この大事件が発生したころ、大陸の大移動や地球全体が氷で覆われて凍りつく「全球凍結」などがあり、大陸移動や火山の噴火熱などによる岩石や土の溶解、あるいは氷の融解にともなって大量の岩石や土砂が海洋へと流れ込んだ可能性が考えられる。
その結果、当時の海水中にはあまり含まれていなかった多種多様な元素、特に金属元素が岩石や土砂とともに海洋に流入して溶けはじめ、それらが海洋中の植物や微生物を含むさまざまな生物の体内に取り込まれた可能性が考えられているのだ。」
……微量元素が生命の進化を促進したのかもしれない、と言うのです!
「第1章 生命の誕生と金属」では、生命の誕生と進化に関係があるものとして、次の2つの事実が書いてありました。
1)体の中のタンパク質や酵素には、金属イオンを含むものがある
2)生体中の金属イオンを取り巻く環境は、鉱物の構造(結晶構造)とよく似たものがある。
「すなわち、体の中の金属を含むタンパク質や酵素は、鉱物の構造をそっくりそのまま取り込んだか、あるいは、それらをまねてつくられたか、ではないかと考えられる。」
……タンパク質は「形」が重要だと言われていますが、それは「鉱物の構造」から来ているのかも……なんだかワクワクさせられる仮説ですね。
「第2章 生命のエネルギー源「酸素」を使いこなす金属」では、隕石落下でアミノ酸が生成される可能性があることが書いてありました。
「隕石が海洋に超高速で衝突すると、その衝撃によって高温の蒸気雲が形成され、液体(水)・気体(大気)・固体(隕石)の3状態が界面で相互に反応すると考えられる。コンドライトやエンスタタイト・コンドライト、あるいは鉄-ニッケル合金からなる鉄隕石などの金属鉄を含む隕石が衝突すると、高温の蒸気によって金属鉄が酸化され、同時に窒素や炭素が還元されて、アミノ酸などの有機物の生成が期待されると考えられている。」
*
さて、生命はシアノバクテリアのせいで地球に激増した酸素を使うことを選択しましたが、それは体内にあるグルコースを使って呼吸をすると、大きなエネルギーを得られるからでした。ただし、それにはリスクも伴いました。
「(前略)生物は酸素分子を用いて大きなエネルギーを得る一方、体内で活性酸素種が発生する大きな危険を冒してまで、酸素分子を利用する方向での進化を遂げる道を選んだ。
しかしそれは、酸素のもつ強い毒性を甘んじて引き受けるという消極的なものでは決してない。生物は同時に、長い時間をかけて酸素の毒性を抑え込む方法も一生懸命に獲得してきたのである。」
・「生物はこのように、さまざまな金属イオンと酸素分子を用いてエネルギーを得る一方、金属イオンや半金属元素を用いて酵素をつくる方法を獲得し、酸素分子による毒性を回避する方法を見出した。」
……微量元素は、進化の上でも、生体内でも、大事な役割を果たしているんですね。
「第3章 「新しい生物の出現」を可能にした金属のはたらき」では、生物が多細胞に進化するためにも、微量元素が働いた可能性が指摘されていました。
・「(前略)原核生物は酸素分子を利用する単細胞生物から始まり、約6億年前に多細胞生物へと進化した。単細胞生物から多細胞生物へと進化するためには、細胞どうしをつなげ合う、すなわち「接着する分子」が新たにつくられたに違いない。」
・「細胞接着の実験では、カルシウムやマグネシウムイオンを結合する化合物「EDTA」(エチレンジアミン四酢酸。キレート剤として用いられる)を加えておくと接着が起こらないことから、細胞と細胞外基質との接着にはマグネシウムイオンが、細胞どうしの接着にはカルシウムイオンが必要であることが見出された。生物は、多細胞化を実現するための細胞接着という進化上きわめて重要な機能を獲得するにあたっても、金属元素の活用を選択するという驚異的な能力をすでに獲得していたと考えられる。」
*
そしてカンブリア紀に突然、遊泳できる新しい生物が多数出現した理由として考えられていることは……
1)大気中の酸素濃度の急激な増加と、二酸化炭素の減少
2)地表から溶け出したリン酸カルシウムによって、利用可能なリンの量が増大
3)大陸変動によって大陸棚の面積が増大し、光合成が可能な地域が増大したことによる植物プランクトンの増大
4)骨格をもつ動物の誕生
5)脳や消化器官、さらには眼(レンズ眼)をもった動物の出現
*
……などが挙げられています。さらに次のようにも書いてありました。
「酸素呼吸には鉄(ヘモグロビンとミオグロビン)や銅(ヘモシアニン)が使われ、骨格の形成にはカルシウム、鉄、銅、亜鉛、バナジウムなどが用いられ、脳や消化器官では高度なシグナルを伝達できる神経系の形成にはナトリウム、カリウム、カルシウム、鉄、銅、亜鉛、マンガンやセレンなど多数の元素が要求された。
さらに、ATPなどの高エネルギーを生み出す化合物や、DNAやRNAなど遺伝情報を伝達するための化合物の作製には、酸素分子とともに、リンの利用が必要だった。」
……微量元素が生物に積極的に利用されるようになったことで、爆発的な進化が起こったのかもしれません。
『生命にとって金属とはなにか 誕生と進化のカギをにぎる「微量元素」の正体』……生命の誕生や進化に、微量元素が大きく関わっていることを教えてくれる本で、とても勉強になりました。最終章「第6章 金属を薬にする!」では、人間は、紀元前から鉄などの鉱物を医薬品として使ってきたこと、今でも新しい薬が開発されていることが紹介されていました。金属と生命の意外なほどの深い関わりに、興味津々でした。みなさんも、ぜひ読んでみてください。お勧めです☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『生命にとって金属とはなにか』