ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
伝記・職業紹介
めざせマントル!(道林克禎)
『めざせマントル!──地球を掘る地質学者の冒険 (岩波科学ライブラリー 331)』2025/3/7
道林 克禎 (著)
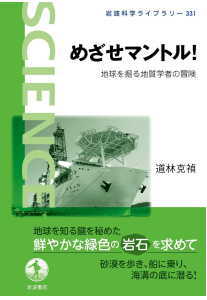
(感想)
マントルの岩石を求めて砂漠を歩き、船酔いに苦しみながら海底から堀り上げた岩石と格闘し、ついには水深9800メートルの海溝の底にまで潜った研究者の見聞記で、主な内容は次の通りです。
プロローグ 鮮やかな緑色の砂利
1 マントルと出会う
2 マントルまで掘れるかも――深海掘削計画
3 海溝の底でマントルを採りたい
4 月より遠い道
5 マントルの痕跡を掘る――オフィオライト掘削と「ちきゅう」船上合宿
6 超深海への潜航
エピローグ
*
『めざせマントル!』というタイトルから、マントルの科学的知見について解説してくれる本だと思ったのですが、知識の解説というよりは、地質学研究者的紀行文という感じの本でした。
もちろんマントルに関する解説もあって、地球の内部構造を「卵」に譬えた話はとても分かりやすかったです。
「(前略)地球の内部構造は、卵に譬えられる。外側から殻が地殻、白身がマントル、黄身が中心核である。地下核とマントルは主に岩石で、中心核は金属でできている。白身に相当するマントルは、このうちの約八割を占めているので、大雑把に言えば「地球はマントルでできている」といえる。さらに、そのマントルはカンラン岩(とその高圧相)を主成分とするので、「地球はカンラン岩でできている」と読み替えられる。
このように地球の内部構造はよく知られているにもかかわらず、人類は未だにマントルに直接到達していない。マントルは地殻に覆われており、一番薄い海底の地殻でも六キロメートル地下までいかないと辿り着けない。この六キロメートルを掘り抜く計画は一九五〇年代からマントル掘削計画として知られている。」
……地球は、ほぼマントルでできていたんですか! それなのに「マントルの実物」にはまだ誰も触っていないようで……近くて遠い物質なんですね……。
さてマントル研究には、次の3つのアプローチがあるそうです。
1)地震学的にマントルの構造を“直接”観測する方法(地震波の解析)
2)実験室にマントルと同じ環境(数千度&数百万気圧)を再現する方法。(高圧科学)
3)地表に現れたマントル物質を調べる方法(地質学)
……道林さんは、このうち3番目の方法(地質学)が専門分野なのだとか。そして地表に露出したマントル物質を含む岩石の塊(岩体という)は、オフィオライトとよばれているそうです。
オフィオライトは日本にもありますが、最も規模が大きく有名なのはアラビア半島東端のオマーン国の黒い山脈をつくるオフィオライトだそうで、道林さんはここで調査を行っています。
オフィオライトを分析することで、プレートの形成から改変までを解き明かすことが出来るようで、本書では次のようなことを地道に行っていました。
「(前略)カンラン岩を構成している鉱物(カンラン石、スピネル、直方輝石、単斜輝石)のうち、スピネルと直方輝石は面状に配列して面構造を示している。さらに、面構造上の鉱物は、ある特定の方向に伸張して線構造を示している。この面構造と線構造を同定するために、岩石標本に一個ずつ、「面だし」という作業を行う。
面だしとは、岩石カッターで岩石標本の端を切断して平面をいくつか作り、その平面の鉱石の配列を調べて、二次元の広がりをもつ面構造を決める作業である。面構造が決まると、面構造に平行な面を岩石カッターで切断して、線構造を決める。」
……これを夏中ずっと毎日やっていたようで……地質学研究者の仕事は、結構「体」を使うようです(笑)。
さて日本には、「世界有数の状態のよいカンラン岩」である幌満カンラン岩体があります。さきほど研究していたオマーン国のオフィオライトは蛇紋岩ですが、幌満のは素晴らしいカンラン岩なのです。
「カンラン岩は、地下深くの高温高圧下で水と反応すると蛇紋岩という黒っぽい岩石に変わる。地表で見られる岩石のなかで、厳密にカンラン岩としてよいものは、幌満カンラン岩くらいで、その他は蛇紋岩だ。」
……カンラン岩中の少量の鉱物(直方輝石、単斜輝石、スピネル、斜長石、ガーネットなど)の形や配列を丁寧に観察すると、特定の向きになんとなく揃っている様子(定向性)が見えてくるのですが、それは「マントルでクリープ(注:ゆっくり動く)した痕跡」なのだとか。また、次のようなことも……
「(前略)地球表層の七割は海洋なので、ほとんどのプレートは海水で覆われている。そのため、海底からプレートに水が浸透する。浸透した水は、海溝から沈み込んだプレートがマントル深部で暖められると脱水してウェッジマントル(沈み込んだプレートの上側に位置するマントル)に移動し、マグマに溶け込んで島弧の火山活動を介して地表に戻る。これが惑星地球のもう一つの物質大循環を成す水循環である。私はこれを地球リサイクルとよんでいる。
地球リサイクルを駆動しているのがマントル対流、つまり地球のクリープ現象であり、その痕跡がカンラン岩の構造として残されている。」
*
そしてこの後は、「しんかい6500」の潜行調査など、深海底での掘削調査を行ったことなどが、具体的に詳しく紹介されていました。このように何度もトライしているのですが……残念ながら、現在(2025年3月)までカンラン岩は見つかっていないようです。
『めざせマントル!──地球を掘る地質学者の冒険』……マントル物質を掘り上げようと頑張っている地質学者の研究生活(紀行)を描いた本です。砂漠地帯での調査や深海での調査など、普通の人にはあまり縁がない環境での研究の実態を知ることが出来て、興味津々でした。地質学に興味のある方は、読んでみてください。
<追記>
この感想を書き終えた後、2025年6月のNHKニュースで、「20億年前の地層から採取の微生物 鉄さびで呼吸か 東大など」という情報について知りました。南アフリカの北東部に広がる20億年前の地層の「地上から微生物が侵入する可能性が低くなる深さおよそ1200メートル」から「カンラン岩」を採取し、その岩の中にある「鉄さび」の周りに微生物が集まっていたことが確認されたようです。残念ながら「六キロメートル」以上の深さではありませんが、「カンラン岩」から「鉄さびで呼吸する微生物」なんて、凄いことですね……今後の展開に期待したいと思います☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『めざせマントル!』