ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
医学&薬学
東洋医学はなぜ効くのか(山本高穂)
『東洋医学はなぜ効くのか ツボ・鍼灸・漢方薬、西洋医学で見る驚きのメカニズム (ブルーバックス B 2261)』2024/5/16
山本 高穂 (著), 大野 智 (著)
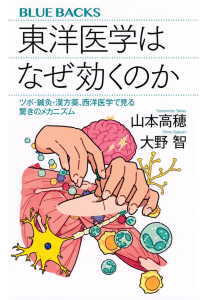
(感想)
私たちの生活に身近なツボ・鍼灸・漢方薬。近年、そのメカニズムの詳細が、西洋医学的な研究でも明らかになってきていることを解説してくれる本で、主な内容は次の通りです。
第1章 鍼灸で「痛み」が和らぐのはなぜか
第2章 心とからだを整える鍼灸の最新科学
第3章 漢方薬は体内で「なに」をしているのか
第4章 「人に効く」を科学する
第5章 今すぐ実践! ツボのセルフケア
*
「第1章 鍼灸で「痛み」が和らぐのはなぜか」には、ツボ(経穴)の2つの特徴が次のように書いてありました。
1)心身に不調があるときに痛みなどが生じる反応点の役割(診察ポイントになる)
2)治療点の役割(鍼を刺す、灸をすえるポイントになる)
*
「鍼灸において、ツボと同じくらい大切だとされるのが経路と呼ばれる概念です。体がもつエネルギーとされる「気」や、血液などの「血」の流れを示す道筋とされ、特定の臓器や体の部位と密接な関係があると考えられています。具体的には経脈と絡脈の2つがあり、経脈は主要な幹線の役割を担い、絡脈は経脈をつなげる役割があるとされています。」
……そしてツボ、つまり経穴を刺激して痛みや不調を和らげようというのが鍼灸だそうです。
鍼灸による刺激では……
「(前略)鍼先で生じた刺激は、まず感覚受容器でインパルスに変換され、末梢折神経を通り脊髄に入ります。この脊髄で起こる反応もありますが(中略)、信号はここから2つのルートに分かれ、脳に向かいます。痛覚や温度覚などを伝える前索・側索系と、触覚などを伝える後索-内側毛帯系と呼ばれるルートです。そして、脳に到達したインパルスは、生体リズムを司る視床下部や、視床、そして大脳皮質に入り、痛み感覚をはじめ、さまざまな脳の部位の働きを調節します。つまり、全身の神経を巡るこのインパルスこそが、鎮痛をはじめとした鍼や灸による治療の大部分の効果をもたらすカギとなるのです。」
……という仕組みのようですが、どうやら鍼灸やツボ押しは、血流をよくして痛み物質を流してしまうとか、痛みを抑制する内因性オピオイドの分泌メカニズムをはたらかせるなどの方法で、鎮痛効果をひきだしているようでした。
ここでは痛みに関する解説もあって、例えば「痛みの通り道」については……
「(前略)皮膚や筋肉などで生じた痛み刺激は、感覚神経の末端にある感覚受容器を興奮させ、痛みの信号(インパルス)に変換されます。痛みのインパルスは、感覚神経によって脊髄を経由して、脳へと上っていきます。そして脳のほぼ中央に位置し、感覚情報を中継する視床や、脳の表面部分にあり、痛みの感覚を感知する大脳皮質に送られるのです。」
……そしてこの痛みの伝達途中にある背骨の部分に、痛み信号を送ったり痛み情報を調節したりする神経回路(膠様質(SG)細胞)があるそうです。
その他にも以下のようなことが書いてありました。
・鍼灸刺激によるインパルスは、ノルアドレナリン系とセロトニン系の神経細胞に働き、両方の系を駆動する役割を持つ内因性オピオイドを分泌させることで、それぞれの神経活動を高める。
・ストレスによって引き起こされる痛みのメカニズムには自律神経のひとつである交感神経も関わっており、鍼灸の刺激はこの神経のはたらきを調節して痛みを緩和する。
*
続く「第2章 心とからだを整える鍼灸の最新科学」では……
・鍼灸によって活性化することが報告されているのは、大脳の一次体性感覚野、運動や、前帯状皮質、頭皮質などの領域。反対に活動が低下する脳の領域は、内側前頭前皮質、偏桃体、海馬など。
・鍼灸によってドーパミンの分泌が促進されることで、意欲や幸福感が改善するが、鍼灸には、ドーパミンの過剰な分泌を抑えるという逆の作用もある。その理由の一つと考えられるのは、鍼の刺激が作用するルートが、心身の状態によって変化するというメカニズム。
・「(前略)体性-自律神経反射では、鍼灸の刺激を行う場所の違いで交感神経、あるいは副交感神経のはたらきが高まるという異なる作用がもたらされます。」
・「(前略)鍼灸治療の多くは、体性-自律神経反射のメカニズムを上手に利用して、血管や血流に関わる症状(高血圧、低血圧、冷え性、ホットフラッシュなど)や、胃腸に関わる症状(消化不良、便秘、下痢など)、また、泌尿器に関わる症状(頻尿、尿漏れなど)の改善をもたらすと考えられているのです。」
*
……など、かなり科学的な解説がありました。鍼灸はうつ病や認知症への治療効果も期待されているようです。
そして「第3章 漢方薬は体内で「なに」をしているのか」では、漢方薬について、さまざまな解説がありました。
ちなみに漢方薬とは、植物、動物、鉱物などの天然物からなる生薬を調合してつくられているもので、日本で医療用に使われている生薬は137種類あるそうです。
例えば、風邪によく使われる「葛根湯」には、免疫機能の調節と解熱作用があり、「麻黄湯」は、ウイルスの「侵入→脱殻」のプロセスを食い止めることで増殖を抑え、「香蘇散」は、うつ・ストレス症状の改善に処方されているようです。
また頭痛やめまい・むくみ・二日酔いの症状改善に使われている「五苓散」は、体内の水のバランスが異常なときだけアクアポリンのはたらきを阻害していることが研究で明らかにされたそうです。科学的な研究によって、漢方薬についても、なぜ効果があるのかが明らかになりつつあるんですね☆
『東洋医学はなぜ効くのか ツボ・鍼灸・漢方薬、西洋医学で見る驚きのメカニズム』……鍼灸や漢方薬について、最新研究で分かってきたことを含めて総合的に解説してくれる本で、とても勉強になりました。最終章の「第5章 今すぐ実践! ツボのセルフケア」では、肩こりや腰痛、メンタルの改善などに関わる28の代表的なツボについても、イラスト付きで解説してもらえます。
鍼灸や漢方薬での治療を受けている方はもちろん、東洋医学に興味のある方も、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『東洋医学はなぜ効くのか』