ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
医学&薬学
RNAの科学(金井昭夫)
『RNAの科学: 時代を拓く生体分子』2024/7/2
金井 昭夫 (編集)
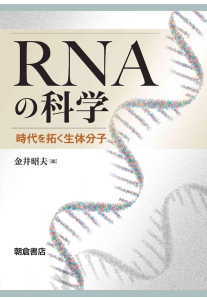
(感想)
RNAの基本的なはたらきから最近の知見まで、全体像を俯瞰できるオールカラーの本で、主な内容は次の通りです。
I RNAの基礎生物学
1章 転写
2章 mRNAスプライシング
3章 tRNA,リボソームとrRNA
4章 tRNAとrRNAの修飾
5章 真核生物の翻訳制御機構
6章 遺伝子発現の正確性を保証する品質管理機構
II 機能性RNA
7章 miRNA経路の全体像
8章 miRNAと翻訳因子の制御
9章 piRNAと生殖
10章 lncRNAによる個体レベルでの機能制御
11章 lncRNAと細胞内相分離
12章 細菌のsRNA
III RNA分野の新技術
13章 CRISPRの構造と機能
14章 RNA分野の新技術─miRNAやsiRNAを用いた創薬研究
15章 mRNA創薬─mRNAを薬として用いる
16章 リボザイムとその応用
17章 RNAの合成生物学
IV RNAと進化
18章 RNAワールド仮説と生命の起源
19章 rRNAの進化と進化工学
*
「RNAの教科書」をめざして作られた本で、RNAについて総合的に網羅しながらも、詳細に具体的に解説してくれていて、とても勉強になりました。
転写はRNAポリメラーゼや転写関連因子がプロモーター領域を認識することで始まりますが、「1章 転写」から、その一部を紹介すると、次のような感じです。
・「Pol I(注:RNAポリメラーゼI)によるrRNA遺伝子のプロモーターの認識には、転写開始点のすぐ上流にあるコアプロモーター領域と、それより100~160塩基ほど上流にあるupstream control element(UCE)領域が必要である。これら2つの領域にupstream binding factor(UBF)タンパク質が結合し、TATA binding protein(TBP)やTAFIタンパク質群(TAFIA~D)、RRN3を含むselectivity factor 1(SL1)とPol Iがプロモーター領域にリクルートされ、転写が開始される。」
・「転写を開始したRNAポリメラーゼは、一定のスピードで転写を続けていくわけではない。(中略)
Pol IIが正確な位置から転写を始めるためにプロモーター上に形成されたPICであるが、Pol IIは他のPICの因子と結合したままでは、転写を続けることができない。そこで、Pol IIは転写開始後10塩基ほど合成したところでTFIIBやTFIIE、TFIIFと解離し、転写を伸長させる。このステップのことをプロモーターエスケープと呼ぶ。プロモーターエスケープには、TFIIHの構成因子であるCDK7による、Pol IIのCTDのSer5のリン酸化が必要である。このリン酸化により、メディエーターとPol IIの結合が弱まり、スムーズなプロモーターエスケープにつながる。」
*
……ここで紹介したのはごく一部ですが、こんな感じにとても詳細な説明があるのです。
「2章 mRNAスプライシング」では、冒頭に……
「高等真核生物では、核内のDNA上に存在する遺伝情報が機能を持ったタンパク質として発現するまでに、非常に複雑な制御機構が存在する。ゲノムDNAから転写された一次転写産物であるmRNA前駆体は、そのままタンパク質合成の鋳型となるのではなく、イントロンの除去、キャップ構造やポリA鎖の付加、そしてRNAの編集や修飾など様々な過程を経て細胞質へと輸送され、初めてタンパク質へと翻訳される。これらの過程を総称してRNAプロセシングと呼び、高等真核生物において遺伝子発現に必須な過程であると同時に、遺伝子発現を精巧に調節する過程である。」
……という記述があり、ほとんどの章で最初に概要解説があるという理解しやすい構成になっています。
「4章 tRNAとrRNAの修飾」では……
「RNA修飾は、今なお、進化を続けている。新たな修飾を生み出す最大の駆動力は、感染性生物の存在である。すなわち、感染される宿主は自分のRNAと感染性生物のRNAを見分けるため、感染性生物は宿主の防御システムをかいくぐるために、新たなRNA修飾と修飾酵素を生み出し続けており、それらの起源の多くはtRNAやrRNAの修飾酵素であると考えられている。」
……これが進化の原動力の一つなのでしょう。
さらに「13章 CRISPRの構造と機能」以降では、CRISPRやmRNA創薬などの新技術についても詳しい解説を読むこともできました。
『RNAの科学: 時代を拓く生体分子』……RNAの全体像をかなり詳しく俯瞰できる本で、とても勉強になりました。まさに最新の「RNAの教科書」で、RNAに関わる研究を行っている場所に一冊あると、とても便利に使えそうです(かなり高価で学生さんのお財布には厳しそうなので、研究室の図書本として……)。
素晴らしい本なので、ぜひ「RNAの教科書」として定期的に改訂し続けて欲しいと思います。医学や生物学に興味のある方は、ぜひ読んでみてください。お勧めです☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『RNAの科学』