ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
ビジネス・経営
「変化を嫌う人」を動かす(ノードグレン)
『「変化を嫌う人」を動かす: 魅力的な提案が受け入れられない4つの理由』2023/2/20
ロレン・ノードグレン (著), デイヴィッド・ションタル (著), 船木 謙一 (監修), & 1 その他
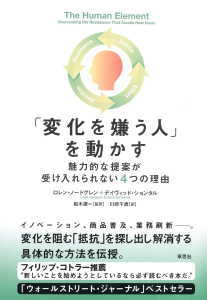
(感想)
魅力的なはずのアイデア、製品、サービスが、相手に受け入れられないのはなぜなのか? それは魅力が足りないからではなく、相手に受け入れたくない理由=「抵抗」があるから……その抵抗を4つ(惰性・労力・感情・心理的反発)に分類して、それぞれの正体を分析、さらにその対処法を、事例を使って具体的に教えてくれる本です。
タイトルの『「変化を嫌う人」を動かす』を見て、特に「変化を嫌うタイプの人」を動かすための特殊なテクニックを教えてくれるのかと勘違いしてしまいましたが、実は私たちはみんな「現状を維持したい(変化したくない)」という性質を持っていて、この本は、「一般の顧客を動かす(その気にさせる)方法」を教えてくれる本だったのでした。
さて、顧客に新しい製品やサービスを採用させる手段としては、機能やメリット、宣伝を充実させることが挙げられますが、これは「燃料」で、これだけでは、うまくいかないそうです。それは新しいものを取り入れようとする消費者の欲望を抑え込む、4つの主要な「抵抗」があるから……実はこの「抵抗」の方が「燃料」よりも重要なことが多いのですが、分かりやすい「燃料」に比べて、「抵抗」の方は見えないところに潜んでいるので、見過ごされてしまうことが多いようです。
本書はこの「抵抗」を次の4タイプに分類して分析、それぞれへの対処法を具体的に教えてくれます。
・「惰性」:自分が馴染みのあることにとどまろうとする欲求。
・「労力」:変化を実行するために必要な努力やコスト。
・「感情」:提示された変化に対する否定的感情。
・「心理的反発」:変化させられるということに対する反発。
*
「惰性を克服する方法」としては、次のものが紹介されていました。
1)アイデアに慣らす
戦略その1)何度も繰り返す
戦略その2)小さく始める
戦略その3)伝達者をオーディエンスに似せる(自分に似た人を好む)
戦略その4)提案を典型的なものに似せる
戦略その5)喩え(アナロジー)を使う
2)相対性を取り入れる
戦略その1)極端な選択肢を追加する
戦略その2)劣った選択肢に光を当てる
*
ここで驚いたのが「劣った選択肢に光を当てる」という方法。これは、欠陥のある選択肢を目立たせることで、最終的に選ばれる製品の感覚的な価値を高める方法なのですが、その事例として、Sサイズのポップコーンばかりが売れる映画館で、Lサイズを買うように仕向ける方法が紹介されていました。
それは「おとりの選択肢」を作るという方法。Sサイズ(3ドル)とLサイズ(7ドル)の中間にMサイズ(6.5ドル)の選択肢を追加したら、なんと大多数がLサイズを選ぶようになったそうです。MとLはサイズのわりに値段があまり変わらないので、Lサイズが相対的に安く感じられるようになったということですが……うーん、これだと確かに誘導されてしまいそう……。
続いて「労力」に関する分析ですが、「労力」には次の2つの側面があると指摘していました。
1)苦労
2)どうすればよいのか分からないという「茫漠感」
……この「茫漠感」もまた、見逃されがちな「抵抗」だと思います。そしてその克服法は……
「(前略)茫漠感は「ロードマップの作成」と呼ばれるプロセスで制するのに対し、苦労は「行動の簡素化」と呼ばれるプロセスで変貌させる。」
……なるほど。「ロードマップ」を見せることで、全体像や進捗状況を見せて「茫漠感」を減らしてあげるんですね☆
また「感情」についての分析でも、驚かされることが。それはみんなの「苦労」を軽減させるはずの「ケーキミックス」が新発売されたときのこと。意外にも売れ行きが悪かったようですが、その理由を調べると、なんと「あまりにも簡単すぎた」からだったそうです(!)。 ケーキは、誰かを祝うためや愛情表現のために焼くものなので、ケーキミックスの「手抜き感」が抵抗を生んでしまった……そこでケーキミックスから卵末粉をとり除いて「卵を加える」という一手間を加えるように手順を変更したら、今度は売れるようになったそうです……うーん、「感情」もまた重要な要素なんですね。
この「感情面の抵抗」に効く一般的な治療薬としては……
1)「お試し」ができるようにする
2)決めたことを簡単に覆せるようにする
3)サービス込みにする
……などの方法があるようです。
また「本当の理由」に近づくためには、行動観察者になるのが有効なのだとか。
そして最後の「心理的反発」。人間には、次のような性質があると指摘されていました。
・自由が奪われると感じると「心理的抵抗」は起きる
・人は変化を迫られるととっさに心を閉ざし、自身の信念を守ろうとする
・自身のものの見方と相反する証拠を突きつけられると、自身の信念を疑うよりも証拠を否定することのほうが多い
・「心理的反発」が発生するきっかけは自由や選択肢が実際に制限されることだけではなく、説得されていると感じるだけでも十分に「抵抗」の引き金になる。
*
そしてそれを克服させるための方法は……
「「心理的反発」を克服するための秘訣は、変化を無理強いするのをやめることだ。相手を説得しようとするのではなく、相手が自分自身を説得できるよう手助けしたほうがいい。」
……これを「自己説得」と言うようです。
そして自己説得の3つのルールとして、次のことが挙げられていました。
1)自己説得は目安箱方式では無理
(目安箱で意見を言う人は少ないうえに、こちらの意図する方向に人々を誘導できない)
2)メンバーにコミットメントを発表させる
(人前で発表すると自己説得の力は一層強くなる)
3)参加を実質を伴ったものにする
(形式的な参加ではなく、有意義な関わり方をしなければ効果はない)
*
さらに最後には、実際に「抵抗レポート」を使って分析し戦術を考察した「石油から企業への転換を成功させたドバイ」などの3つの事例も、具体的に紹介されています。この事例では、1枚の用紙を「惰性・労力・感情・心理的反発」に4分割して内容を記入した「抵抗レポート」も掲載されているので、自分で分析するときの参考にもなると思います。
『「変化を嫌う人」を動かす: 魅力的な提案が受け入れられない4つの理由』……販売や組織改善など、さまざまな分野で使える「人を動かす」テクニックを具体的に教えてくれる本で、とても参考になりました。ここで紹介した以外にも、数多くの具体的なアドバイスがあるので、販売促進活動などで困ったときに、何かヒントをみつけられると思います。みなさんも、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『「変化を嫌う人」を動かす』