ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
ビジネス・問題解決&トラブル対応
イェール大学集中講義 思考の穴(ウーキョン)
『イェール大学集中講義 思考の穴──わかっていても間違える全人類のための思考法』2023/9/13
アン・ウーキョン (著), 花塚 恵 (翻訳)
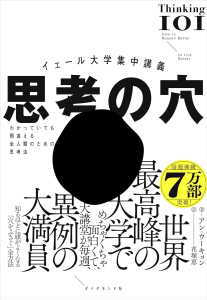
(感想)
「人間の脳」ならではの思考の罠とは? イェール大学の人気集中講義「シンキング(Thinking)」の本で、主な内容は次の通りです。
■INTRODUCTION わかっていても避けられない?
イェール大学の超人気講義「シンキング」
戦略的に「論理的思考力」を向上させる
■Chapter 1 「流暢性」の魔力──人はすぐ「これは簡単」と思ってしまう
「BTSのダンスを踊れる」と錯覚した訳
何度も見ると、なぜか「できる」と思ってしまう
「言いやすい名前」のものを高く評価してしまう……など
■Chapter 2 「確証バイアス」で思い込む──賢い人が自信満々にずれていく
「自分が正しい」と思える証拠ばかり集めてしまう
確証バイアスに気づける「クイズ」
こうすれば「思考のワナ」を破れる……など
■Chapter 3 「原因」はこれだ!──関係ないことに罪を着せてしまう
人はこの「手がかり」から原因を考える
「小さな原因から大きな結果が生まれること」がわからない
「最後に起こったこと」が原因だと思ってしまう……など
■Chapter 4 危険な「エピソード」──「こんなことがあった」の悪魔的な説得力
エビデンスより「友だちの話」に影響される
「ジンクス」が生まれるからくり
すべてのコアラが動物なら、すべての動物はコアラか?……など
■Chapter 5 「損したくない!」で間違える──「失う恐怖」から脱するには?
「得る100ドル」と「失う100ドル」の重みの違い
賢い営業マンは「喋る順番」が違う
「自分のもの」になった瞬間、惜しくなる……など
■Chapter 6 脳が勝手に「解釈」する──なぜか「そのまま」受け取れない
わかっているのに、歪めて解釈してしまう
賢いからこそ、進んでバイアスにとらわれる
事実を「自分の考え」に一致させようとする……など
■Chapter 7 「知識」は呪う──「自分が知っていること」はみんなの常識?
あなたの「皮肉」は実は全然通じていない
すべてを「自分の持っている情報」から考えてしまう
人は全然「相手の視点」から考えない……など
■Chapter 8 わかっているのに「我慢」できない──人はどうしても不合理に行動する
必死に我慢しても「衝動」に抗えない
人は「確実性の高い」ことを極端に好む
自己管理レベルが高いほど早く老化する?……など
*
「Chapter 1 「流暢性」の魔力」には、人間には「何度も見ると、なぜか「できる」と思ってしまう」傾向があることが書いてありました。そのため「何かを完了させるのに必要となる時間と労力は、少なく見積もられることが多い。」……うーん、私にもまさにその傾向があります(苦笑)。その対策としては、「タスクを「分解」すれば、現実に気づける」、「見積もりより「50パーセント」多く時間を確保する」が有効とのことで……とても実践的に役に立つアドバイスだと思います。
つづく「Chapter 2 「確証バイアス」で思い込む」では、人間は「「自分が正しい」と思える証拠ばかり集めてしまう」癖があることが書いてありました。なお「確証バイアスとは、人が「自分が信じているものの裏付けを得ようとする」傾向のことを指す。」そうです。しかも確証バイアスには「悪循環」が潜んでいて……
「暫定的な仮説を裏付ける証拠ばかり集めていると、それが正しいと確信する気持ちが極端に強くなっていき、裏付けとなる証拠をさらに集めるようになるのだ。」
……うーん、耳に痛い……。
さらに「Chapter 3 「原因」はこれだ!」では、次の文章が心に残りました。
・「問題を解決するには、むしろ問題から距離を置くほうがいい。たとえ問題の当事者が自分だけだとしても、一歩引いて他者の視点に立つことはできる。」
・「(前略)原因はこれだと100パーセント確信できることは絶対にない。」
・「この先同じ状況に遭遇することはありえないのなら、答えをひとつに絞ることは不可能なうえに無意味だ。」
*
そして、とても良いアドバイスだと感じたのは、「Chapter 6 脳が勝手に「解釈」する」の次の文章。
「バイアスのかかった解釈で誰かに迷惑をかけられたり、嫌な思いをさせられたりしたときはどうすればいいか?
そういう場合にもやはり、バイアスは人の認知につきものだと理解していれば、自分とものの見方の違う人に対して寛容になれるはずだ。相手には必ずしも悪意があるわけではなく、たんに、その人独自の視点からものを見ているだけかもしれない。
バイアスのかかった解釈をしている人に対し、毎回身構える必要はない。場合によっては、相手のものの見方を変えようとするよりも、視点の違いによって生じた問題の解決に力を注ぐほうが、簡単かつ効果的なときもある。」
……確かに。そうですよね……。
また「Chapter 7 「知識」は呪う」の次のアドバイスも。
・「実は、他者の心を理解し、自分の思いを明確に伝える能力を向上させる確実な方法がひとつある。しかも、それは簡単だ。自分の思いを他者に推測させず、素直に伝えればいい。そして皮肉を込めたジョークを文章で送るときは、明らかに皮肉な感情を表す絵文字をつけるようにする。」
・「それから、他者の思いや感情を深読みすることもやめる。」
・「結局、事実を集めることだけが、互いを理解するための確かな方法なのだ。」
*
……皮肉やジョークは、半分しか正しく伝わらないという研究結果があるようです。
『イェール大学集中講義 思考の穴──わかっていても間違える全人類のための思考法』……人間にはさまざまなタイプの「思考の穴」があり、なかには避けようのないようなものもあることを具体例で教えてくれる本でした。これらの穴を完全に防ぐ方法はありませんが、かなり実践的に役に立つ対策も教えてくれるので、トラブルの予防や回復にも役に立ちそうな気がします。みなさんも、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『イェール大学集中講義 思考の穴』