ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
脳&心理&人工知能
心は存在しない(毛内拡)
『心は存在しない 不合理な「脳」の正体を科学でひもとく (SB新書 674)』2024/11/7
毛内 拡 (著)
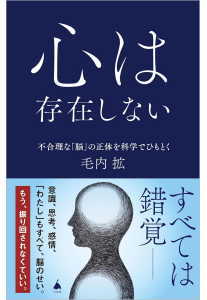
(感想)
人間独自のものと称される「こころ」とは一体何なのか? また、どこにあるのか……
だれもが「こころ」があることを前提に、「こころ」の定義や在りか、「こころ」がどうして生まれたのか、どうやって生まれたのかを議論しています。
しかし、じつは生物学的に見れば「こころ」は脳という働きの結果(副産物)であり、解釈に過ぎません。言ってしまえば、「最初からこころなんてものは存在しない」のです……という考え方から「こころ」の実情を語ってくれる本で、主な内容は次の通りです。
序章 実は心なんて存在しない?
第1章 心の定義は歴史上どう移り変わってきたのか
第2章 心はどうやって生まれるのか
第3章 心は性格なのか
第4章 心は感情なのか
第5章 脳はなぜ心を作り出したのか
終章 心は現実の窓
*
「序章 実は心なんて存在しない?」には、次のように書いてありました。
「(前略)心は身体とは切り離されて存在する、独立した別物であると捉えられがちです。場合によっては“自分”とは無関係で制御不能な、厄介な存在と諦めている人もいるかもしれません。あれ、自分っていったい何なのでしょうか?
心のはたらきには、なんとなく脳が重要だとは多くの人が感じていることでしょう。つまり、すべてはこの硬い頭蓋骨の中で起こっているのです。
実際、機能的MRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像法)と呼ばれる脳スキャン技術では、人が喜怒哀楽を感じている時には、特定の脳の部分が活性化することが示されています。またPET(Positron Emission Tomography:陽電子放出断層撮影)を用いると、脳内での血流や代謝の変化を可視化することで、脳の機能的な活動を詳細に把握することが可能となります。」
*
……『心は存在しない』という断定的な表現から、ガチな「科学第一主義」本かと思いましたが、「心の「本質」は情動による身体喚起にある」など、全体としては、ごく一般的な脳科学的な「心」の本だったように感じます。
個人的には、「第2章 心はどうやって生まれるのか」が、とても面白く読めました。
まず「認知」については……
「脳には外界の情報を取捨選択するメカニズムがあります。
このフィルターは、手足や目など末梢の感覚からの情報を、大脳皮質に送るか否かを決定すると言われています。このフィルターでほとんどの情報が弁別され、非意識的に処理されます。
特に生理的なものは、体が勝手に処理してくれています。たとえば、心拍や体温の調節、食事後に血糖値が変動するなど、これらは意識にのぼらずに自律的に行われます。
しかし、何か特別な注意を要する情報がある場合は、それが大脳皮質で照合され、意識的な「知覚」として認識されます。」
……そして危険な状況に出会ったとき、心拍が上昇したり、鳥肌が立ったりするのは……
「このような調節は、自律神経という自分の意思ではコントロールできない神経によって、さまざまな器官や臓器を同時に調節することによって実現しています。そのあとで、私たちはこのような身体の変化を認知し、「ああ怖かった」とか「緊張した」というような解釈を加えて、感情として表出するのです。
このように感情は、外界の刺激をどのように認知し、解釈するかによって形成されます。それは静止画的なものではなく、常に私たちの認知プロセス、身体的状況、そして外的環境との相互作用の中でダイナミックに変化しています。
実は、この認知のプロセスは、私たちが個々の事柄から概念を作り上げる方法と密接に関係しているのです。」
……私たちはこういう個々の経験を、「犬」などの知識や、「ヨロコビ、カナシミ」のような感情として、カテゴリーでまとめて認識しているそうです。そして……
「(前略)私たちの心=感情は、一定不変の本質を持っているわけではなく、都度ダイナミックに形成されるものです。
そう考えると、私たちが表面上の感情表現だけを根拠に、互いに理解し合うことは困難であることがわかります。感情とは、極めて主観的なものであり、しかも必ずしも言語化できるものばかりではありません。
わかり合うためには粘り強いコミュニケーションが不可欠であり、まずは互いの違いを認め、尊重し合うことが重要なのではないでしょうか。」
……また私たちは、自分の経験や記憶に基づいて形成する「知恵ブクロ記憶」を持っていて……
「この「知恵ブクロ記憶」が、身体喚起の情報をどのように解釈するかに影響を及ぼし、結果として特定の情動が引き起こされます。感情は単なる反応ではなく、過去の経験と現在の状況の間での複雑な対話の結果なのです。」
……感情は常にダイナミックに変化するものなので……
「逆に言えば、自分というものは、水のように形の定まっていないものですから、日々アップデートしていけるものです。
「自分とはこういうものだ」「私らしくない」「こうあらねばならない」などと言って、枠の中に収まらず、自分で自分に蓋をしないで、多様な自分の可能性に「チャレンジすることだってできるはずです。」
……そう考えると、「心」を作っていくのは、私たち自身の経験や感情、そして意識なのでしょう。
『心は存在しない 不合理な「脳」の正体を科学でひもとく』……私たちが「心」と感じているものは、脳と身体の相互作用で出来ていることを教えてくれる本でした。心理学や脳科学に興味のある方は、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『心は存在しない』