ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
脳&心理&人工知能
SF脳とリアル脳(櫻井武)
『SF脳とリアル脳 どこまで可能か、なぜ不可能なのか (ブルーバックス B 2281)』2024/12/26
櫻井 武 (著)
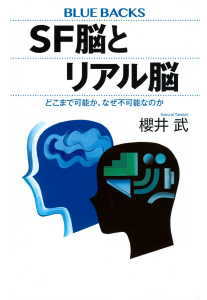
(感想)
神経科学者として、脳の覚醒にかかわるオレキシンや、「人工冬眠」を引き起こすニューロンを発見する一方で、大のSFファンでもある櫻井さんが、『二重太陽系死の呼び声』や『攻殻機動隊』など古今の名作に描かれた「SF脳」の実現性を大真面目に検証している本で、主な内容は次の通りです。
第1章 サイボーグは「超人」になれるのか(『二重太陽系死の呼び声』ニール・R・ジョーンズ)
第2章 脳は電子デバイスと融合できるか(『攻殻機動隊』士郎正宗)
第3章 意識はデータ化できるか(『順列都市』グレッグ・イーガン)
第4章 脳は人工冬眠を起こせるか(『夏への扉』ロバート・A・ハインライン)
第5章 記憶は書き換えられるか(『追憶売ります』フィリップ・K・ディック)
第6章 脳にとって時間とはなにか(『TENET/テネット』クリストファー・ノーラン監督)
第7章 脳に未知の潜在能力はあるのか(『LUCY/ルーシー』リュック・ベッソン監督)
第8章 眠らない脳はつくれるか(『ベガーズ・イン・スペイン』ナンシー・クレス)
第9章 AIは「こころ」をもつのか(『2001年宇宙の旅』スタンリー・キューブリック監督)
*
「はじめに」には、次のように書いてありました。
「本書では、古今東西のSF作品の中から脳を題材にした名作を取りあげて、その実現可能性について、考察を試みることにした。」
「本書は科学と空想を織り交ぜた、いわば脳についての思考実験といった趣きで書かれているが、「SFに描かれた脳」と比較して「リアルな脳」では、どこまでが可能で、どこから不可能なのかを知ることで、現在の科学で理解されている脳の特性を知ることができるようにしたつもりである。また、世の中に広まっている脳についての誤解や、いわゆる「都市伝説」を払拭する一助ともなることを期待している。」
……わくわくしてしまいます☆
最初の「第1章 サイボーグは「超人」になれるのか」では、『攻殻機動隊』や『銃夢』に登場するような、中枢神経系(脳と脊髄)以外をすべて人工的なものに置き換えたサイボーグについて、人間の脳がとても複雑なだけでなく、末梢神経すら一本一本が別々の機能をもって独立した情報を運んでいるので、技術的に極めて困難で、たとえ末梢神経がすべて解明されても、それを実現したメカニズムを脳が正確にコントロールできるようになるまでには、かなりの学習が必要と書いてありました。
しかも過酷な環境下での使用や、兵器としての使用する場合には、サイボーグがもつ脳の脆弱性が問題になるので、AIの方がむしろ望ましいとして……
・「AIロボットなら、ヒトが遠隔操作によって関与することが可能であることからも、次世代の「超人」はサイボーグではなく、遠隔操作された兵器や、自律型AIロボット、あるいはそれらを組み合わせたものになると思われる。」
・「近未来のサイボーグは、難しい作業用や兵器としての用途よりも、最初に紹介した障害や疾患などを治療する医療目的が重要になってくるはずである。」
……うーん、確かに、その通りですね……とても現実的な分析だと思います。
続く「第2章 脳は電子デバイスと融合できるか」では、次のような最新研究について紹介されていました。
「たとえば発声も運動の一種だが、カリフォルニア大学などによる研究チームは、皮質脳波から言葉を生成する研究を進めている。これは、発声に関わる筋肉への指令を出す脳の働きを皮質脳波から推測して、テキストを生成するという試みだ。脳卒中により構音障害と痙性四肢麻痺を患っている参加者を対象に、皮質脳波を検知する電極を脳に埋め込み、深層学習により皮質脳波から情報を抽出し、被験者が話そうとしたことをコンピュータ上のテキストデータとして表示する。」
また脳と電子デバイスの融合については……
・「(前略)生体のニューロンと電子デバイスは作動様式がまったく異なると述べたが、唯一の共通項は、作動原理として電気を使うことである。したがって、電気を使って神経系を操作する、あるいは、電気信号をもちいて脳の機能をモニターすることは、ある程度は可能なのだ。」
・「将来的には、脳深部のさまざまな場所に超微細な電極を埋め込み、それぞれを適切な強さとタイミングで制御することにより、脳のあらゆる機能を外部から適切に調整できる、いわば「ブレイン・コンディショナー」のような装置もできるかもしれない。」
・「しかし、ここまでみてきたような脳の操作は、いわば脳の「作業モード」を変えているにすぎない。気分や、睡眠・覚醒の操作はできたとしても、「情報」そのものを脳から出し入れすることは、意味合いがまったく異なる。」
……脳と電子デバイスの融合は、技術的にかなり困難なだけでなく、さまざまな危険もはらんでおり、人間のありようを根本的に変えてしまうおそれもあるようです。
そして、とても興味津々だったのが「第3章 意識はデータ化できるか」。次のように書いてありました。
・「意識を電子化できれば、そのメリットと広がる可能性は、はかりしれない。まず、電子データは正確に複製することが可能なので、同じ意識をもつ存在、つまり“自分”をいくらでも複製できることになる。分裂した自分がそれぞれ別の体験をしていたら、別の人格になってしまう気もするが、データである以上、お互いが出会ったときに意識を共有できる。すると、一人だけで生きるよりもはるかに多くの情報が短時間で獲得でき、密度の高い人生を送ることができる。」
……例えば、電波などの光子の信号として意識データを遠方にも正確に送信できるので、宇宙旅行が可能になる他、偉人や天才の意識も保存可能。さらにデータは劣化しないので老化することも認知症の心配もなく、半永久的に生きることも可能。ただしこれも、実現はきわめて困難なようです。そして……
・「(前略)脳の情報処理システムとしての特性は、コンピュータのそれとは大きく異なっている。たとえばコンピュータは、その情報処理速度を生かして大量のデータから最適解を探し出すことを得意とするのに比べ、ヒトの脳は、直感的にものごとを判断している。したがって、ある特定の対象に注意を向けるという意味でも「意識」が必要なのだ。また、何かを判断するにも、「情動」や「気分」というものが大きく影響する。しかも、「無意識」という得体の知れないものの影響を強く受けている。このようなものを模倣しようとすることは、きわめて困難な試みになるであろうことは想像に難くない。」
・「脳は運動系を介して体を動かしているだけではなく、運動系からのフィードバックも受けている。また、脳は自律神経系や内分泌系を介して全身の機能を制御しているが、脳や精神の機能も、自律神経系や内分泌系からきわめて大きな影響を受けている。」
・「だから、生体の機能を完全に模倣できる機械をつくるには、このような身体の変化までシミュレートして、それがどう精神活動に影響を与えるかを演算することも必要になってくる。」
・「実際に、生きている脳も、身体から切り離されると覚醒状態や意識を失い、ノンレム睡眠に似た状態になる。覚醒の維持には、脳幹を中心とした下位構造から大脳皮質に向けての絶え間ないインプットが必要なのだ。」
・「(前略)生きた脳を完全に模倣するには、ある時間の状態だけではなく、経時的変化も加味する必要がある。細胞内各分子は、つねに転写・翻訳・分解されているし、分解されるまでの速さはそれぞれ異なっているからだ。」
*
さらに「第5章 記憶は書き換えられるか」では……
「(前略)海馬には明確なメモリー・エングラムがあり、それを完全に解析する技術や神経回路を書き換える技術が開発できれば、成立した初期の記憶に改変を加えることはできるかもしれない。しかし成立から長時間を経た記憶は、大脳皮質に広範に分散して、ホログラムのように想い出が蓄えられていると考えられる。だとしたら、それに関係するニューロンを解析したり、改変したりすることは、もはや不可能に近いだろう。」
*
『SF脳とリアル脳 どこまで可能か、なぜ不可能なのか』……有名なSF作品を通して、脳の本質を科学的に深く考察している本で、とても面白く、また勉強にもなりました。みなさんも、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『SF脳とリアル脳』