ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
脳&心理&人工知能
UXデザインの法則 第2版(Yablonski)
『UXデザインの法則 第2版 ―最高のプロダクトとサービスを支える心理学』2025/1/29
Jon Yablonski (著), 相島 雅樹 (翻訳), 磯谷 拓也 (翻訳), 反中 望 (翻訳), & 1 その他
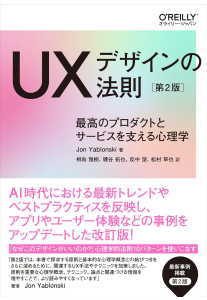
(感想)
「意思決定にかかる時間は、とりうる選択肢の数と複雑さで決まる」、「タッチターゲットに至るまでの時間は、ターゲットの大きさと近さで決まる」など、UXデザインと交差する心理学の法則について解説してくれる本で、著者のJon YablonskiさんがUXデザインと交差する心理学の法則をまとめたウェブサイト「Laws of UX」を元に構成されているそうです。本書で解説してもらえるのは、次の10法則です。
第1章 ヤコブの法則
(ユーザーは他のサイトで多くの時間を費やしているので、あなたのサイトにもそれらと同じ挙動をするように期待している)
第2章 フィッツの法則
(ターゲットに至るまでの時間は、ターゲットの大きさと近さで決まる)
第3章 ミラーの法則
(普通の人が短期記憶に保持できるのは、7(±2)個まで)
第4章 ヒックの法則
(意思決定にかかる時間は、とりうる選択肢の数と複雑さで決まる)
第5章 ポステルの法則
(出力は厳密に、入力は寛容に)
第6章 ピークエンドの法則
(経験についての評価は、全体の総和や平均ではなく、ピーク時と終了時にどう感じたかで決まる
第7章 美的ユーザビリティ効果
(見た目が美しいデザインはより使いやすいと感じられる)
第8章 フォン・レストルフ効果
(似たものが並んでいると、その中で他とは異なるものが記憶に残りやすい)
第9章 テスラ―の法則
(どんなシステムにも、それ以上減らすことのできない複雑さがある。複雑性保存の法則ともいう)
第10章 ドハティのしきい値
(応答が0.4秒以内のとき、コンピューターとユーザーの双方が最も生産的になる)
*
この他に、「第11章 心理学的な原則をデザインに適用する」、「第12章 力には責任が伴う」などがあります。
さてUXデザインとは、ユーザーエクスペリエンス・デザインのことで、本書は「ユーザーをプロダクトや体験に合わせるのではなく、プロダクトや体験をユーザーに合わせてデザインするための手引きとして、心理学から重要な原理を活用する」人間中心の設計法について教えてくれます。
例えば「第1章 ヤコブの法則」では、冒頭に次のようなポイントがまとめて書いてありました。
(ポイント)
1)慣れ親しんだプロダクトと見た目が似ていれば、同じように働くことを期待する
2)すでにあるメンタルモデルを活かせば、ユーザーは新たなメンタルモデルの学習なしにタスクに集中でき、ユーザー体験の質が高まる
3)変更時に生じるメンタルモデルの不一致を最小限にとどめるには、慣れ親しんだバージョンを使い続けられる移行期間を設けよう
*
ユーザーには他のウェブサイトでの経験の積み重ねを通じて「デザインはこうあるべき」という期待を築き上げる傾向があるそうです。……確かに、そうですね。初めて訪れるサイトでも、よく見に行くサイトと同じような構成になっていると、ストレスなく使い始められます。この章の結論には、次のようなアドバイスがありました。
「ヤコブの法則からわたしが助言できることとしては、まずは常にありふれたパターンや慣習から始め、その後、うまくいきそうなときだけ慣例から離れるのが良い、ということだ。(中略)
慣例から逃れた道を進むのであれば、デザインをユーザーテストにかけて、ふるまいがユーザーに理解されるかを確かめよう。」
……とても良いアドバイスだと思います。
また「第2章 フィッツの法則」では……
「ユーザビリティは、良いデザインであるための要だ。使いやすいということは、つまり、そのインターフェースがユーザーにとって一目瞭然でなければならない。」
そして「第3章 ミラーの法則」では……
「(前略)チャンク化によって、ユーザーが情報の関係性や階層関係を理解しやすくなる。」
「第4章 ヒックの法則」では……
「(前略)わたしは、ユーザーの目的達成に役に立たない要素を減らし取り除くプロセスが、デザインにおいて何より重要だと感じている。目的達成について考えなくてすむほうが、ユーザーが目的達成する可能性は高くなる。」
最後の「第10章 ドハティのしきい値」では……
・「ユーザーの注意を目の前のタスクに引きつけておけるのは10秒が限界とされる。」
・「(前略)適切なフィードバックを提供し、体感性能を高め、プログレスバーを利用することで「待っている」という感覚を全体として減らすことが重要だ。」
……など、とても参考になるアドバイスをたくさん読むことが出来ました。
さらに「第12章 力には責任が伴う」では、アメリカの心理学者のスキナーが、タイミングがころころ変わるランダムな強化こそが、最も効果的に行動に影響を与える方法であることを実証したことを受けて、デジタルプラットフォームも、「変動報酬」を利用して行動を形作ることができると言っています。
「ソーシャルメディアプラットフォームは、機械学習アルゴリズムを頻繁に利用し、予測リコメンデーションを通じて体験をパーソナライズする。これは、データを収集すると同時に、その結果によって自己改善し、ランダムな強化フィードバックループを生み出すことで実現されている。プラットフォーム上のコンテンツとのインタラクションに費やす時間が増えれば増えるほど、アルゴリズムの質は向上し、その結果、プラットフォームでの滞在時間は長くなり、データ収集量、そして広告閲覧数も増える。」
……このような変動報酬を通じて、デジタルプラットフォームが私たちの行動を誘導・操作しているのかもしれないと思うと、ちょっと恐ろしいような気がします(実際に、スロットマシンなどのギャンブル・システムは、それを狙って作り込まれているようです)。この章には、続けて次のようにも書いてありました。
・「デザインプロセスには倫理が組み込まれていなければならない。このチェックアンドバランスがなければ、テクノロジーを生み出す企業や組織の中でエンドユーザーを擁護する人がいなくなる可能性がある。(中略)
倫理的なデザインの意思決定を行うにはまず、人の心はいかにして搾取されうるのかを知ることから始めよう。そしてわたしたちが一翼を担っているテクノロジーに対して説明責任を持たなければならないし、それが人々の時間や集中力、あるいはデジタル上のウェルビーイング全体を守らなければならない。」
・「テクノロジーは人々の生活に重大な影響を及ぼす力を持っている。だからこそ、その影響を確実にポジティブなものにすることが極めて重要だ。ユーザーの目標達成とウェルビーイングに寄り添って、支援するプロダクトや体験を生み出すことは、わたしたちの責任なのだ。人の心は悪用されうるものだ、ということを認めることによって倫理的なデザインの意思決定を行える。」
*
『UXデザインの法則 第2版 ―最高のプロダクトとサービスを支える心理学』……UXデザインと交差する心理学の法則を教えてくれる本でした。
「第2版では、本書で探求する原則を基本的な心理学概念とより深く結びつけるために、関連するUX手法やテクニックを補足しました。読者の理解を深めるために、これらの原則を重要な心理学概念、テクニック、論点に結びつける情報を盛り込んでいます」だそうです。
また「本書は網羅的な資料を目指したものではなく、むしろデザインと交差する心理学の実践的なガイドを目指しました。もっと網羅的に知りたい人は、ぜひウェブサイトも訪れてください。」とのことで、ウェブサイトでは、目標勾配効果、オッカムの剃刀、パレートの法則、パーキンソンの法則なども紹介されているそうです。
本書で紹介されている心理学の法則は、ウェブデザインだけでなく、さまざまな場面で活用可能なように感じました。みなさんも、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『UXデザインの法則 第2版』