ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
IT
世界最凶のスパイウェア・ペガサス(リシャール)
『世界最凶のスパイウェア・ペガサス』2025/1/22
ローラン・リシャール (著), サンドリーヌ・リゴー (著), 江口 泰子 (翻訳)
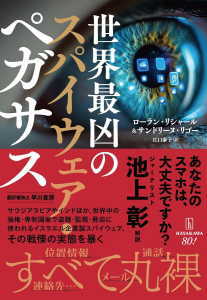
(感想)
世界中の強権・専制国家で盗聴・監視・脅迫に使われるイスラエル企業(NSO)製スパイウェア「ペガサス」が、通話・メール・連絡先・位置情報のすべてを丸裸する、その戦慄の実態を暴いている本です。
「イントロダクション」には、次のように書いてありました。
・「(前略)NSOが誇るサイバー監視ソフトウェア「ペガサス」は、まったく何の規制も受けないまま恐ろしい機能を発揮し、顧客にとって危険な魅力を放ち、NSOには莫大な利益(二〇二〇年の売上げは約二億五〇〇〇万ドル)をもたらしていたからだ。不正アクセスに成功すれば、基本的に相手のスマートフォンを乗っ取ることになる。暗号化を含むセキュリティを破って相手のスマートフォンに不正侵入し、スパイウェアの存在を知られることなく、端末をほぼ意のままにできる。スマートフォンを使って送受信したあらゆるテキスト、通話内容、位置情報、写真、動画、メモ、閲覧履歴だけではない。ユーザーに感づかれることなく、カメラとマイクロフォンも起動できる。ボタンを押すだけで、遠隔操作による完璧な個人監視が可能になるのだ。」
・「(前略)一般市民が、彼らの意に反し、あずかり知らないところで、何の手立てもなく、軍用グレードの監視兵器の標的にされている。この脅威を理解せず、阻止するための行動を起こさなければ、私たちは本当にディストピア的な未来に突き進んでしまうことになる。」
・「本書が語るナラティブの原動力は、彼らが二〇二〇年後半に初めて流出データにアクセスした瞬間から二〇二一年七月に報道するまでの、危険に満ちた調査そのものである。」
*
このスパイウェアが世界各地のジャーナリストや人権活動家、政治家などを標的にした違法な監視活動に使われていることを暴いたのが、世界10カ国、17報道機関、80人以上のジャーナリストによる「ペガサス・プロジェクト」。
サウジアラビアのジャーナリスト・カショギ氏の殺害をはじめ、世界各地で独裁者や専制主義国家による市民の弾圧や批判者の封じ込めにペガサスが使われてきた実態を、各国の記者やエンジニアが連携しながら突き止め、ついに世界に公開するまでを記した迫真のルポでした。
「解説」には、次のようにありました。
・「本書の執筆者二人は「フォービドゥン・ストーリーズ」(禁じられた物語)というNPO(非営利組織)の調査報道機関のジャーナリストです。「禁じられた物語」とは、犯罪者集団や独裁国家の体制を暴く仕事をしていたジャーナリストが、殺害されたり逮捕されたりして中断された仕事を引き継ごうという集団の名称です。」
・「イスラエルの民間企業NSO(創業者たちの名前の頭文字を並べたもの)は、強力なサイバー監視ソフト「ペガサス」を開発し、世界四〇カ国を超える「法執行機関と国家安全保障機関」に販売。莫大な利益をあげてきました。
しかし、販売先には権威主義的な(要するに独裁的な)国家が含まれていますし、NSOが「供給していない」と言っている国の情報機関が、反政府活動家やジャーナリストの取り締りに悪用している可能性があります。」
*
本書は、勇敢な情報提供者によって、フランスのジャーナリストなどにもたらされた流出データ(ペガサスの標的となった五万件のスマートフォン電話番号など)を端緒に、その信憑性の調査や、サイバー監視の痕跡を見つけ出したことなどを、とても具体的に描き出しています。ペガサスの能力の高さ(まさに軍事兵器レベル!)に戦慄せずにはいられませんでした。
ジャーナリストやセキュリティ専門家たちが、標的となったスマートフォンのフォレンジック分析を行う一方、事態を察知したペガサス(NSO)側も次々と対策を打ってきて……緊迫の展開が続きます。
その劇的な結末については、「解説」に次のような簡潔なまとめがありました。
「著者らの集積した情報にもとづき、二〇二一年七月一八日の日曜日の夜、一〇カ国一七の報道機関が一斉に報道を開始します。NSOは報道内容を全面否定しますが、NSOに投資してきた各社は手を引き、大統領が盗聴されていたことに衝撃を受けたフランス政府が捜査を始めると、NSOは万事休す。結局、姿を消すことになりました。
この時点で、著者らの努力は実りましたが、反体制派やジャーナリストの動向をスパイしたいと考える独裁政権は多数存在します。需要あれば供給あり。NSOの後を継ぐ組織はいくらでも生まれます。」
また「エピローグ」でも……
「NSOの崩壊は、軍用グレードのサイバー兵器の現在と将来の密売業者にとって教訓となった。そのいっぽう、ジョージ・オーウェルが描いたような、市民生活にサイバー監視が組み込まれた世界の到来を阻止したいと願う、スパイウェアに批判的な人間や人権活動家にも警鐘を鳴らした。NSOは活動不能に追い込まれたかもしれない。だが、NSOが設計したテクノロジーは生き延びた。プライバシーの保護、表現の自由、報道の自由という問題を提起したかもしれない。だが、解決策は見つかってもいない。」
*
今回はジャーナリストたちの必死の努力が実を結び、NSOは崩壊に導かれましたが、これを単純に「めでたしめでたし」と喜んでいいものかどうか判断に苦しみました。
とても気になるのが、崩壊したNSOの組織や優秀な技能のある社員たちは、その後どうなったのかということ。イスラエル警察や軍などの「法執行機関と国家安全保障機関」に全員再就職できたなら、むしろ安心なのですが、もしも犯罪組織などにリクルートされていたら……さらに恐ろしい事態が起きてしまうかもしれません……。
このようなサイバー監視会社(組織)には、他にもいろいろな問題があるようでした。
一つは自分たちのサイバー監視システムが悪用されて、権力者にとって不都合なジャーナリストや一般人が暗殺されることが実際に起きたこと(社員は精神的に追い詰められる)。これに関してNSOは次のように言って社員の士気を高めているようです。
「NSOは言う。我が社が開発し、四〇カ国を超える国家の六〇を超えるクライアントのために、頻繁にアップデートし、アップグレードしてきたサイバー監視システムは、世界をより安全にしてきました。これまで何万もの人命を救ってきました。なぜなら、テロリスト、犯罪者、小児性愛者(中略)を監視し、彼らが行動を起こす前に犯罪を阻止できるからです、と。」
そして二つ目は、サイバー監視を運用する側に生まれる微妙な心理。ペガサスの運用ターミナルで働いた経験のある人は、次のように話しています。
「(前略)他人の生活を覗き見することには、ある種の病的な好奇心が働くのです……。あの種のツールは、手元にそのツールをもつ(公僕という)者のなかに、優越感や権力感、支配感を生み出します。そして、ペガサスの使用目的が倒錯してしまうのです。つまり、公共の利益のためではなく、個人的な満足感を得る手段になってしまうおそれがあるのです。」
……いろいろな意味で誘惑にさらされやすいサイバー監視者が、監視能力を濫用することなく、常に正義の側にい続けることができるよう、「監視者も監視される」仕組みを作るべきなのではないでしょうか。
また自分がサイバー監視をされていたことを知らされたジャーナリストたちは、次のように反応したそうです。
「最初はある意味、否定する。次に理解し始める。そして、惨めな思いをする――堪え難いほどの罪悪感に苛まれるからだ。まず心配するのは自分のことじゃない。迷惑をかけてしまった相手のことだ。誰の端末を感染させてしまったのか。自分のせいで、誰を危険に曝してしまったのか。彼らはみな個人的に受け止め、自分を責める。『ああ、悪いことをしてしまった』というふうに」
……サイバー監視は、される側・する側の両方を精神的に追い詰めていくような気がします。
でもこのようなサイバー監視を完全に防ぎきる方法はなく、「どんなデバイスもハッキング被害に遭うという前提で運用する」しかないようです。
重要なのは、「運用レベルで、どうすれば被害を最小限にとどめられるか」で、たとえば、「重要な関係者とは、特定の場所で会い、他の場所では会わないようにする」とか、「スマートフォンは持たないか、重要な件では使わない。重大な時には持ち歩かないか、電話番号を誰にも知られないようにする」とか、「ラップトップを個人的なことに使わない」とか……なかなか難しいことですね……でも気をつけていかなければ……。
そして最も重要なことだと感じたのが、権力者の問題を明らかにするジャーナリストを守ること。
「イントロダクション」には、次のように書いてありました。
「世界のあちこちで反民主主義と権威主義の風が勢いを増すなか、法の支配を躍起になって排除しようとする勢力に対して、法の支配がさほど力を発揮しないことが、ますます明白になりつつある。(中略)もちろん、法律も時には役に立つ。だが、脅威はたいてい法を回避し、その裏を掻き、巧みにしのぐため、私たちには別の種類の保護が必要になる。権力者の汚職、金銭ずくの買収、縁故主義、無法状態、残忍行為の事実をつまびらかにするのはいつの時代もジャーナリストたちの任務である。」
そして「第一七章」では、あるジャーナリストが次のように言っています。
「それらの政権が必要とするのは沈黙です(中略)沈黙すれば、彼らは国民から機会を奪いやすくなります。権力とカネ、犯罪と政府ががっちりと手を組み、司法制度が機能不全に陥ると、独立系ジャーナリストがおもな標的になります。なぜなら、社会が腐敗や組織犯罪に抵抗する唯一の手段が、独立系ジャーナリストだけになるからです。」
*
『世界最凶のスパイウェア・ペガサス』……イスラエル企業製スパイウェアの実体を詳細に描いていて、恐ろしさに戦慄せずにいられませんでした。このような軍用兵器レベルのサイバー監視システムに対抗する手立てを何も思いつかない以上、このようなシステムは、「法執行機関と国家安全保障機関」だけが使用できるように厳格に制限して欲しいと願わずにいられません。
いろいろなことを考えさせられる本でした。新しい社会をどう生き抜いていくか……いつも臨機応変に対応し続けられるよう、自らの能力を高め続けていかなければならないのでしょう。
みなさんも、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『世界最凶のスパイウェア・ペガサス』