ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
健康&エクササイズ
病気の仕組みと予防の正解(峰宗太郎)
『病理医が切実に伝えたい 病気の仕組みと予防の正解』2024/6/20
峰 宗太郎 (著)
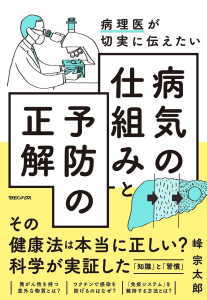
(感想)
病理医として病気で亡くなった方々を200例以上解剖してきた峰さんが、「手遅れになってしまう前にもっとできることは、たくさんあったかもしれないのに……」という切実な思いから「健康を自分で守る」術を教えてくれる本で、主な内容は次の通りです。
1章◎日本人の2人に1人がかかる いちばん身近な「がん」の話
2章◎今だからこそ伝えたい「感染症」の歴史と予防法
3章◎ちょっとした不調、そして慢性の病気とどう付き合う?
4章◎科学が実証した「病気にならない習慣」
5章◎後悔しない「情報の集め方」と「医療への頼り方」
巻末付録◎超厳選! おすすめブックリスト
*
「1章◎日本人の2人に1人がかかる いちばん身近な「がん」の話」では……
「(前略)細胞の分裂(=増殖、つまり増えること)と細胞の死んでいくバランスが崩れ、ある場所で細胞が増えて塊になったものが「腫瘍」というわけです。」
……などの「がん」についての知識や、代表的ながん治療の「三大療法(外科手術、化学療法(抗がん剤治療)、放射線治療)」の他、新しい治療法として、「免疫チェックポイント阻害薬」、「CAR-T療法」などの自分の免疫を利用した治療法や、「光免疫療法」というがん細胞(組織)だけを壊す方法などが紹介されていました。
タバコや大量の飲酒は、がんや他の病気のリスクも高めるそうです(そうなんだ……)。
ここでは、「ガン」とカタカナで書かれている本や報道は無視していいというアドバイスもありました。実は、「悪性腫瘍の総称が「がん」で、その中でも特に上皮組織由来のものを「癌」と表記する」ことになっているそうです。……これは知らなかったので驚きました。私自身も時々「ガン」と書いてしまっていますが、それは「がん」という平仮名を文章の中に入れると読みにくくなることが多いから、という理由も大きいと思います。医学的には正しくない表記だったんですね……。でも……ガンと書いてあるものは医学業界のものではないから無視していいと言うのは、ちょっと言い過ぎのような気もします……。
えーと……とても参考になったのが「3章◎ちょっとした不調、そして慢性の病気とどう付き合う?」。次のようなことが書いてありました。
・「(前略)定期検診で出た数値などに問題があったら、医師の判断に従うことは当然ですが、軽微といわれた場合にはまずは生活習慣を見直して一次予防に取り組みます。」
・「(前略)「生活習慣病」を予防すれば、命に関わる重大な疾病の多くが予防できる。」
・「(前略)私たちの体にある臓器は、血液が常に適切に流れていることがとても大事です。血管が破れたり詰まったりすると、命に関わる大問題になります。」
……まったくその通りですね!
ちなみに、よく「血液ドロドロ」なんて言いますが、高脂血症でも、血液はサラサラと流れてはいるそうです。次のように書いてありました。
「(前略)高脂血症になると、血管壁に脂がこびりつき、それが酸化することによって血管の内皮が傷つきます。すると、マクロファージという物質がやってきて、酸化した脂を取り込んで死にます。この「脂を取り込んだマクロファージの死骸」は、最初はベチャベチャの物質なのですが、しだいにカチカチに硬くなって血管壁にプラークと呼ばれるこぶをつくります。これが高脂血症から起こる動脈硬化です。」
……うわー……ぜひとも予防したいです……。
またここでは、副作用のない薬はないと断言してありました。薬は体に作用するので、良い効果なら「薬効」、悪い効果なら「毒」になるそうです。だから「副作用なし」と謳うサプリや治療は、たいてい「効果なし」と同じ意味なのだとか(苦笑……確かに……)。
薬との付き合い方は、次のようにすべきだそうです。
「(前略)投薬治療のリスクとベネフィットを天秤にかけ、医師と相談して治療方針を決めていくとよいでしょう。」
……これも納得のアドバイスだと思います。
また家族が高齢になるとともに、認知症のリスクも増えていくわけですが……
「(前略)頑固になった程度の話ではなく、被害妄想や誇大妄想に見える言動や異常行動が見えたら、やはり、すぐに専門家の手を借りてください。(中略)
家族のことだからと抱え込んで共倒れになる前に、しかるべき医師、行政に頼ってください。これは冷たいことでも無責任なことでもありません。お互いにとって最善の選択をしていくために必要な行動なのです。いかにヘルプを求めることができず、遅きに失する人が多いかを思うと、早め早めの対応の重要性は、いくら強調してもしすぎることはありません。」
……これは本当にそうだと思います。家族は「長期的に支え合っていける」のが大事で、支える側が疲労やストレスで倒れてしまったら、誰も幸せになれません……。
続く「4章◎科学が実証した「病気にならない習慣」」では……
・「(前略)食物繊維に富む野菜を食べる。運動習慣を持つ。そして水分もマメに補給する。「食を断つ」よりも、このように「賢く食べる」「生活習慣を整える」ということのほうが重要です。」
・「ストレス解消は睡眠と運動をメインに食事をサブに位置づけるぐらいがおすすめ」
……などのアドバイスがありました(もちろん本文ではもっと詳しい解説があります)。
食事では、厚生労働省が出している「食事バランスガイド」も参考になるそうです。
そして「5章◎後悔しない「情報の集め方」と「医療への頼り方」」では、医者を見極めるチェックポイントや、受診したときに医師に聞くことなど、実践的に役に立ちそうな情報をたくさん読むことが出来ました。
自分の病気について、学会が定めた診療ガイドラインや、標準医療がどんなものなのか情報収集することも勧められています。……これもとても大事なことですね!
なおサプリや代替医療や統合医療については、厚労省の事業でつくられているサイト「eJIM」も参考になりそうです。
さらに「巻末付録◎超厳選! おすすめブックリスト」もあり、ここで紹介されている本も読んでみたくなりました。
『病理医が切実に伝えたい 病気の仕組みと予防の正解』……まさにタイトル通りの本で、とても参考になりました。みなさんも、ぜひ読んでみてください☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『病気の仕組みと予防の正解』