ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
生物・進化
マダニの科学(白藤梨可)
『マダニの科学: 知っておきたい感染症媒介者の生物学』2024/10/31
白藤 梨可 (著, 編集), 八田 岳士 (著, 編集), 中尾 亮 (著, 編集), & 1 その他
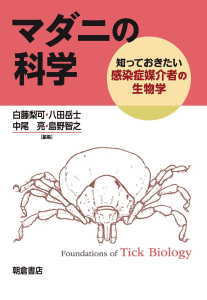
(感想)
マダニの生態・生理・生物学のおもしろさも通して、マダニとマダニ媒介性感染症について総合的な情報を教えてくれる「マダニ学」の専門書で、主な内容は次の通りです。
第1章 Q&A
第2章 分 類
2.1 概 要
2.2 マダニ目の分類
2.3 日本産マダニ種の特徴
第3章 形態と生理・生化学
3.1 形 態
3.2 感覚器
3.3 フェロモン
3.4 神経系
3.5 呼吸器系
3.6 吸血生理
3.7 血液消化
3.8 排泄・体内水分調節
3.9 循環系
3.10 脂肪体
3.11 生殖器
3.12 卵形成・産卵・胚発生
3.13 共生菌
第4章 生活史
4.1 生活史
4.2 宿主探索と吸血行動
4.3 ホルモンによる脱皮・卵形成の制御
4.4 繁 殖
4.5 休眠・越冬
4.6 季節消長
4.7 寿 命
第5章 マダニによる被害
5.1 直接的な被害
5.2 間接的な被害
5.3 マダニ媒介性病原体
5.4 微生物に対するマダニの免疫応答
第6章 マダニ刺症とマダニ媒介性感染症の対策
6.1 医学におけるマダニ刺症患者の診療
6.2 獣医学におけるマダニ対策法とマダニ媒介性感染症への対応
6.3 海外でのマダニ対策と殺ダニ剤抵抗性の問題
第7章 マダニ研究の現状
7.1 ゲノム・ミトゲノム
7.2 採集法・飼育法・実験法
7.3 国内外におけるマダニ研究動向
付録 マダニ分類表
*
個人的に昆虫は特に苦手ではありませんが、蚊やマダニのように吸血する生物は大嫌いで、できれば絶滅して欲しいとすら思っています。それでもこの本を読んだのは、「嫌いだからこそ対策したいから」。この本には冒頭からマダニのカラー写真がありますので、昆虫などが苦手な人には、かなり厳しい本だと思います……。
さて第1章は、初学者にも分かりやすいようQA形式で、みんなが抱く疑問に答えてくれます。例えば……
Q 血液を吸っているマダニが簡単に取れないのはなぜ?
A セメント物質という固まる性質の唾液成分を分泌するからです。
……などのように簡潔に疑問に答えてくれるのです。……ぐ、ぐえー……簡単には取れないようですが、吸血が終われば落ちるようです。本文には次のようにも書いてありました。
「(前略)興味深いことに飽血に至ったマダニは、少量の唾液を分泌することで、宿主皮膚に強固に接着しているセメント物質から自身の口器を抜去し脱落する。」
……そして先ほど私は、マダニを昆虫のように書いてしまいましたが、実はマダニは昆虫ではないようです。マダニの体は昆虫とは異なって頭・胸・腹の区別がなく、顎体部、胴体部、歩脚からなり、未吸血時は扁平なのだとか。ちなみにマダニは大型で、未吸血でも2mm以上ある(肉眼ではっきり認識できる)そうです。
しかも、けっこう変わった生き物のようです、次のようにも書いてありました。
・「マダニには独立した「脳」がない。マダニの胴体部前方に神経節が融合した「塊」が存在しており、中枢神経系全体を表す単一の構造をしている(総神経球、synganglion)。この器官は、マダニの生存、繁殖、発育に不可欠な生理的プロセスの神経統合を行う主要な部位である。
マダニを解剖すると黒色の中腸のすぐ上に総神経球が見える。これは、食道が総神経球を貫通しているため、総神経球と中腸があたかも連結しているかのように見えているだけである。」
・「マダニの循環系はほかの節足動物と同様、開放血管系であり、脊椎動物のように血液、リンパ液、組織液の区別がないため、体液を血リンパという。血リンパの循環は心臓、大動脈、短い動脈管などによって支えられている。血リンパは栄養分と窒素系老廃物の輸送を担っており、また、体内水分調節、微生物に対する免疫応答においても重要であるが、ガス交換は行わない。」
*
そして私がこの本で一番知りたかったのは、防御対策と治療について。「第6章 マダニ刺症とマダニ媒介性感染症の対策」によると、多くのマダニの活動が活発になるのは春から夏(特に5~7月)で、温暖な地域ではさらに晩秋~早春にも活動が活発になるようです。生息しているのは、雑木林の下草や笹薮、林縁部の畑や河川敷の草地なのだとか。
そして病原体の媒介については……
・「マダニはウイルスやリケッチアなど、各種の病原体を保有する可能性はあるが、通常、病原体保有率はきわめて低い。したがって、マダニ刺症に伴う感染症の発症について過剰な心配は不要であるが、マダニの吸血に伴って、注入される唾液腺物質に対するアレルギー性の炎症反応や、口器に対する異物反応などを生じる可能性を考慮すれば、早めに虫体を除去するのが望ましい。」
・「マダニは北海道や本州中部山地ではボレリア感染症のライム病、西日本ではリケッチア感染症の日本紅斑熱やウイルス感染症の重症熱性血小板減少症候群(SFTS)などを媒介する可能性がある(夏秋、2019)。そのため、マダニ除去後1~2週間は念のために発熱や皮疹、消化器症状などの出現に注意する必要がある。」
*
……皮膚に寄生しているマダニを除去するには、先端の尖ったピンセットでマダニの顎体基部を挟んでゆっくり引き抜くのが良いようで、最も確実な方法は、局所麻酔をして皮膚ごとマダニを切除することなのだとか。
またダニ媒介脳炎ウイルスにはワクチンがありますが、その他のウイルスにはワクチンも特効薬もないので、刺されないよう気をつけた方が良いようです。
予防としては……
「マダニ刺症を予防するためには、野外活動の際に肌の露出を避けるように長袖、長ズボンなどの衣類を着用すること、マダニの多いけもの道や繁みの中にむやみに入らないこと、草むらや笹薮に入った後はマダニが衣類に付着していないか確認することなどがポイントとなる。そして最も有効なのは、虫除け剤の適切な使用である。」
ペットの場合も、マダニの生息する山に連れていかない(散歩させない)ことが確実な予防方法のようです。
マダニには刺されても気づかないことが多いようなので、登山の時などは繁みなどを避けて歩くべきなのでしょう。
『マダニの科学: 知っておきたい感染症媒介者の生物学』……マダニについて総合的に教えてくれる専門書でした。興味がある方は、ぜひ読んでみてください。
* * *
この本には姉妹編の『ハダニの科学』もあります。
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『マダニの科学』
『ハダニの科学』