ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
数学・統計・物理
私たちの生活をガラッと変えた物理学の10の日(クレッグ)
『私たちの生活をガラッと変えた物理学の10の日』2023/8/2
ブライアン・クレッグ (著), 東郷 えりか (翻訳)
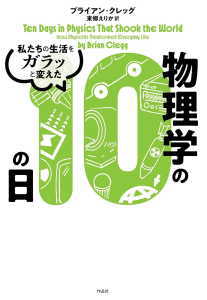
(感想)
私たちの日常生活を劇的に変えた物理の歴史の中の「10の日」をピックアップ。そこで起こった出来事と、もたらしたものを紹介してくれる物理学の歴史の本で、内容は次の通りです。
1日目 1687年7月5日 ニュートン『プリンキピア』刊行
2日目 1831年11月24日 ファラデー「電気の実証的研究」発表
3日目 1850年2月18日 クラウジウス「熱の動力について」発表
4日目 1861年3月11日 マクスウェル「物理的力線について」発表
5日目 1898年12月26日 キュリー「強い放射性をもつ新しい物質について」発表
6日目 1905年11月21日 アインシュタイン「物体の慣性はそのエネルギー含量によるのか?」発表
7日目 1911年4月8日 超伝導の発見
8日目 1947年12月16日 実用的なトランジスターの最初の実演
9日目 1962年 8月8日 発光ダイオードの特許出願
10日目 1969年10月1日 インターネットの最初のリンクの開始
11日目 ?
*
タイトルが『私たちの生活をガラッと変えた物理学の10の日』だったので、有名な物理学の概念についての「物理学的解説」をしてくれる本と勘違いしてしまったのですが、実際には「物理の歴史」や「著名な物理学者の伝記」的な内容だったので、物理学が苦手な方にとっても読みやすいと思います。
訳者あとがきにも、次のように書いてありました。
「(前略)本書は物理のなかでも馴染みのある技術として応用されているものだけを厳選して、その構想がどうやって生まれ、どういう過程を経て実用化されたかをたどる物理学史の本だ。」
……物理が好きな方にとっては、有名な概念や発明がどのように生み出されたかを知ることができて興味深いと思いますし、物理が苦手な方にとっては、物理の歴史的経緯を知ることで、苦手を克服するきっかけをつかめるかもしれないと思います。
さて「私たちの生活をガラッと変えた10の日」の1日目は、ニュートンさんの『プリンキピア』が刊行された日。冒頭には次のように書いてありました。
「ニュートンの輝かしい業績である『自然哲学の数学的諸原理(プリンキピア)』――一般には言いやすくするために『プリンキピア』の通称で知られる――が刊行されたとき、現代の意味による、数学を利用した物理学が誕生した。ニュートンの運動の3法則と万有引力の法則を盛り込み、微積分学という新たに必須のものとなった数学的手段を使って展開した『プリンキピア』は、力を運動に結びつける機械的原理を定めたものだ。そこからジェット・エンジンや航空機の翼の働きを裏づける法則が打ち立てられ、天気予報からGPS(全地球測位システム)まで、あらゆるものを提供する人工衛星を利用するのに必要な引力の計算方法が与えられた。」
……そして、この頃はどんな時代だったかとか、ニュートンさんの性格とかの話題が続く一方で、「物理学的な解説」はほとんどなかったので、とても気楽に読めました(笑)。
この章の終わりには、ニュートンさんの『プリンキピア』が暮らしを一変させたものとして、「機械工学」、「ジェット・エンジン」、「翼」、「人工衛星」についての説明もあります。
そして各章とも、これと同じような構成になっているので、有名な物理学の研究や概念の概要を把握できるとともに、それが生まれた時代背景や経緯、それが世の中をどう変えてきたかを、じっくり学ぶことが出来るのです。
しかも有名な物理学者の先生たちも、必ずしも恵まれた子供時代を過ごしてきたわけではないことを知ることができて、この本は「伝記」としても読みごたえがありました。
個人的に面白く感じたのは、「4日目 1861年3月11日 マクスウェル「物理的力線について」発表」で、マクスウェルが、数学的モデルが既知の物理的状況になんらもとづいている必要はないと気づいたことで、科学的なモデリングが始まったということ。
「(前略)マクスウェル以来、現代の物理学者は、自然界で生じていることに即した数値を生み出す数学システムを構築することで、周囲の世界の理解を深めようと試みている。」
と書いてありました。数学モデルを使うことは今では当たり前のことで、「1日目(1687年)」にはあったのかと思っていましたが、そうではなかったんですね……。
また「なるほど」と思ったのは、「8日目 1947年12月16日 実用的なトランジスターの最初の実演」からは、暮らしを一変させるような新しい物理研究が、個人ではなくチームによる作業が中心になってきたこと。この頃になると多くの科学的知見が積み上がり、人間の社会も複雑になってきたことで、「暮らしを一変させる」ためのハードルがとても高くなって、一人の天才だけでは成しとげられなくなってきたのかもしれません。
そして最終章の「11日目 ?」には、今後「暮らしを一変させる」ものになる可能性のある4つとして、「AI(人工知能)」、「AR/VR(拡張現実と仮想現実)」、「量子コンピューティング」、「核融合」などがあげられていました。これらも納得の選択だと思います。今後、これらが、私たちの暮らしを、より良いものに変えていくことを期待したいと思います。
『私たちの生活をガラッと変えた物理学の10の日』……熱力学、超電導、トランジスター、発光ダイオード、核融合、インターネットなど、科学的発見の歴史を探索するブレイクスルーの科学史を知ることができて、とても参考になりました。みなさんも、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。
『私たちの生活をガラッと変えた物理学の10の日』