ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
数学・統計・物理
透明マントのつくり方(グバー)
『透明マントのつくり方 究極の〝不可視〟の物理学』2024/8/23
グレゴリー・J・グバー (著), 水谷 淳 (翻訳)
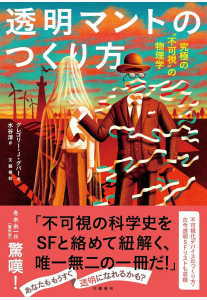
(感想)
SF『透明人間』や、ファンタジー小説『ハリー・ポッター』の透明マントなど、「人/物を不可視にする」ことは常に人を魅了します。実はなんと今や、「光をよけさせて、目に見えないようにする」技術が真剣に研究されて試作品までできているそうです。そんな「透明化」の科学史を、まさにその研究を最前線で行っている科学者のグバーさんが解説してくれる本です。
『透明マントのつくり方』というタイトルだったので、面白空想科学の解説本かなーと想像していたのですが、「不可視」とはどういうことなのか? について真剣に深く掘り下げて解説してくれる本でした。
ニュートンが述べた光の性質にはじまり、「目に見えない光線」赤外線の発見や、いわゆる「偏光」の発見などを経て、光の正体は徐々に明らかになってきています。
そしてX線の発見が巻き起こしたフィーバーと、そこから生まれた史上最も有名なSF『透明人間』。さらに原子構造の解明からはじまった、現代の「不可視化」の科学は、量子力学を経て、空間をゆがませて光を迂回させる特性をもつ物質「メタマテリアル」の着想へと至っていきます。
……この本は、完全に「物理学」の本ではありますが、光の性質を解き明かすのに役立った発見や理論を生み出した科学者たちの伝記も紹介されているので、物理や数学が苦手でも読みやすく、興味津々で読み進められました。
前半の「科学者たちの光と物質の正体の解明」の解説で、不可視化現象への理解への準備がちょっぴりできてきたかなーと思い始めたところで、ミルトン・カーカーが著した「不可視物体」というシンプルなタイトルの論文から、「不可視研究」についての話が始まっていきます。その一部を紹介すると……
「カーカーのこの不可視物体は、光散乱の基本的な物理に基づいている。物体に光が当たると、電磁波によって物体中の電子が振動し、そのときに光のエネルギーの一部が電子へ移動する。するとその電子が加速して新たに電磁波を発生させ、それが散乱光となる。カーカーは、中心核と外殻からなる小さな球形粒子をつくって、それを水などの液体中に浮かべるとイメージした。そして、中心核の屈折率が液体の屈折率よりも低く、外殻の屈折率が液体の屈折率よりも高いというケースを考えた。そのような場合、中心核の電子が上向きに加速すると、外殻の電子は下向きに加速し、その逆も成り立つ。そのため、中心核から発生する電磁波の位相と外殻から発生する電磁波の位相が完全にずれ、相殺的干渉によって完全に打ち消し合う。散乱光が発生せず、当たってきた波はそのまま通過するため、その粒子を検知することはできない。不可視なのだ。」
…………え? なんですって?
このあたりから、だんだん「理解できなさ」が強まっていって、ちょっと凹みながら読み進めていきました……。
透明化の方法としては……
・相殺的干渉を引き起こすことで、隠したい領域から外へ散乱場がけっして出て行かないようにする
・不可視化クローク:中央の隠したい空間の周囲に光を迂回させて、まるで何も出会わなかったかのように反対側へと導く空間の歪みを使う
・変換工学を用いた光学的ワームホール(光の波だけを通過させる通路のようなもの)
*
……などなど、不思議で、本当に実現可能なの? という方法があるようです。
また「透明化」ではありませんが、「光を吸収する」方法もあり、これに関しては「2019年、MITの工学者が、当たった光の99.995%を吸収するカーボンナノチューブ素材を開発」した事例もあります。
えーと……全体としては『透明マントのつくり方 究極の〝不可視〟の物理学』という、興味を引くタイトルにふさわしい内容で、物理学が苦手な人でも、それなりに楽しく読み進められるよう、うまく工夫されているなーと感心させられる本でした。
なんと巻末には「おうちで作れる透明化デバイス」(笑……本当につくれるのかどうかは不明ですが)、さらに「古今透明SF小説リスト」という付録もついています。
面白くて勉強にもなる本なので、みなさんも、ぜひ読んでみてください。物理は苦手だけどSFは好き、という人には特にお勧めです☆
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。
『透明マントのつくり方』