ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
健康&エクササイズ
今と未来がわかる 老化の科学(中西真)
『今と未来がわかる 老化の科学 (ビジュアル図鑑)』2024/1/17
中西 真 (監修), 新井 康通 (監修)
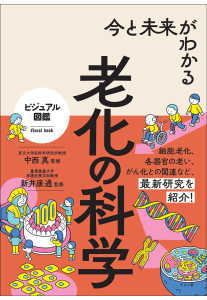
(感想)
人生100年時代に向けて知っておきたい老化の基本や最新研究を、イラストで分かりやすく解説してくれる本で、主な内容は次の通りです。
INTRODUCTION 老化とは何か?
PART 1 老化の基本
PART 2 身体機能の老化
PART 3 各器官の老化
PART 4 老化にともなう病気
PART 5 老化とがん
PART 6 老化研究の最前線
PART 7 老いを防ぐには
*

「老化すると臓器や組織の機能が衰えていきます。その理由として挙げられるのが、臓器や組織の萎縮です。つまり縮んで容積が小さくなるのです。」
……なんと「脳」も神経細胞の減少により委縮して、脳の表面のしわが深くなるようです。脳の「しわ」は委縮によっても深まるんですね……(涙)。
本書の前半では、「老化とは何か」、「老化で起こりやすくなる病気にはどんなものがあるか」などについて学ぶことが出来ました。
そして「PART 6 老化研究の最前線」からは、いよいよ「老化への対抗」を期待させてくれる研究成果の紹介が始まります。
ここでは、老化研究の参考にされている動物として、「老化しない動物」と言われているカメやゾウの他、不老不死に近い動物としてクマムシやヒドラが次のように紹介されていました。
「(前略)クマムシは乾燥させると細胞の代謝機能が停止し、完全な休眠状態に入ります。真空中や放射線下といった過酷な環境下でも、乾燥している限り、環境のせいで死ぬことはないと言われています。
また淡水に棲むクラゲのような無脊椎動物ヒドラは、寿命が3000年ともいわれています。ヒドラは親の個体から子が生まれる「出芽」という方法で無性生殖し、自分の複製をつくりながら生き続けるのです。また再生能力も高く、体が切られても分割し、それぞれが個体のヒドラになるという性質があります。」
……うーん、凄い生物たちですが……人間がこの方法で不老不死になるのは、かなり無理かも(苦笑)。
それでも、もっと小さい細胞レベルの研究では、なんと「老化細胞を除去」する薬が生まれているようです。
実は、老化細胞を生きのびさせるGLS-1酵素というものがあるようです。
・「細胞が老化すると、傷ついたリソソームの膜から酸性物質が漏れ出して細胞全体が酸性になるが、GLS-1酵素の発現で中和されて老化細胞が延命する。」
……ならばこのGLS-1を阻害すれば、その結果として老化細胞を除去することができるのでは? と考えたことで生まれたのが「GLS-1阻害薬」。実際に、効果があるようです。
「GLS-1阻害薬を含むセノリシスが注目を浴びている。そのなかでも、老化細胞だけを狙いうちし、副作用の少ない老化細胞除去ワクチンに期待が集まっている。」
……GLS-1阻害薬には、慢性腎臓病の治療薬としての効果も期待されているようで……本当に老化細胞だけを正しく片付けてくれるなら、副作用の少ない素晴らしい薬になりそう……今後の発展に期待したいと思っています。
この他、iPS細胞についても……
「山中因子を導入してリプログラミングしたiPS細胞を、各臓器の細胞に分化させる再生医療が行われている。リプログラミングを若返りに利用する研究も進められている。」
……将来は「老化」を除去して自らの細胞の力で「若返り」……なんてことが可能になると良いですね!
また「PART 7 老いを防ぐには」では、現時点で私たちができる「健康寿命延伸のための提言(厚生労働省「e-ヘルスネット」より)」についても知ることが出来ました。
「健康寿命延伸のための提言」の概要とは……
1)喫煙:禁煙する。受動的喫煙も避ける。
2)飲酒:飲むなら節度のある飲酒。
3)食事:適正量のバランスのよい食事
4)体格:ライフステージに応じた適正体重を維持。
5)身体活動:日頃から活発な身体活動を心がける。
6)心理社会的要因:心理社会的ストレスを回避。睡眠時間の確保・質を向上。
7)感染症:肝炎ウイルスやピロリ菌の感染検査を受ける。インフルエンザ、肺炎球菌を予防する。
8)健診・検診の受診と口腔ケア:定期的・適切に検診受診。口腔内を健康に保つ。
9)成育歴・育児歴:出産後初期はなるべく母乳を与える。将来の疾病に注意する。
10)健康の社会的決定要因:社会経済的状況、地域の社会的・物理的環境、幼少期の成育環境に目を向ける。
*
……ということで、普段から一般的な「健康的な生活」を心がけていれば、「老化」も防止できるようです。
さて、日本は世界的に見ても「長寿」の国ですが、センテナリアン(100歳を超えて長生きした人)には、医学的にみて、糖尿病になりにくい、動脈硬化が起こりにくいなどの特徴がある他、栄養状態がよいグループほど炎症反応も少なく、「外向性」「開放性」「誠実性」が高いそうです。
さらに110歳を超える人のことをスーパーセンテナリアンというようですが、2020年の国勢調査では、日本では100歳越えの79,523人に対し、110歳越えはわずか141人で、その研究には困難があるようです。
そんななか実施されているのが「シングルセル解析」で……
「(前略)近年では、シングルセル解析という手法が注目されています。シングルセル解析とは、一細胞レベルで遺伝子発現やゲノムの状態を解析する技術のことです。たとえば亡くなったばかりのアルツハイマー型認知症の患者さんから抽出したサンプルを細胞ごとに解析するといった研究が行われ、認知症と遺伝子やDNAの関連性が発表されています。このように、実験動物でわかってきたことが、シングルセル解析を使うことによって、人間の細胞でも検証できるようになってきているのです。」
……細胞の研究で、治療や老化防止に役立つことが見つかることに期待したいです☆
また今後の「介護予防」を進めていくためには、次の技術がカギを握っているそうです。
1)介護保険のビッグデータ解析
2)介護ロボットの開発
……これらの技術もどんどん進んでいくと良いですね。
『今と未来がわかる 老化の科学』……老化についての科学的解説とともに、健康長寿を維持するために私たちが出来ることについても教えてもらえる本で、とても参考になりました。みなさんも、ぜひ読んで(眺めて)みてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。
『今と未来がわかる 老化の科学』