ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
防犯防災&アウトドア
防災
2040年の防災DX(村上建治郎)
『2040年の防災DX』2025/1/31
村上 建治郎 (著)
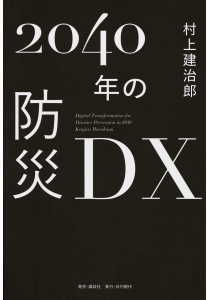
(感想)
防災テックベンチャーSpectee(スペクティ)のCEOの村上さんが、2040年の防災の未来像と最新の防災技術、それにかかわる防災の受け入れの問題点を徹底的に解説してくれる本で、主な内容は次の通りです。
第1章 2040年、「防災DX」はここまで変わる
第2章 日本の自治体の課題・問題点
第3章 企業における防災DX戦略
第4章 グローバルケーススタディ(世界の自治体、企業)
*
「はじめに」には、令和6年能登半島地震で、輪島市の住所の記載とともに「夫婦が建物の下敷きに」というフェイク投稿があったという事例が紹介されていました。これを読んで消防局が駆けましたが、夫婦は無事で住宅の損傷も軽微だったそうです。それでもこのフェイクをした同じアカウントは発信を継続、その閲覧数は全体で7200回になったのだとか(インプレッション稼ぎと推測されます)。こういうフェイク投稿は本来必要な救助を遅らせ、人的被害を拡大させるだけなのに……(涙)。
防災テックベンチャーSpectee(スペクティ)は、災害時のファクトチェックもしているそうです。
「スペクティではAIなどを活用して情報の真偽を判定する技術に加え、チームで投稿の真偽を見極めるファクトチェックの体制を整えており、SNSに飛び交う無数の投稿から正確な情報を自治体をはじめ関係機関に提供している。投稿された場所を地図上にプロットし、投稿者のアカウントをさかのぼって確認、その地域で暮らす実在の人物なのか、現場で投稿できる可能性があるのか、そういった細部までを確認し、真偽を見極めていく。」
……とても素晴らしい活動だと思いますが、災害を利用した偽情報でインプレッション稼ぎができる仕組み自体がなくなればいいのに……とも考えてしまいました。災害や選挙時の偽情報問題には、プラットフォーム側でも何らかの対処をして欲しいと願わずにいられません。
さて「第1章 2040年、「防災DX」はここまで変わる」からは、次の6つの観点から考える近未来の防災の姿が描かれていました。
1 AI:AIを活用した防災事例
AI活用の気象予測、停電予測。IoT情報や自動車の走行データの活用など。
2 ドローン:災害支援活用
ドローンによる上空からの災害状況の確認、夜間の上空からの照明、水中捜索など。
3 ロボティクス:災害支援活用
ロボットによる災害状況の確認。災害時に自動で水やがれきの中を進める遠隔操作クローラーロボットなど。
4 デジタルツイン(現実の世界をそっくりそのままデジタルの世界で再現するもの)
シンガポール政府による都市計画利用。日本の「PLATEAU(プラトー)」など。
5 人工衛星:衛星の画像解析技術、衛星利用のインターネット接続サービスなど。
6 インターコネクティッドの世界:医療用ウェアラブル端末、家電やSNSからの情報利用など。
*
例えばドローンには、すでにかなりの能力があるようで、2024年現在、市販されているドローンでも100kg程度の重さなら楽に運搬が可能なのだとか。
また欧米の軍事技術がベースとなって発達してきたUGV(無人地上車両)は、能登半島地震でも試験的に導入されたそうです。カメラとセンサーを用いて視界環境を共有、10kg程度であれば荷物の搭載も可能なのだとか。
欧米は「軍事目的」でドローンやロボティクス技術をどんどん進めているようですが、災害大国日本は、「防災目的」でドローンやロボティクス技術をどんどん進めるべきではないでしょうか。例えば、災害時に自動で水やがれきの中を進めるサンリツオートメイションの遠隔操作クローラーロボットは、普段は地下水路や配管の保守点検に使用でき、災害時には復興支援に転用できるそうです☆
またデジタルツインは……
「防災の観点から言えば、デジタルツインを使うことで災害発生時の被害の広がりを精密に再現することができるため、様々な災害を想定した避難訓練をバーチャルで行ったり、避難拠点の備蓄状況を可視化したりすることができる。
また道路の混雑や普通、各種インフラの弱体化といった状況を想定して、支援や避難における最適解を導きだすなど、精度の高い使い方が可能となるだろう。
また、単に被害状況をシミュレートするだけでなく、長年の懸案であった災害の「予測」にまで応用することも可能だ。」
……なるほど。デジタルツインはデータの作成・更新が大変そうですが……都市計画や、防災のためのシミュレーション・予測では効果を発揮しそうですね。なお日本は、Society5.0(サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会)を計画しています。
続く「第2章 日本の自治体の課題・問題点」では、防災DXをはばむ壁として、次の3つが挙げられていました。
1)予算の壁:自治体などには先進技術を知っている人材が少ない。
2)庁内の壁:自治体の防災担当者も異動してしまう。「公平性」の壁が効率化を阻んでいる。
3)地方議会の壁:役所だけでなく議会にも上記の問題がある。
*
ここでは自治体における先進的防災DX活用事例として、福井県のケースが紹介されていました。なんと福井県は、県民衛星「すいせん」を打ち上げ、画像解析に活用するなど先進的な取り組みを進めているそうです。その他にもWebサイトやSNS、クラウド型の道路施設データベースなども活用していて、とても参考になりそうでした。
さらに「第3章 企業における防災DX戦略」では、日本政府の「GX(グリーン・トランスフォーメーション)実現に向けた基本方針(2023年)」や、大学発ベンチャーや企業を支援する動き、企業のBCMなどに関する解説がありました。
BCMとは事業継続マネジメントのことで、自然災害、火災や事故、戦争、テロ、サイバー攻撃によるリスク事象が生じても、重要な企業活動をストップさせないよう、計画をあらかじめ用意して、事業を止めないように管理運営していこうというものです。例えば……
「イオンのBCMは「情報インフラの整備」「施設における安全・安心対策の強化」「商品・物流におけるサプライチェーンの強化」「事業継続能力向上に向けた訓練計画の立案と実行」「外部連携の強化とシステム化」の5分野からなっている。」
……とても大事な活動ですね。
最後の「第4章 グローバルケーススタディ(世界の自治体、企業)」では、OSINT(Open Source Intelligence)について紹介されていました。
OSINTとは、オープンデータをソースとした情報分析手法のこと。ウクライナ侵攻では、誰かがSNSにアップしたロシア軍に攻撃されたウクライナの街並み画像を、別の誰かが衛星画像と比較しながら繋げていき、ロシア軍の侵攻ルートを特定するなどの成果をあげています。
「イスラエルのあるセキュリティアナリストは、「情報の9割はOSINTで得られる」と言っている。Society5.0の時代には、衛星だけでなくIoTや交通、人流、ドローンなどから高品質で多彩なビッグデータが得られる。そこにAIによる分析や予測の自動化が加われば、OSINTの精度はますます上がっていくだろう。」
……OSINTの能力を磨くことは、私たちにとっても必要なことのように感じました。なお東京都は、OSINTに活用できそうなオープンデータを集約した「東京都オープンデータカタログサイト」を公開しているそうです。
ここでは、海外およびグローバル社会における防災DXの具体的事例として、次の6つについても解説がありました。
1)医療DXが進むエストニアの取り組み
2)Googleが推進するアジア・アフリカ諸国の洪水予測
3)世界に広がる中国の交通顔認証技術
4)欧州の防災都市計画スマートシティと国際連携
5)マイクロソフトのBuilding Scale VR
6)グルーバル時代に求められる、防災情報の多言語化
*
『2040年の防災DX』……これからの日本の防災や海外の防災、企業の防災への取り組みなどについて解説してくれる本で、とても参考になりました。防災に関する問題点の指摘などもあります。防災に関心がある方は、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『2040年の防災DX』