ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
自己啓発・その他
ロボット倫理学(クーケルバーグ)
『ロボット倫理学』2024/10/29
マーク・クーケルバーグ (著), 田畑暁生 (翻訳)
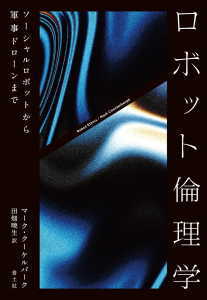
(感想)
コンパニオンロボットから軍事用ドローンまで、様々なロボット技術とその応用を考察し、それらの使用がもたらす倫理的問題点を明らかにしている本です。
国際電子工学会の定義では、ロボットとは……
「ロボットとは、環境を感知し、意思決定を行うための計算を実行し、実世界で行動を行うことができる自律型機械である。」
そして倫理とは……
「(前略)倫理が、「私たちが何をすべきか」「いかに生まれるべきか」といった規範的な問題に関わるという点においては、哲学者は概ね同意するだろう。」
そして本書の目的は……
「本書は哲学上の概念や理論をロボット倫理学という分野に導入することに焦点を置き、ロボット倫理と実世界の問題との関係を示そうとする。」
……だそうです(もっともロボットも倫理も、定義がたくさんあるようですが……)。
今やロボットはかつてないほど、より自律的、知的、競争的、柔軟になっていて、次のような問題も起きています。
1)安全に関する新たな問題(高速移動ロボットが人間に衝突する危険、AI搭載ロボットの予測できない行動への危険など)
2)ネット接続によるセキュリティ問題
3)プライバシーと監視問題(ロボットへの監視が人間にも及ぶことも)
4)ロボットに仕事を奪われる問題
*
実はすでに家庭に入りこんでいる多くのロボットには、次のようなセキュリティ・リスクがあるのです。
・「個人向けロボットを家庭用アシスタントとして使うことは、こうした形の監視をされて、プライバシーと権力に対する脅威に晒すことである。声を使って対話し、人のふるまいを知るために、個人向けロボットは通常カメラとマイクを備えている。」
・「(前略)スマートドールやスマホは既にデータを集めており、それを会社のサーバーに送って分析している。」
……そう考えると、ちょっと気持ち悪いような気がします……。
さて個人的に本書で特に参考になったのは、「第5章 自動運転車、道徳的行為者性、責任」。ここでは、ロボットは道徳的行為者になれるのか? について深く掘り下げていました。
「(前略)ロボットが道徳的行為者になりうると考える研究者がおり、道徳機械を作り上げようとしている。例えば、マイケルとスーザンのアンダーソン夫妻は、人間がするような意思決定を行う倫理的行為者性を開発する目的で、「機械倫理」を提唱している。アンダーソンらは「倫理は計算可能」と考えており、機械に原理を与えて合理的な方法で理性を与えるべきで、そうすれば「人間が感情に流されて」行う決定を避けられるとしている。」
……確かに。ロボットには人間のような意思や感情はないかもしれませんが、「倫理を計算」することで、道徳的行為を覚えさせて実行させることはできそうな気がします。
その一方で次のように言っている方もいるようです。
「例えばデボラ・ジョンソンは、コンピュータシステムは心的状態や自由な行為者としての「意図」をもたない(当然ロボットもそうである)ため、道徳的行為者になるための重要な要件を欠いている、と主張する。ロボットは行為者ではなく人間(とりわけ設計者や利用者)の行動の要素に過ぎない。倫理は人間の行動に焦点を当てるべきだ。さらにロボットは、道徳的判断に不可欠な感情もない。」
……うーん。でも、そもそも道徳的判断に「感情は不可欠」なんでしょうか? ロボットと私たち人間が、共に生きていくためには「道徳的行為」が必要なのだから、ロボットがほぼ常に「倫理的に正しい」とされる行動をとれるなら、実用上、それで問題ないのでは? と考えてしまいます。……こんな風に思ってしまうのは、私たち日本人が、ロボットに親近感を持ちやすい文化の中で生きているからなのかもしれませんが……。
また自動運転や介護・医療ロボットが「失敗」して人間を傷つけることになったとき、誰が責任を持つのか? という問題についても指摘がありました。それは開発者なのか、利用者なのか、環境を整備した者なのか……ロボット自身に責任能力がなくても、被害者がいる以上、その被害を補償する必要はあるはずですが……難しい問題ですね。これについては……
「(前略)未来のテクノロジーに関しては、私たちすべてが便益を受けるだけでなく意見や利害を持っているのであり、その意味で何らかの責任を全員が負っている。」
……ロボットによる便益を、私たちすべてが受けることになるのでしょうから、ロボットによる被害が出た場合には、私たち全員が何らかの形で拠出する保険金か税金で、被害を補償する仕組みを作る必要があるのかもしれません。
自律兵器ロボット(ドローン)には、さらに多くの問題が指摘されていました(「正しい戦争なのか?」「戦争ではなく暗殺ではないのか?」「機械が人間を殺していいのか?」など)。
そして最終章では、人間中心の倫理学を超えた時に「ロボット倫理学」のとりうる選択肢として、次のもの(考え方)が挙げられていました。
1)「機械」に抗せず、むしろ人間も一種のロボットであることを受け止める(薬や補助具を使っている私たちは、すでにサイボーグとも言える)
2)人間をロボットで置き換えるという考え方ではなく、人間も、ロボットのような人間以外の存在も、関係し融合する(人間もロボットも動物も共に生きられるし、共に生きるべき)。
3)「人間を超える」ことは自然環境指向であり、人間中心ではないよりエコロジカルな「人類学」および倫理学を示しえる。(自然環境や生物への害を最小化する、環境に優しいロボットを作る。あるいは、そもそもロボットのような人工物は不要とする。)
*
『ロボット倫理学』……倫理という側面からロボットについて深く考察している本で、とても参考になりました。「ロボット」にはいろいろな種類があり、また「倫理」にもいろんな捉え方・考え方があるので、すっきり整理されていたわけではありませんが、さまざまな考え方を知ることが出来て有意義だったと思います。興味がある方は、ぜひ読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『ロボット倫理学』