ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
医学&薬学
基礎からわかるハイリスク薬 第3版(浜田康次)
『基礎からわかるハイリスク薬 第3版』2024/6/17
浜田康次 (著, 監修), 吉江文彦 (著), 山口晴美 (著), 中村由喜 (著), 小川雅教 (著)
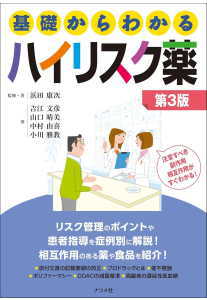
(感想)
ハイリスク薬の薬学的管理指導として、注意すべき副作用や経過観察など、リスク管理を行う上で知っておくべきポイントを、最新情報にもとづいて解説してくれる本で、主な内容は次の通りです。
1章 ハイリスク薬にかかわる薬剤師の役割
2章 ハイリスク薬チェックシートの活用
3章 ケース別 服薬指導の注意点
4章 抗悪性腫瘍薬
5章 抗不整脈薬
6章 抗てんかん薬
7章 血液凝固阻止薬
8章 ジキタリス製剤
9章 テオフィリン製剤
10章 精神神経用薬
11章 糖尿病薬
12章 膵臓ホルモン薬
13章 免疫抑制薬
14章 抗HIV薬
15章 重篤な副作用

ハイリスク薬とは、とくに薬学的管理指導(薬剤師による適切な薬物の使用)が必要な薬剤のことで、ハイリスク薬の管理指導では、相互作用・副作用の回避や有効性の確認などが求められます。
「1章 ハイリスク薬にかかわる薬剤師の役割」には、次のように書いてありました。
「ハイリスク薬の薬学的管理については、厚生労働省の『医薬品の安全使用のための業務手順書』作成マニュアルで投与時に注意が必要と考えられる11の薬効群について、日本薬剤師会の『薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)』と日本病院薬剤師会の『ハイリスク薬に関する業務ガイドライン(Ver.2.2)』がそれぞれ業務で留意すべき点を記載しています。」
なおハイリスク薬の薬剤管理において各薬効に共通する5項目は、次の通りです。
1)患者に対する処方内容(薬剤名、用法、用量等)の確認
2)服用患者のアドヒアランスの確認(飲み忘れ時の対応を含む)
3)副作用モニタリングおよび重篤な副作用発生時の対処法の教育
4)効果の確認(適正な用量、可能な場合の検査値のモニター)
5)一般用医薬品やサプリメント等を含め、併用薬および食事との相互作用の確認
※アドヒアランス:病気に対する治療方法について、患者が十分に理解し、服用方法や薬の種類に十分に納得した上で実施、継続すること
*
そして「4章 抗悪性腫瘍薬」からは、いよいよ各疾患で使われる代表的な薬剤が、具体的に解説されていきます。
疾患別に代表的な薬剤の商品名、剤形、用法、用量はもちろん、投与禁忌の情報、飲み忘れ時の対応、副作用の有無、重篤な副作用発生時の対処方法の指導などの解説の他、他の薬剤との相互作用について、併用禁忌、併用注意でのポイントから、相互作用のある対象薬剤や薬効群、食品に対して、本剤と併用薬の作用の増強、減弱も分けて記載されています。
例えば「4章 抗悪性腫瘍薬」では、まず「抗悪性腫瘍薬」全般について、次のような概説があります。
「抗悪性腫瘍薬は、がんの成長を抑制し、症状を改善する効果が期待される薬剤の総称です。一方、抗がん薬(剤)は、がん細胞を攻撃し破壊する効果(殺細胞性)があり、がんの転移や再発を防ぎ、生存率を向上させることが期待されている薬剤であり、抗悪性腫瘍薬の1つと捉えられています。抗悪性腫瘍薬には、そのほかに分子標的薬、ホルモン療法薬などがあります。」
ここではアルキル化薬、代謝拮抗薬などとともに、プラチナ(白金)製剤というものが紹介されていましたが、プラチナ(白金)製剤とは……
「白金化合物がDNAに結合し架橋形成を起こすことで、抗腫瘍効果を発揮します。」
……というもののようです。白金化合物は「DNAに結合し架橋形成を起こす」ことが出来るんですか! 驚きでした。
この章では、化学療法における薬剤師の役割も、次のように書いてありました(一部の抜粋紹介です。)
「最も重要なことは「がんが告知されているかどうか」の確認です。最近は告知が一般的ですが、告知されていないケースもあり、重大な事態に陥ることもあります。薬剤師は、医師と患者がコミュニケーションをとるためのメッセンジャーとして重要な立場です。」
そして「化学療法で求められる薬剤師の役割」とは……
1)服薬指導
・がん治療について医師からの説明内容、治療方針を把握する。
・患者の癌治療に対する理解度を確認する。
・薬剤の効果、副作用の初期症状などについて、患者にわかりやすく説明する。
・外来化学療法において、副作用に対する患者のセルフケアをサポートする。
2)チーム医療における薬剤師の役割
・レジメンの管理。ステージに応じた標準治療、投与スケジュールなどを把握しておく。
・投与計画の確認、薬理管理、薬剤の調製などを行う。
・エビデンスに基づいた最新情報を医師へ提供する。
・他の医療スタッフと薬剤情報を共有する。
・想定される副作用の対策を検討する。
※レジメン:薬物治療における薬剤の種類や量、期間、手順などを時系列で示した計画
*
……だそうです。
とても参考になったのが、「コラム:医薬品情報の活用方法」。その一部を以下に紹介します。
「(前略)まず、医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページで、調べたい薬剤の「審査報告書」「申請資料概要」「医薬品リスク管理計画」をざっと読み込み、治験段階の問題点と市販後の安全対策をつかみます。
次いで、「インタビューフォーム」「製品情報概要」「新医薬品の使用上の注意の解説」「重篤副作用疾患別対応マニュアル」などを参考に、「添付文書」に書いてある項目とその裏付けになる情報をリンクしながら読み解きます。
最後に、患者に服薬指導を行うために、「患者向け医薬品ガイド」「くすりのしおり」に、それらの情報を要約します。(後略)」
*
……このような感じで、ハイリスク薬の種類ごとに詳しい解説があるのです。
ハイリスク薬は身体の状態を大きく変えてしまうので、問題が起きたときに素早く対処することが重要なようで、「7章 血液凝固阻止薬」では、「抗凝固薬に対する中和薬」があることが説明されていました。
ちょっと驚いたのが「11章 糖尿病薬」。糖尿病というのは割とありふれた病気のように感じていましたが……使われているのは「ハイリスク薬」なんですね……。
『基礎からわかるハイリスク薬 第3版』……薬剤師の方が薬局で服薬指導を行うときを想定しているという、経口薬を中心とした専門家向けの解説本でした。各薬について、それがどのように働くものか、リスク管理のポイント、代表的な薬剤の商品名、副作用や併用禁忌などが分かりやすく、まとめて書かれています。薬剤師の方はもちろん、家族やご自身がハイリスク薬を使っている方にも、とても参考になると思います(ただ……自分に処方されている薬について詳しく知ることは、自分の病気についてもリアルに詳しく知ってしまうことになるので……読むほうがいいのかどうかは難しい問題でもありますが……)。興味のある方は、読んでみてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『基礎からわかるハイリスク薬 第3版』