ちょき☆ぱたん お気に入り紹介 (chokipatan.com)
第1部 本
工作(紙以外)
建築環境デザインのディテール(荻原廣高)
『建築環境デザインのディテール 光・熱・風・水・音』2024/12/3
荻原 廣高 (編集, 著), 花岡 郁哉 (編集, 著), 青木 亜美 (編集, 著), & 3 その他
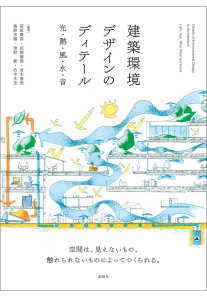
(感想)
光、熱、風、水、音といった環境を建築デザインにどう生かしていくのか、その発想のポイントをビジュアルに解説。さらに、環境の視点から優れたデザインを実現している18事例を紹介してくれる本で、主な内容は以下の通りです。
建築環境デザインの設計フロー
Step 1 気候を読む
Step 2 与条件を捉える
Step 3 周辺と調和する
Step 4 背景からつかむ
Step 5 環境性能を定める
Step 6 コンセプト・ディベロプメント
光をいざなう
熱をあやつる
風をうながす
水をめぐらす
音をとどける
ヴァナキュラー建築と建築環境デザイン
座談会 建築をつくることは,環境をつくることである。
荻原廣高×花岡郁哉×青木亜美×海野玄陽×清野 新×竹中大史
建築環境デザイン 手法とディテール
1 リバー本社:竹中工務店
2 EQ House:竹中工務店
3 MONOSPINAL:山口誠デザイン
4 NICCA イノベーションセンター:小堀哲夫建築設計事務所
5 みんなの森 ぎふメディアコスモス:伊東豊雄建築設計事務所
6 松原市民松原図書館:MARU。architecture+鴻池組
7 コープ共済プラザ:日建設計 / 羽鳥達也
8 NBF 大崎ビル:日建設計 / 山梨知彦+羽鳥達也+石原嘉人+川島範久
9 アクロス福岡:日本設計,竹中工務店
10 JR熊本駅ビル:日建設計 / 小松良朗+岩田友紀+羽月喜通+青木亜美
11 東京音楽大学 中目黒・代官山キャンパス:日建設計・戸田建設一級建築士事務所設計共同体
12 高槻城公園芸術文化劇場:日建設計 / 江副敏史+多喜茂+高畑貴良志+差尾孝裕
13 新宿住友ビル RE-INNOVATION PROJECT:住友不動産(建主・基本構想・総合監修),日建設計(基本設計・実施設計・監理),大成建設一級建築士事務所(実施設計・監理)
14 一宮のノコギリ屋根:川島範久建築設計事務所
15 SHOCHIKUCHO HOUSE:西沢立衛建築設計事務所
16 淡路島の住宅:SUEP. / 末光弘和+末光陽子
17 UNIQLO TOKYO:佐藤可士和(トータルクリエイティブディレクター),ヘルツォーク&ド・ムーロン(デザインアーキテクト),ファーストリテイリング(プロジェクトマネジメント)
18 ONOMICHI U2:吉田愛・谷尻誠 / SUPPOSE DESIGN OFFICE

「建築環境デザインの設計フロー」には、次のことが書いてありました。
・「まず計画地付近の気象データを収集、分析することから建築デザインは始まる。」
・「局地風(地方風)などによって風速の大きい季節は防風対策や防雪対策が必要。一方風速の穏やかな中間期には、風力(水平)換気や重力(上下温度差)換気などの自然換気が提案できる。」
・「(前略)長寿命、高性能な設備機器の採用に加え、機器に頼らず自然の力を上手に利用して光熱水費や修繕・更新費を削減する工夫が必要である。」
・「(前略)たとえば特殊な地形の中にあったり、周辺に建物が密集していれば、敷地での風向きや風速、日照は大きく左右される。また、周辺の空気質や騒音も、空調や自然換気計画に影響を与えることもある。一方、自身の建物が周囲環境に与える悪影響を最小限にすることも、建築環境デザインにとってたいへん重要である。」
*
気象データとしては、拡張アメダス気象データの他、その地の格言や言い伝えなどが役立つそうです。
また「環境性能」には、次の3つが参考になるようでした。
・CASBEE:建築環境総合性能評価システム
・BELS:建築物省エネルギー性能表示制度
・ZEB:ネット・ゼロ・エネルギー・ビル
*
「Step 6 コンセプト・ディベロプメント」では、「風をうながす」の次の話がとても勉強になりました。換気方式には次の2つの方法があるそうです。
1)風力(水平)換気:建物に風が当たると、風上側には圧縮力が、風下側には引張力が作用する。建物内外で圧力差が生まれることで自然換気がうながされる
2)重力(上下温度差)換気:建物の内外に温度差があると空気の密度にも差が生まれ、密度の高いほうから低いほうへ風が流れる。このときに生まれる圧力差による浮力を利用して、建物下部で取り入れた冷涼な空気を建物上部の暖められた空気により誘引し、自然換気を行うのが重力(上下温度差)換気である。
*
この重力換気の「温かい方に冷たい空気が流れていく」というのは、直感的に理解しがたくて、「温かい空気は膨張して拡散する→冷たい方に流れていく」、「暖かい空気の運動量>冷たい空気の運動量→冷たい方に流れていく」はずでは? と考えてしまうのですが、そうではないようです……。お洒落な巨大ビルの中で、大きな吹き抜けになっているエスカレーターに乗っている時には、上下階の眺めを楽しみつつも「空間や光熱費のムダ遣いでは?」と心配していたのですが(苦笑)、吹き抜けにはそういう意味があったんですね。全館を温めるためには、むしろ節約できるのかも?
そして「ヴァナキュラー建築と建築環境デザイン」では、「水を使い切る」の次の2つの事例がとても興味深かったです。
・川端/滋賀県高島市針江区:ほぼすべての住戸内に自噴する水が湧き出ている。野菜の保存、食器などの洗浄に。食べ物屑が魚の餌に。最後には琵琶湖に。
・港南区総合庁舎:大量の地下鉄湧水を庁舎へと誘導し、空調用熱源として利用している。利用された水はろ過され、屋上緑化の散水、トイレ用洗浄水、災害時マンホールトイレの用水としてカスケード利用される。
そして「建築環境デザイン 手法とディテール」では、建築環境デザインの特徴が現れた18の事例が詳しく紹介されていました。
例えば「1 リバー本社」は……
「(前略)緩やかにつながる有機的な空間に適度に緩和された自然光とそよ風と取り込んでいる。建物の中央の吹き抜けや外壁の形状は、シミュレーションを重ねることで、場所ごとのアクティビティ(デスクワーク・ミーティング・移動)に適した光環境になるようチューニングした。」
……などの事例の他、「松原市民松原図書館」「アクロス福岡」や「高槻城公園芸術文化劇場」などの公共の建物や、一般住宅、リノベーションの例もあります。
この中でちょっと気になったのが、「4 NICCA イノベーションセンター」……
「自然光を利用した明るさ確保と日射熱除去を両立するため、コンクリート天井スリットが計画されている。スリットに角度をつけることで直達日射を反射・拡散し柔らかい光として室内に取り入れるとともに、スリットに埋設した配管には豊富な地下水を利用した冷却水を流すことで、日射熱は室内に取り込まない仕組みとなっている。地下水は室内の放射(輻射)空調・研究用途・トイレ洗浄・融雪などにも利用し、井水ポテンシャルを最大限生かした建築である。」
……これ、最初に読んだときは、素晴らしい仕組みだなーと感心してしまったのですが、よく考えてみると「結露問題」はないのでしょうか? とても気になりました。これらの事例には、「実際に目的の効果が得られたのか」「予想外の問題はなかったのか」「経年変化による問題はなかったのか」も知りたかったと思います。「建築環境のデザイン」には、そういう視点も重要なのではないでしょうか。
『建築環境デザインのディテール 光・熱・風・水・音』……光、熱、風、水、音といった環境を建築デザインにどう生かしていくのかのポイントと、多数の事例を紹介してくれて、とても勉強になる本でした。興味のある方は、ぜひ読んで(眺めて)みてください。
* * *
なお社会や科学、IT関連の本は変化のスピードが速いので、購入する場合は、対象の本が最新版であることを確認してください。
Amazon商品リンク
興味のある方は、ここをクリックしてAmazonで実際の商品をご覧ください。(クリックすると商品ページが新しいウィンドウで開くので、Amazonの商品を検索・購入できます。)
『建築環境デザインのディテール』